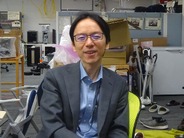KPIを導入
現在、ドコモグループではドコモ本社と地域会社、関連グループ会社でそれぞれ主要業績指標(Key Performance Indicator:KPI)あるいはバランススコアカード(BSC)が導入されており、BIによるKPIや関連する指標のリアルタイムモニタリングが展開されている(一部リアルタイムではないものも存在する)という。ここでいう関連指標とは、財務指標や管理会計指標であり、在庫回転率や時間帯別トラフィック分析などのオペレーション指標も含まれている。
ドコモでは、企業として戦略目標を定め、それに基づいてKPIを設定し、データウェアハウス(DWH)とBIにより市場のニーズを分析、市場分析から得られた結果をもとに顧客の行動予測モデルを作成、それに基づいた価格決定や製品・サービスの開発、プロモーション展開をする。そしてその結果をDWHにフィードバックしている。
経営のスピード化に活用
同社が、財務指標や管理会計指標をリアルタイムに把握するのは、「“経営のスピード化”と“アカウンタビリティの確立”という2つの理由から」(久保田氏)だという。
経営のスピード化では、システムを活用することで、情報と、業務・カネ・モノそれぞれの流れを一致させて、現実の経営の姿をリアルタイムで把握すれば、意志決定や事業計画・管理、業務処理をスピード化させるということを意味している。また、アカウンタビリティの確立は、企業としての債権と債務が発生する度にリアルタイムにシステムに入力することで、日次の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書に近いものが数日の遅延で把握できるようにすべきという考えだ。
先に挙げたオペレーション指標は、翌日あるいは翌々日には把握可能となっている。オペレーション指標をする際には、非定型検索では「View」、定型検索では「MDDB」というそれぞれシステムが稼働している。
Viewではたとえば、新規申込者やオプションサービス契約者といった顧客リストの抽出、物品在庫リストや未受取販売店リスト、経理明細リストなどの在庫情報の抽出といったことが可能だ。一方のMDDB(Multi Dimension DataBase)は、要約した情報をいくつかの次元(軸)に基づいて格納したデータベース(DB)である。MDDBではたとえば、支店別とプラン別と加入期間別のそれぞれから解約者数に基づいたDBを検索することができる。
これらをすべて含むドコモのDWHは「DREAMS」と呼ばれ、そのディスク容量は、会計データ用に87テラバイト、オペレーション指標を含む非会計データ用に128テラバイトとそれぞれ確保されている。クライアントの数はMDDB用で約3万台、View用で約2100台という巨大なシステムとなっている。
顧客行動予測モデル
ここまでがドコモのいう情報活用のレベル3だ。次のレベル4では、情報を全社的に最適化して、顧客の次の行動を予測、的確なアクションを迅速に展開することを目指している。
ドコモではこのレベル4を実現するものとして、顧客の行動を予測するシステムを活用している。これは、「同一の行動を行う顧客は、購買や解約などの消費行動も同じである」という普遍性を仮定して、顧客の行動予測モデルを作成、それをもとに企業として営業施策を展開するという仕組みとなっている。顧客行動予測モデルを活用すれば、(1)施策対象の絞り込みが容易になる、(2)施策の費用や効果が定量的に推定しやすくなる――というメリットを得られる。
「顧客行動予測モデルを活用すると、携帯電話を解約しそうな人や新たにサービスを契約してくれそうな人を見つけることができる」(久保田氏)
解約率低下に成功
携帯電話は現在、簡単に他社に乗り換えられるサービスである。いかに他社への乗り換えを防いで、解約率を低くするかが携帯電話会社にとって重要な課題となる。他社への乗り換えによる解約をチャーン解約というが、久保田氏は、顧客行動予測モデルの優位性を、チャーン解約予測分析という事例で説明した。
チャーン解約予測分析では、実際に解約する顧客にアンケートを行い、今後解約しそうな顧客をDWH上にあるデータで分析するのである。分析するために、チャーン解約しそうな、あるいはチャーン解約をしやすい顧客はどんな顧客であるかをまず百数十もの仮説を作成し、その後で仮説立証に必要なデータをDWH上からマイニングサーバに抜き出して分析用に変換、そして行動予測モデルを作ってから、仮説が正しいかどうかをシステム上で分析するという段取りで進めていくのである。
先のチャーン解約予測モデルで得られた結果をもとに、解約の可能性が高い顧客に対して営業施策を実施すると、場合によっては通常の数倍もの効率的な活動ができるという。これらの仕組み、システムによる実際のメリットを久保田氏はこう話す。 「ドコモでは、約1.0%あった解約率を0.7%にまで低下させることに成功している」
BICCを確立
このように全社的にデータを最適に活用するため、つまりレベル4を実現するために、ドコモでは「BIコンピテンシ・センター」(BICC)と呼ばれる情報分析サポート体制を2003年から確立している。
チャーン解約予測分析モデルなどは数理モデルと呼ばれる仕組みを土台としている。マイニングサーバを中心とした数理モデルの作成・分析には「一から始めると3カ月もかかっていた」(同氏)という。このため、「数理モデルを常時使える仕組みを2005年から構築しているところだ」と久保田氏は説明する。
またレベル4の施策として、同社では、ディスカウントストアや販売店、コールセンター、iモードを含むウェブサイトといったすべてのチャネルに対してリアルタイム的にアクションが取れる仕組みを構築している。