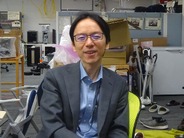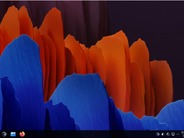前回までの連載で、情シス部門から事業部門へプロアクティブに働きかける「サービス型情シス部門」へのシフトの必要性と、組織ではなくプロジェクト単位での価値創造の重要性を述べてきた。
しかし、顧客である事業部の課題の本質を理解できない、理解できても解決するためのアイデアが出せない、アイデアがあっても活用できるテクノロジが古くてさまざまな制約をクリアできない、結果として事業部門との連携が進まず、サービス型への転換がはかれない……という負の連鎖に陥るケースが多い。今回は、情報システム部門(情シス)がサービス型モデルで成功し、進化し続けるためのいくつかのポイントに焦点を当てる。
テクノロジは経営における最大のチェンジドライバー
5年後の2020年、世界に普及するIoTデバイス数は、現在の約5倍の500億個に到達し、データ量はそれに伴って現在の約10倍量に急増すると言われている。普通に考えれば現実感のない途方もない数字だが、Android端末が世界で初めて発売されたのが2008年9月、その後2014年には年間10億台もの出荷を記録していることを考えれば、実は私たち皆がすでに経験済みのスピード感だ。
Gartnerの「日本におけるテクノロジのハイプサイクル」を2009年版と2014年版で比較して見てみると、「3Dプリンティング」「IoT」はおろか、「ビックデータ」といった今となっては一般用語と化している言葉ですら、5年前のチャートには登場してこない。
テクノロジは、進化のスピードが加速しているだけではなく、種類が急激に多様化し、影響を与える領域が急拡大しており、テクノロジの世界で行き来するデータ量はそれに伴って幾何級数的に増え続けている。社会、企業、個人、いずれにとっても、テクノロジは最大のチェンジドライバーになっていると言ってよい。
経営戦略として最先端テクノロジを活用する体制を構築する企業も
そんな中、企業経営者は「過去の成功体験を捨ててイノベーションを」と叫びはじめている。競争力のひとつでもあった「自前主義」はイノベーション創出の足かせとなり、日本企業でも外部資源を活用するオープンイノベーションが盛んになっている。
もはやテクノロジなくしてビジネスのイノベーションはあり得ない今、事業を考える上でどんなテクノロジを活用したらいいかというテーマに事業部門も取組み始めており、「だからこそ“攻めの情シス”の出番だ」というのが、本連載全体を通じてのメッセージであるわけだが、ここにきてその「テクノロジ選別・採用」のアプローチにも新しい動きが出てきている。
従来は、収益を上げている自社の既存事業に親和性のあるテクノロジを中心に、あくまで自社主導で情報を集めて検証し、安定性・安全性の高いものを選別するというやり方だった。そして強化策としては、アカデミーとのネットワーク構築、シリコンバレーへの視察調査といったものが一般的だった。
しかし最近では、事業会社がベンチャーキャピタルへの投資を通じて情報を取得する、あるいは旭化成、ニッセイなどのように自社ファンドを立上げて、ベンチャー企業を初めとする外部から最先端の情報が自然と集まってくる構造を会社として作ってしまう、というケースも増えている(図1参照)。

テクノロジを一時的な「打ち手」として扱うのではなく、継続的な情報収集を通じて、常に事業に最先端を適用し続けることを重視したこういった取組みは、テクノロジがもはや経営戦略の一部であることを意味しているといえる。