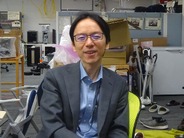人工知能(AI)は、今や誰でもサービスへ適用可能な成熟技術になりつつある。ITに縁遠い企業においても、導入を検討する段階になるだろう。一方で、実際に導入を検討してみたが、結局、できなかった/失敗したという声も聞かれる。
今後、AI活用の有無によって、ビジネスにおける優位性が格段に開いていくのは目に見えている。そのため、現段階で何としても導入を成功したいところだ。AIの導入を失敗しないためには、まず自社の問題をはっきりとし、その問題を解決できるようなアプリケーションに展開させる必要がある。つまり、「イシュードリブン(課題先行型)」な考え方を徹底することだ。では、具体的にどのようなことに気を付けてAI導入を検討していくべきかを見ていくことにしよう。
AI導入は加速するばかり
MM総研の調査によると、2018年9月の時点でAIをビジネスに導入している企業は全体の4.4%であるらしい。読者の中では、まだまだ少ないと思われたかもしれない。ただ、2017年6月の時点では1.8%だったことから、着実に増えてきていることが分かる。
業種別導入率を見ると、金融業が12.2%、情報通信業が10.0%、エネルギーインフラ業が6.0%、製造業が5.8%、サービス業が5.0%と続く。特に導入を検討中と回答した割合は金融が29.9%、情報通信が27.9%となっており、今後も導入例が増加していくものと想定される。
また、導入率の少ない業種は医療、建設、運輸であり、それぞれ2.4%、2.7%、2.8%となっている。しかし、導入を検討中と回答した割合はそれぞれ、医療が21.1%、建設が20.9%、運輸が13.8%と決して低くなく、今後このような業種からも多くの事例が出てくる可能性を秘めている。実際、これらの業種のAI活用の事例をちらほら聞かれることが出てきた。
また国内AIビジネス市場規模は2017年の時点で2568億円であり、2018年には2736億円と前年比6.5%増加する見通しである。その後も年平均成長率7.6%で拡大し、2022年度には3437億円に達すると予測している。
このように日本国内におけるAI導入はこれからが本番であり、この流れに乗れるかどうかが今後のビジネスの命運を分けると考えていいだろう。
「状況が違う」で終わってしまう「事例疲れ」
AIの導入を検討するに当たって、多くの企業では、事例調査を実施するだろう。自社の置かれている立場となるべく似たような事例をたくさん集め、それらについて徹底的に調べる。それはそれでいいことだと思う。しかしながら、その事例をもとにして、実際に導入を検討する段階で足が止まってしまうことが多い。
そこで聞かれる意見として、「この事例で成功したのはA社の環境が良かったからであって、弊社の状況とは違う」といったものだ。しかし、この意見はまっとうだ。いくら自社の状況と似ている事例を見つけて検討したとしても、細部が異なるのは当たり前だ。このような場合、いくら良い事例を集め、似たようなケースを検討したとしても、導入には踏み切れないだろう。このような状況を「事例疲れ」と呼んでもいいだろう。
もちろん、事例は導入を検討する際において非常に参考になることが多い。しかし、事例ばかりに着目すると、自分たちの置かれている状況とのギャップでなかなか導入に踏み切れなくなる。そればかりか、導入に踏み切れたとしても、それは二番煎じとなってしまうだろう。
この状況に陥らないためには、自分たちの抱える問題を明確にし、その問題点を解決するようなAIの導入を心掛けることが重要である。つまりイシュードリブン(課題先行型)な考え方を徹底することだ。
もちろん、全てのイシュー(課題)がAI導入によって解決できるわけではない。AIで解けるようなイシューを見つけないといけないのだが、そのためにはイシューを分解していく必要がある。分解されたイシューがAIで解けるのかマッチングをしていくのだ。AIで何ができるのか、それをつかむために事例は有効だ。
大事なことは、自社に事例を合わせるのではなく、自社の解決すべきイシューを解く方法として事例を参考にするのだ。このようにイシュードリブンでAI導入を検討すれば、事例疲れに陥る心配はない。当たり前だが、抱えるイシューはそれぞれ似ているかもしれないが、それぞれ異なっていることに注意しなければならない。
ビジネスに結び付かない「PoC疲れ」
最近よく聞かれる言葉に「PoC(Proof of Concept)疲れ」という言葉がある。AI導入を意気込み、実証実験にようやく移ったものの、実際の導入やビジネスに移行しないといったものだ。筆者が特に恐れているのは、PoCをやっていればAI市場の成長に追随したと思い込んでしまうことだ。PoCは社内の経験値は増すかもしれないが、それまでである。PoCから実際の問題解決やビジネスに結び付けない限りは意味がない。
PoC疲れが起こる原因として、次の二つが挙げられる。
一つは、AI導入が目的化してしまうことである。これは加熱したAIブームの弊害と考えてもいい。AIは単なるツールであって、それ単体でお金を生むことはない。AI導入が目的化してしまうと、そのプロジェクトに何の意味があったのか、そもそもビジネスとして成立するのかという問いに答えられなく行き詰まってしまう。
もう一つは、事例につられてやってしまうことである。日々生まれるAI関連のニュースを眺めてみると、一見非常に分かりやすい事例を見つけることもある。そういう事例こそ注意が必要だ。特にAI関連の事例で注意しなければならないことは、ニュースなどで流れる全ての事例がマネタイズできているわけではないということだ。
事例の中には、技術としては明確に実現できると記述されているが、それはどういう現実のイシューを解決するものなのか、どうやってマネタイズすればいいのかまでは書かれてないことが多い。そうなると、PoCで実際にシステムを動かすところまでは成功するが、ビジネスに生かす際にオリジナリティが欠如していたり、マネタイズが十分考えられてなかったりして、実サービスに移ることが難しくなってしまう。
このような状況に陥らないためには、なるべく自社での重要なイシューと、導入したいAI技術とを結び付けるのに注力することだと考える。イシューを明確にし、AI技術で解けるようなイシューに分解し、解けるものをマッチングすることだ。解決しなければならないイシューに貢献する技術であれば、導入は必然になるし、ビジネスにすることも比較的容易になるだろう。
AI技術単独ではお金を生まない。明確なイシューと結び付き、解決することで初めてビジネス化が検討できるのだ。

- 中西崇文(武蔵野大学准教授)
- 武蔵野大学 データサイエンス学部(2019年4月開設)准教授
- 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター主任研究員、デジタルハリウッド大学大学院客員教授、データサイエンティスト、博士(工学)。1978年、三重県伊勢市生まれ。2006年3月、筑波大学大学院システム情報工学研究科にて博士(工学)の学位取得。2006年から情報通信研究機構でナレッジクラスタシステムの研究開発等に従事。2014年4月から国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授・主任研究員、テキストマイニング、データマイニング手法の研究開発に従事。2018年4月から現職。現在、機械学習などをはじめとする人工知能技術をコアとしたシステムの研究開発やそれらのビジネス、サービスの立ち上げを目的とした企業連携研究プロジェクトを多数推進中。総務省「AIネットワーク社会推進会議」構成員、経済産業省「流通・物流分野における情報の利活用に関する研究会」委員、総務省「ICTインテリジェント化影響評価検討会議」構成員など歴任。専門は、データマイニング、ビッグデータ分析システム、統合データベース、感性情報処理、メディアコンテンツ分析など。著書に『スマートデータ・イノベーション』(翔泳社)、『シンギュラリティは怖くない:ちょっと落ちついて人工知能について考えよう』(草思社)などがある。