非技術系社員の取り込み
ここで問題になるのが、非技術系社員の取り込みだ。ヤフーでは、新人向けのガイドから業務に必須の情報まで、すでにあらゆる情報がWiki上にあるため、既に「使わざるを得ない」状況ができている。しかし、それでもすべての社員がいきなりWikiを使いこなせるわけではない。そこでシステム統括部では、Wikiシステムの利用を広めるために、社内キャラバンを組んで使い方を教えて回っている。
「それでもわからない場合は、メッセンジャーでシステム統括部の人に直接質問することもある」と広報の菊池氏。石井氏は、こうしたメッセンジャーによる質問、つまり「どこがわからないのか」も重要な情報の一部だという。
一方で石井氏は、Wikiそのものを通じて使い方を広めようという試みにも取り組んでいる。それは、Wiki上に作られた「みんなの広場」という練習ページだ。みんなの広場では、Wikiを使った文書の閲覧方法や編集方法、装飾の仕方などが紹介されており、その場で実際の操作を試すこともできる。業務に直接関わる書類をいきなり編集することはできないが、練習道場で使い方に慣れることができる。
Confluenceのいくつかの特徴的な機能も、社内のWikiリテラシーの向上に貢献しているという。例えばConfluenceには、「MySpace」という自分専用のページがあるが、人によってはこのページを練習場所にして、子供の写真を貼ったり、個性を出した飾り付けをしたり、ブログ的なものをつくったりして、楽しみながら操作を覚えるケースが多いという。
Confluenceのもう1つの魅力は、写真アルバムなど多彩なページ表現を可能にするマクロ機能や、新たな機能を追加するプラグインが使える点だ。これらを使って、カレンダーやTo Doリストなども簡単に作成できる(同様のことはPukiWikiでもできるが、定番の方法はない)。こうしたプラグインを使ってページを装飾していると、それを見た他の社員から「やり方を教えて欲しい」と言われてノウハウの伝授が行なわれる。
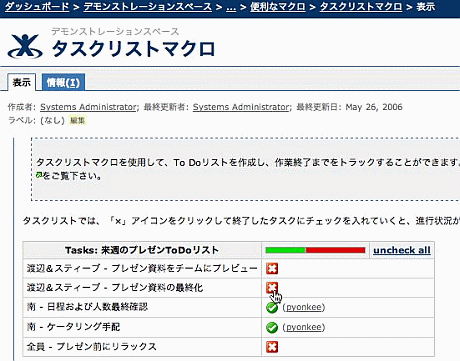 Confluenceでは、プラグインやマクロを使って、さまざまな形の情報やデータを扱う標準的手段が確立されている
Confluenceでは、プラグインやマクロを使って、さまざまな形の情報やデータを扱う標準的手段が確立されている充実したモジュールは、Wikiの応用範囲を広げ、親しみやすさを増幅するのにも貢献している。例えばみんなの広場では、投票用のプラグインを使って、人気の夕飯メニューなどのアンケートが行われていたかと思うと、同じモジュールが、冷房の温度調整のアンケートに使われたりするなどして、用途が広がっている。また、誰かが始めた個人のTo Doリストが、やがてチームを巻き込んだ「共用型のTo Doリスト」に発展することも多いという。
このようにヤフーの社内では、日々の業務のあらゆるところにWikiが入り込んでおり、社員は業務の分野を問わず、Wikiを利用している。
Enterprise Wiki導入の流れは日本だけのものではない。海外でも、北欧のNokia社で2006年10月までに5000人の従業員がWikiを利用するなど、次々と大型事例が出始めている。活用事例が広まれば広まるほど、導入障壁に関する知識も蓄積され、より導入のための改善が進むかもしれない。






