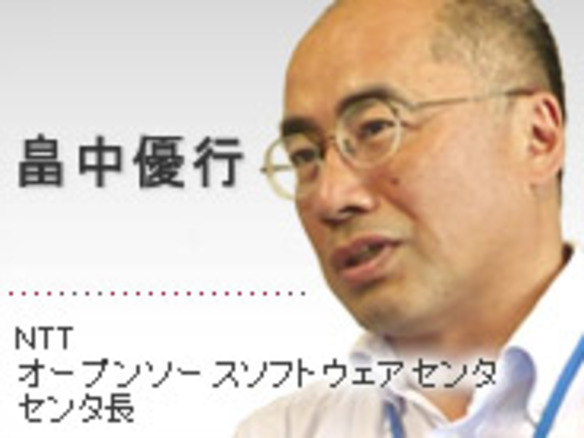この事例では、イニシャルコストを見ると、IAサーバとOSS製品の導入でハードとソフトの購入費用を削減できている。またランニングコストの点では、ソフトの保守費用はほぼ変わらないが、IAサーバを導入したことでハードの保守費用を削減できたという。
コストダウンというOSSがもたらすメリットをOSSセンタは享受しているが、そのメリットはどんなシステムでも得られるというわけではない。実際に「アプリケーション移行費用までも考慮すると逆にコストがかかってしまうというシステムもあった」(同氏)からだ。
OSSはどんなシステムにでも適用できるわけではない。移行費用といった問題のほかに、システムに求められる堅牢性や応答速度などの問題もあって、OSSはすべてを解決できる“万能薬”にはなっていないのである。そうしたことからOSSセンタでも「OSSが向いているシステムとそうではないシステムがあるので、適材適所で導入するようにしています」と畠中氏は、社内システムにおけるOSSへの取り組み方を説明している。
ソースコードを読むというメリット
OSSセンタでは、グループ会社の社内システムで利用されるOSSに対して一元的にサポートサービスを展開しているが、OSSをミッションクリティカルなシステムに適用する際の課題はどんなところにあるのだろうか。
「ミッションクリティカルなシステムにOSSを適用する際には、自分たちで検証する必要があるでしょう。また、ミッションクリティカルなシステムは、開発してから10年以上は使い続けるわけですから、10年以上という長期間にわたるサポートのスキームをどう作るかが重要になってきます」(同氏)
当然のことではあるが、システムは開発してからどう維持していくのかが重要なポイントだ。OSSの場合、開発した後でのサポート体制をどう確保していくのかが、商用ソフトよりも大きな課題となる。NTTグループ内で「Dendenkosha Information Processing System(DIPS)」と呼ばれたメインフレームの開発・維持に携わった経験から、畠中氏は、OSSをシステムに導入する際の課題を明らかにしている。
そうした課題もあることを踏まえたうえで畠中氏は、OSSを活用するメリットについてこう語る。
「OSSのメリットの基本にあるのは、やはりソースコードを読めるという点にあると思います。最終手段として、ソースコードを触ることもできるわけです。これはソフトを開発するうえでとても大事なことです。またソースコードを読むことで、ソフトがどういう風に動いているかが分かります。これはシステムが不具合を起こしたときに、トラブルシューティングをする際の重要な情報になります」
社内システムにOSSを適用するのならば、そのOSSがどのように動いているのかを理解するとともに、適用する社内システムの構造も理解しなければならない。だが、その両方ができる企業は、ベンダーに頼らずとも、システムを自ら向上させていくことができるはずだ。
 「10年以上という長期間にわたるサポートのスキームをどう作るかが重要」と語る畠中氏
「10年以上という長期間にわたるサポートのスキームをどう作るかが重要」と語る畠中氏