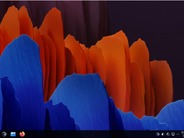Feldman氏の説明によれば、過去のデータセンターでの演算処理負荷は数は少ないが、巨大であり、複雑で相互に関連したものだったという。その場合、データセンターでの演算処理は、計画的にリソースをフル稼働させることが容易だったという。
しかし、「インターネットがすべてを変えてしまった」(Feldman氏)という。現在のデータセンターでは、iPhoneやネットブックの普及で、膨大な利用者がいつでもどこからでもアクセス可能になることで処理すべき演算は膨大な数になっている。そうした端末からのネットのアクセスは、どれも小さく、単純なものになるが、瞬間的かつ爆発的にトラフィックが増加するために、「大抵のサーバの利用率は低く、待機状態になっていることが多い」とFeldman氏は説明する。
そうした事象からFeldman氏は、現在のサーバは今の状況に適応できていないと見る。「現在のサーバは、小さくて単純な負荷の処理で、特に非効率だ。低い利用率や待機状態ではさらに非効率。サーバと演算処理負荷のミスマッチが電力問題の根本を形成している」。
そうした背景から開発されたSM10000の実際の効果についてFeldman氏は「電力コストを2億400万〜8億1500万円削減できる」という試算を示している。また設置面積が既存サーバと比べて4分の1という点からは、データセンターの設置費用も「2億1600万〜10億8000万円削減できる」という試算も提示。合計して「4億2100万〜18億9000万円削減できる」とSM10000の総所有コスト(TCO)削減効果の大きさを強調している。その削減率は75%になるという。
 ネットワンシステムズ代表取締役社長の吉野孝行氏
ネットワンシステムズ代表取締役社長の吉野孝行氏
Feldman氏が強調しているように、今回のSM10000はウェブサーバ、アプリケーションサーバ、データベース(DB)サーバという3階層で言えば、ウェブサーバとアプリケーションサーバに向いていると指摘できる。日本国内でSM10000を展開するネットワンシステムズ代表取締役社長の吉野孝行氏も、SM10000の当面のターゲットとして、ISPや通信事業者(キャリア)などを想定しているという。
吉野氏は「YouTubeなどのネットサービスに活用されるサーバと企業内で活用されるDBサーバのアーキテクチャが同じでいいのかというと、そうはいかない」と説明。「ネットサービスなどのウェブサーバのフロントエンドはI/Oをどう処理するかが問われるため、スケールアウト型で能力を増強する必要がある」としており、今回のSM10000がウェブサーバなどのフロントエンドでの活用に大きな効果をもたらすと考えている。