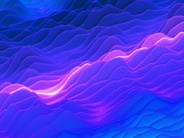ウォン安を武器に世界市場で価格攻勢をかける韓国勢に対して、シャープは円高によって価格競争に追随できず後れをとったばかりか、国内では地上デジタル放送への完全移行によって、テレビの販売台数が激減。業界全体では、2011年度下期に前年同期の3分の1の販売台数へと大幅に落ち込んでいる。
当時、ラジオを主力としていたシャープがその転換期において事業構造の変革を余儀なくされていたわけだが、約60年後の薄型テレビでも同様のことが起こったといえる。この時、ラジオメーカーはわずか1年で十数社にまで減少。そして約60年後の今は、薄型テレビ事業から撤退したり、テレビ事業を大幅に縮小したメーカーがある。
シャープは、1949年度上期業績において712万円の純利益を確保していたが、1949年度下期には一転して465万円の赤字に転落。銀行からの借入金は1950年7月には1億3200万円にまで膨れ上がっていた。1949年の株式市場の再開とともについた42円というシャープの株価は、その後、14円まで落ち込んだ。
先頃、シャープの株価が38年ぶりの安値を更新したように、株価の落ち込みぶりもかつてとまさに同じ状況だ。
この時、シャープは遊休施設を売却し、手持ち資材も売り尽くした。早川氏が個人所有する土地も安く手放したが、原料、材料の支払いにも苦慮し、それまでにはなかった従業員への賃金支払い遅延まで生じたほどだったという。
実際、早川氏は自らの手記のなかで「私は密かに、最後の覚悟も固めていた」と当時を振り返っている。そして、「家内が不吉な予感を覚えたのか、それとなく身辺を警戒しはじめて、会社の誰彼となく、夜は私のところに寝泊まりにくる始末であった」と記しているほどだった。
金融機関からは、経営の合理化を前提に資金融資の提案があったが、そこには人員削減策の実行が含まれていた。すでに社員数は588人と縮小していたものの、さらに数百人規模の人員削減が求められたのだ。
 シャープ創業者の早川徳次氏
シャープ創業者の早川徳次氏
※クリックで拡大画像を表示
実は早川氏は「人員を整理するぐらいならば会社を閉める方を選ぶ」と考えていた。これを察知した部課長クラスの社員が「このまま会社を潰してもいいのか。会社が立ち直る方法を従業員も考えよう」と呼びかけ、その活動が労働組合側で自主的な希望退職者を募るという動きへと発展していったのだ。
組合の代表からの正式な申し入れを経て、早川氏に対して210人の人員削減が提案され、その条件として1カ月の売上回収目標を1853万円とするほか、退職する社員には退職金のほかに上乗せ金、そして再雇用の際には優先的に採用すること、ラジオ1000台を支給することなどが盛り込まれた。
また、取締役の任に就いていた経営幹部も、銀行融資の個人保証をすること、取締役が持つすべての持ち株を銀行担保とすること、さらには再建に伴う組織編成の取り組みについても、白紙の委任状を早川氏にそのまま提出したという。
こうした労働組合と取締役たちの動きが、富士銀行(現みずほコーポレート銀行)を筆頭とする協調融資による金融支援につながり、シャープは奇跡的に倒産を回避することができた。
早川氏は「シャープの再発展は、このときの社員の捨身の行にあったといえる。そして、この時、惜しい人たちを多く失っている。生涯、肝に銘じたい」と述懐している。
その後60年以上にわたって、シャープでは「二度と人員整理をしない」という不文律が守られてきた。
それが、62年を経て、とうとう破られることになるのだ。