FlashSystemでは、ディスクドライブとしてOSに認識されるため、既存のSAN(Storage Area Network)環境に追加するだけで活用でき、導入にかかる作業負荷や運用変更を抑えながら、システム処理性能の向上を図れるという。FlashSystemの高性能を活かせる分野を波多野氏はこう説明した。
「金融や証券でのオンライン取引など、高い信頼性が求められる業務分野や、画像処理やシミュレーションなどの膨大かつ複雑な処理を必要とするハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)分野、財務や会計管理といったERP(統合基幹業務システム)、ビッグデータによるデータベース処理、データ分析、検索エンジンといった高負荷なアクセスが発生するシステム、放送や映像などのメディア分野などでも大きな役割を果たせる。性能が求められるあらゆる領域で利用できるだろう」
FlashSystemは、フラッシュメモリのチップ単位でRAIDを実装。IBM独自の「Variable Stripe RAID」技術を活用することで、障害が発生したフラッシュメモリチップは、自動的にRAIDグループから外れ、残りのフラッシュメモリが処理を引き継ぐことができる。「処理するデータ量が増えても、高い可用性と高速な処理を維持できる」(佐野氏)
ミッドレンジのディスクストレージである「IBM Storwize V7000」と連携させて活用することも可能。自動階層管理として、SSDとHDDの間で過去24時間の使用頻度に応じ自動的にデータを再配置する「IBM System Storage Easy Tier」機能でアクセス頻度の高いデータ領域を高速な記録媒体への自動的な移動を実現。1台で最大32Pバイトまでを管理できるという。
「企業全体のストレージをStorwize V7000で一元管理することで、遅延が許されないミッションクリティカルな業務にFlashSystemを活用するといったように、業務の優先度に応じた効率的なストレージ環境を実現できる」(佐野氏)
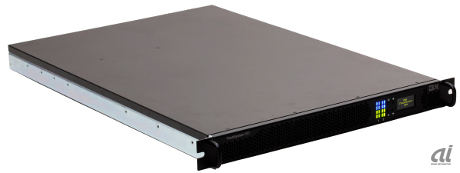
FlashSystem 820
IBMは今後3年間で、10億ドル(約1000億円)の研究開発費を投資し、フラッシュ技術をサーバ、ストレージ、ミドルウェアなどの製品ポートフォリオに統合。年内には日本(幕張)を含む世界12カ所に技術支援を行うコンピテンシーセンターを開設するという。
「コンピテンシーセンターでは、ベンチマークやIT最適化などの各種アセスメントを無償で提供する。これにより、さらに速く、効率的に、膨大なデータからビジネスに活用できるアクションを導き出せるように支援を行う」(波多野氏)
日本IBMの中にFlashSystemを専門に取り扱う組織を新たに編成。早期に試用してもらうための無償試用プログラムを提供することも明らかにした。効率化と自動化を兼ね備えたストレージを「スマーター・ストレージ」として提唱。この実現でFlashSystemは、重要な技術と位置付けた。






