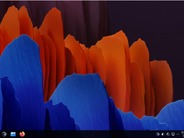米IT業界の「人材不足」は嘘?
ZuckerbergらのFWD.usが、すでに米国内にいる非市民権保持者(不法移民の子供らなど)の問題と、国外から連れてくる新たな働き手の話を分けて議論してくれると、話がもう少しすっきりとしてくるのだろうが、そう簡単に分離できない事情もあるのだろう。Max Levchinの例などを見ていてもなんとなくそのことが伝わってくる(註8)。
ただし、FWD.usが改革の錦の御旗として掲げている「米国経済の競争力の維持」、その前提となる「IT関連の人手不足緩和」については疑問を呈する声も上がっている。「科学、技術、エンジニアリング、数学(STEM)関連の学位を取得した人材の不足は実は(Mark ZuckerbergやBill Gatesなどが言うほど)深刻ではない」といった調査の結果がすでに明らかにされている。
The Atlanticが4月下旬に掲載していた「The Myth of America's Tech-Talent Shortage」という記事には、3つの大学(ルトガー、ジョージタウン、アメリカンの3大学)の研究者が行った調査の結果が紹介されている(レポートの発行元はEconomic Policy Instituteという団体となっている)。この記事には「2009年の時点でSTEM分野を専攻した大学卒業生の半分程度しか、関連分野の仕事に就いていなかった(求人に対して2倍以上の潜在供給があった)」、「本当に供給がタイトであれば人材のサラリーも上昇していたはずだが、シリコンバレーやニューイングランドのルート128沿いなど、IT関連のメッカといわれる地域では、プログラマーの平均年俸はほとんど変化がみられなかった」などという指摘(とそれを示すグラフ)が出ている。
またこの記事には、就労ビザ「H1-B」の批判派の見解も紹介されているが、それによると、本来は「米国人の人材が見つからない仕事に従事させるために連れてくる外国人向け」とされるH1-Bが悪用され、実質的に「若くて、経験の浅い、それ故に米国人に比べてサラリーの安い外国人労働者を雇うために使われている」「H1-Bビザの保持者は仕事を変わることもできず、また昇級や賃上げも難しい(ましてや、自分で会社を立ち上げ、新たな雇用を生み出すことなどほぼ不可能)」「2012年に発給された約13万5000件のH1-Bビザの約2割が、インドのTata ConsultancyやWiproなど仲介業者(昔の言い方をすると「口入れ屋」)大手4社に渡っていた」などという記述もある。
もっとも、昨年5月末(FacebookのIPO直後)にWSJに出ていた記事には、Googleなどの各社が積極的に人材確保に動いたせいで、「トップクラスの大学を出たコンピュータ科学専攻の学生は初任給(年俸)の平均が7万5000~10万ドル、さらに支度金(5000~1万5000ドル)や株式が付与される例もある」などと書かれているから、そうした人件費の高騰も一部には確かにあったのだろう。それでも何万~何十万人はいるとされる「力仕事」をこなす人材がすべてそうした恩恵にあずかっているとは考えにくい。