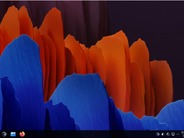音楽とビッグデータ
Eric ビッグデータを使ったレコメンデーション機能などについてはどうお考えでしょうか?
松武氏 いいんじゃないですか。利用の仕方によるかもしれないが、良いと思う。逆に教えられることもあるので、私は良いと思います。ミュージシャンからすれば、こういう時代でCDも売れないし、「昔作った音楽がまた聴かれる機会になって、いいんじゃないか」、と思うんじゃないでしょうか。ミュージシャンたちの仕事は本当に厳しい状況なので、このままでは皆廃業してしまうという勢いです。
同業者の中で、「え、xxさんミュージシャンやめちゃったの?」ということがほんとに多くなった。こんな時代ですから、ミュージシャンになりたいという若い人がいない。いたとしても行く場所が少なすぎるんです。そうは言ってもいつまでも老人がやってるわけにはいかないので、悩ましい問題です。作詞作曲、演奏をできる人は増えるだろう。ただし、スタジオミュージシャンで、楽譜を渡されたら一発でできる職人はいなくなっている。シンセサイザーをずっとやってきて、いろいろ見てきた。良い時代もあった。今が普通の状態なのかもしれません。
音楽と教育
松武氏 やはり日本は、考え直さないといけない。日本人アーティストは、自らから率先してテクノロジを使えるようにならないといけない。テクノロジという言葉がいいかどうかは分からないのですが。
Eric デジタルとアナログ、バーチャルとリアル。SNSはバーチャルと言われているが、SNSを使っている人はリアルで、リアルなコミュニケーション。実は昔とあまり変わらないかもしれない。しかしバーチャルというものについては倫理観の問題がある。近所の畑で野菜を盗るのとネット上のコンテンツを盗るというのは、両方とも「盗む」ということ。テクノロジがどうこうというより、倫理の問題です。教育が一番重要なのではないかと。
松武氏 音楽は絵と同じで自由にやらせるのがいいわけで、歌を歌って点数化して評価するというのは違うと思うんです。音痴な人やリコーダーが下手な人は、変わらない。努力の問題じゃないですしね。また、音符は読めたほうがいいが、読めなくても音楽をできる人はいるわけです。実は気仙沼の中学校でシンセサイザー教室を計画しています。シンセサイザーを見たことのない、触ったことのない人に対して少人数だけどやります。ああいう場所なので、太陽光と電池を試してみます。自然の力でもシンセサイザーはできるんだよ、というのを子供たちに見せてあげたいんです。
メッセージ:テクノは忍耐
松武氏 シンセサイザーを通して見てきたものを話したい。自分の好きな音楽をもう一回聴きませんか? 音楽を聴く時間を作りませんか、ということ。それと、良い音をもう一度考えませんかと。良い音で聴こうとする努力。自分で良い音を追求しないと、良い音は聞こえてこない。アーティストは日夜努力して良い音で作っている。このため、リスナー側も努力してほしい。もちろんイヤホンも悪くないんですがね。「テクノは忍耐」。これがないとダメ。打ち込みをやっていて、何かの拍子に消えちゃった、ということはよくある。デジタルは裏切りますからね。
Eric素晴らしいお話ありがとうございました。
松武氏のメッセージ--「テクノは忍耐」
Keep up with ZDNet Japan
ZDNet JapanはFacebook、Twitter、RSS、メールマガジンでも情報を配信しています。

- エリック松永(Eric Matsunaga)
- プライスウォーターハウスクーパース株式会社 エンターテイメント&メディア リードパートナー
- バークリー音学院出身のプロミュージシャンという異色の経歴を持つアーティストであり、放送から音楽、映画、ゲーム、広告、スマホまで、幅広くメディア業界の未来をリードする人気メディア戦略コンサルタント。アクセンチュア、野村総合研究所、デロイトトーマツコンサルティンクグメディアセクター APAC統括パートナーを経て、現職。主な著書:『クラウドコンピューティングの幻想』(技術評論社)、『イノべーション手法50 -デフレ時代を勝ち抜く経営術-』日経BPムック。GQでも連載を掲載中。その他、メディア系専門誌、ウェブメディアに執筆多数。多方面での講演も話題になっている。