IaaS/PaaS「Google Cloud Platform」が日本でも本格的に展開される。イベント「Google Cloud Platform セッション 最新技術と日本での展開について」の中で明らかにされた。
Googleは、2013年末に台湾とシンガポールにデータセンターを開設し、Google Cloud Platformのサイトを日本語化するなど、日本展開を着々と進めてきた。イベントは、PaaSである「Google App Engine」に加え、IaaSの「Google Compute Engine」を本格展開することが中心となった。
具体的には、App Engine上で仮想マシン(VM)を動作させる「Managed Virtual Machines(Managed VM)」、クラウドベースのDevOpsツールの展開、提供価格の値下げ、継続利用による価格の自動値下げなどだ。米国で3月25日に開催したイベント「Google Cloud Platform Live」で発表した内容を日本でも展開することなる。
Google Cloud Platformは、App EngineやCompute Engineといったサービスと、MySQLの「Cloud SQL」、オブジェクトストレージの「Cloud Storage」、NoSQLの「Cloud Database」といったストレージサービスが主要な構成要素だ。それにくわえて、ビッグデータ分析の「BigQuery」やDNS「Cloud DNS」、MBaaS(Mobile Backend as a Service)「Cloud Endpoints」、機械学習向けAPI「Prediction API」といったサービスも展開する。

グーグル エンタープライズ部門 クラウドプラットフォーム セールススペシャリスト 塩入賢治氏
グーグル エンタープライズ部門 クラウドプラットフォーム セールススペシャリストの塩入賢治氏によると、これらは、そもそもGoogleが自社のサービスを支えるために開発したものであり、「検索エンジンの裏で動いているデータセンターとネットワーク、それらの上で動作している独自のソフトウェアとまったく同じものをユーザーが利用できるようにするもの」だという。
ここで言う独自のソフトウェアとは、巨大なデータセットに対する分散コンピューティングを支援する「MapReduce」、データベースシステム「Big Table」、大量のデータを数秒で解析するプラットフォーム「Dremel」などがある。
日本でも4月から価格変更が適応されているが、価格変更の理由としては「クラウドの特性である必要なときに必要なリソースをオンデマンドで入手できるという点に立ち返った」ことが大きいという。
「数年契約でロックインされるというクラウドのあるべき姿でない状態を払拭したい。そこで、価格の複雑化を防いでシンプルにしていくことにした。複数年契約やデポジット制度を廃止し、使えば使うほど安くなるような価格体系である“Sustained-Use Discounts”を新たに取り入れた」(塩入氏)
イベントでは、App EngineとCompute Engineについて、基本的なことから強化ポイントまでが解説された。App Engineが取り組むテーマは「アプリケーションを早く世の中に出せるような開発環境と実行環境を提供すること」「世界中からの秒間何万というアクセスがあっても落ちないインフラを提供すること」だという。
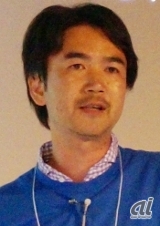
グーグル エンタープライズ部門 クラウドプラットフォーム セールスエンジニア 福田潔氏
「App Engineは特殊なPaaS環境だと思われている人がいるかもしれない。しかし、PythonやJava、Goに加え、PHPもサポートした。EclipseのプラグインとしてSDK(ソフトウェア開発キット)を提供しており、Eclipseから直接実装できるなど開発者が違和感なく使えるようになっている」(グーグル エンタープライズ部門 クラウドプラットフォーム セールスエンジニア 福田潔氏)
もっとも、App Engineでは、RubyやNoSQLの「Redis」などは未サポートだ。そうしたニーズを解決できるのがIaaSのCompute Engineになる。ポイントは「Googleが提供する各種サービスと同じ仕組みを持ったデータセンターから提供していること。スケーラビリティ、スピード、安全性、グローバルレベルでのリソース利といった、GoogleのDNAを引き継いだIaaSだ」(同氏)
Compute Engineの機能的な特徴としては「高速なインスタンス起動」「高性能永続ディスク」「高速なネットワーク」がある。“高速なインスタンス起動”というのは、クラスタのサイズを増やしても1VMあたり20~40秒程度で起動できること。要件に応じて素早くリソースを割り当てられるという。






