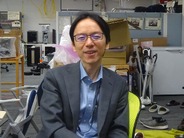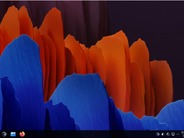オンラインだけにカネをかけるな
ビッグデータ活用の妨げになっているもう1の課題として「経営層の無理解」を挙げる現場担当者は多い。特に日本においてビッグデータ活用は始まったばかりであり、事前に明確なROI(投資利益率)を提示することは難しい。そのため、経営層がビッグデータ活用に及び腰であるケースも少なくないという。こうした状況についてArthur氏は、「米国企業でも同じような課題を抱えている」とした上で、以下のようにアドバイスする。
「現場はビッグデータ活用で。どういった問題を解決しようとしているのかを明確にすることが大切だ。具体的に課題解決の担保(ROI)がとれなくても、現状の課題とその解決策を明示すれば、経営層の琴線に触れる可能性は高い。最初はパイロット(小規模)単位で実行し、その成果と改善ポイントを開示しながら次のパイロットを実行すればよい。これであれば、『課題解決プロジェクト』として承認されるだろう」
またArthur氏は、現在のマーケティング活動予算の大半がオンライン(デジタル)に割かれていることに疑問を呈した。特に小売業においては、オンラインと実店舗では顧客の行動や得られる体験が違う。「両方の顧客体験を同水準にし、実店舗でもワンツーワンマーケティングができるようにすべきだ。そのために今後は、実店舗での行動分析が重要になる」というのが、Arthur氏の主張である。
例えば米国P&GではSNSの利用やウェブ閲覧履歴など、16種類のユーザー行動をラベリング(確認)し、自社ブランドに対して接点があるかを分析している
「よく利用しているブランドショップでは、『いらっしゃいませ』と言われるよりも『○○様、こんにちは』といわれたほうが嬉しいと感じる顧客は多い。そして自分の好みにあった商品を勧めてもらえばさらに嬉しいだろう。多くの小売業ではビッグデータ活用で、このレベルまで実践しようとしている。こうした施策は、デモグラフィックのデータ分析だけでは実現できない」(Arthur氏)
しかし、ワンツーワンマーケティングの重要性を説く一方でArthur氏は、「顧客が提供したくない情報は収集すべきでない」と警鐘を鳴らす。
「顧客の同意がないままデータ活用することは、顧客エンゲージの視点から考えれば、大きなマイナスだ。情報を提供した覚えのないブランドショップからお知らせメールがスパムのように届けられれば、だれでも不快に思うだろう。マーケティングには透明性がなければならない」(Arthur氏)