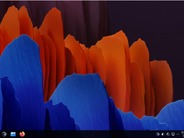そもそも、サービス仮想化は、連携するシステムの振る舞い、データ、パフォーマンスの特徴を補足してシミュレートする技術だ。実機を用意せずに、結合テストや負荷テストを早期に実施できるため、タイムトゥマーケットの短縮や品質の改善につなげることができる。マルチベンダーでの並行開発で実際の顧客データなどを参照せずに開発を進めることができるため、セキュリティやコンプライアンスの面でもメリットが多いという。
機能強化には、Needleman-Wunsch法という分析手法を使った「オパークデータ・プロセッシング(不明瞭データ処理)」が用いられているという。AI機能を使うことで、サービスプロトコルの知識やデコードなしにサービスを仮想化する。
また、学習モードを搭載しており、「新たなレスポンスを受け取ると自動的に仮想サービスを更新。次のリクエストを受けると“学習した”レスポンスを返す。少しずつ実システムに近づけていく」(渡辺氏)という。プロトコルとしては、これまでJavaの疎連携システム向けのWSDLが中心だったが、あらたにウェブシステム向けにWADL(Web Application Definition Language)やRAML(Restful API Modeling Language)、SWIFTなどに対応した。
もう1つの強化点は、モバイルアプリケーションテストの強化。「ボイジャー・モバイルテスト・ジェネレーター」という機能でファイルを検査し、ページやリンク、ジェスチャ、入力といったベンターに分解し、自動テストを生成する。「生成された自動テストからテストケースを自動生成することもできる。手動でテストケースを作成する手間を省略できる」という。
「モバイル・ラボ」というオンプレミスでテストするためのラボ環境も提供される。たとえば、iPhoneのiOS 7.1など複数のデバイスの複数のOSの環境を構築してテストできるようになった。
発表会では、DevOps & Application Deliveryプリンシパル・コンサルタントの西野寛文氏がService Virtualizaiton 8.0.1のデモを披露した。西野氏は、複数のサブシステムからなるモバイルバンキングシステムをユースケースとして、仮想サービスの生成とモバイルアプリのテストを紹介。スタブを作ることなく、トランザクションから自動的にテストケースが作られることを示した。