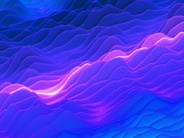10年前、企業にとってデータはビジネスの“副産物”だった。しかし、あらゆるモノがデジタル化している現在、データはビジネスを成長させる重要な“原動力”となっている。「これからの企業は、データ分析を中核に据えた『データドリブン(データ駆動型)ビジネス』を推進しなければ生き残れない」と語るのは、米Teradataで共同プレジデントを務めるHermann Wimmer氏だ。
ビッグデータ活用の普及を背景にデータウェアハウス(DWH)専業大手である同社は堅調な成長を続けている。3月5日に開催したプライベートイベント「Teradata Universe Tokyo 2015」で基調講演に登壇したWimmer氏と日本テラデータ代表取締役社長の吉川幸彦氏に、今後の事業戦略について話を聞いた。
さまざまなデータを組み合わせる
――データ駆動型のビジネスは、企業にどういった変革をもたらすと考えているか。

Teradata 共同プレジデント Hermann Wimmer氏
Wimmer デジタル化が進んだことで、あらゆる現象が可視化され、測定可能になった。すでに大規模企業は「デジタル化によるデータの可視化」と「さまざまなデータを組み合わせて分析することで得られる知見」の価値を理解している。
その好例が、自動車業界で起こっているビジネスイノベーションだろう。“IoT(Internet of Things:モノのインターネット)”とトランザクションデータの組み合わせで従来は可視化や予測が不可能だった課題を詳らかにし、その対策を講じている。ある自動車メーカーでは、エンジンやバッテリにセンサを取り付けて収集したデータとトランザクションデータを組み合わせて分析したところ、特定の課題を早期に発見。問題が大きくなる前に対策を講じることができた。
ここで重要なのは、異なる種類のデータを統合して分析し、そこから新たな知見を得られるプラットフォームの存在だ。過去においてデータ分析と言えば「トランザクションデータをどのような切り口で分析するか」が主流だった。
しかし、現在は、IoTによるセンサデータやSNSなどのソーシャルデータ、さらにオープンデータなど、さまざまな種類のデータが存在している。こうしたデータを融合させ、事業部門(LOB)がすぐにビジネスに活用できるようにすることが企業の競争力を強化すると考えている。
――LOBとIT部門の連携を最重要課題に挙げる企業は多い。どのようなアプローチでこの課題を解決していくのか。
Wimmer 近年われわれは「UDA(Unified Data Architecture)」をベースに製品を提供している。UDAは、構造化か非構造化かを問わずあらゆるデータを蓄積、管理し、分析に活用していくためのアーキテクチャだ。その中の処理プラットフォームの1つとして「Hadoop」を採用している。これは、CRM(顧客情報管理システム)やERP(統合基幹業務システム)とソーシャルデータなどを統合して分析したいという顧客の要望に応えたものだ。
われわれは2014年10月に「Teradata QueryGrid」をリリースした。これは、Teradataのデータベースとほかのデータソースをシームレスに統合する機能で、利用者は格納されているデータのロケーションを気にすることなく、分析プラットフォームの「Aster」から分析できる。つまり、分析のためにデータを移動させたり、分析を別々のプロセスに分割したりする必要がない。
こうした技術は、LOBのユーザーにとって有用だ。彼らが(分析対象となる)データの格納先を知る必要はない。こうした技術によって、LOBとIT部門のギャップは埋められるものと考えている。
データは誰のものか
――データプライバシーについて聞きたい。さまざまなデータが統合され、分析に利活用されると、データの所有権が曖昧になるとの指摘がある。ビッグデータを活用する上で企業はどんな点に留意してデータを扱うべきだと考えるか。
Wimmer データの所有権は個人のものだ。最初に明確にしておくと、Teradataはデータ分析のインフラを提供する立場である。われわれが(Teradataの顧客が管理する)ユーザーデータを持つことはない。
数年前まで、ユーザーには「無料で使えるサービスの対価は自分のデータ」との考えがまったくなかった。例えば、GoogleやFacebookが提供する機能は無料だが、それを利用するためには、自分に関するさまざまなデータと引き換えだった。チャリティでもなければ、無料のサービスはあり得ないだろう。最近、ユーザーはこのことに気が付き始めている。信頼できるサービスや企業でない限り、自分のデータを提供する以上の見返りや利便性が享受できない限り、ユーザーはデータを渡さなくなるだろう。