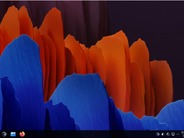また、あまり知っている方は少ないかもしれませんが、Ciscoのネットワーク装置も数年前からコンテナ対応を進めていまして、今では、CatalystやNexus、「ISR」「ASR」などのルータやスイッチは、すべて“コンテナレディ”なんですね。それによって何が嬉しいかというと、たとえばOpenFlowやREST API対応など、いろいろな上位層からのリクエストを装置が受信してIOSとやり取りしてくれる、ソフトウェアエージェントをコンテナ上に実装することにより、装置対応がしやすくなるといった例があります。他にも、セキュリティ機能や障害解析アプリケーションなど、ネットワーク装置のコンテナ上で直接、さまざまなサービスが動作するようになってきます。
発展途上のコンテナ
山下氏 Ciscoのコンテナ技術では「cgroups」がありますね。CPUやメモリなどのリソースの配分を決めるコントローラですが。

シスコシステムズ システムエンジニアリング SDN応用技術室 テクニカルソリューションズアーキテクト 生田和正氏
生田氏 技術そのものはまだまだ発展途上と言っていいと思います。例えば、Ciscoでマイクロサービスやコンテナといった技術を専門とする研究開発(R&D)部門が本社部門にありまして、そこの部門はもうひたすら作ったコードをGitHubに上げて公開したりしています。日本法人とは比較的接点が少ないのが残念ですが、OpenDaylightやOpenStackにも積極的に貢献させていただいています。
山下氏 製品を供給しているメーカーもオープンソースとの関係はとても重要視しています。IBMもOpenStackに強力な支援をコミットしています。そのうえでさまざまな製品、先ほどのCloud OrchestratorにもOpenStackを同梱させていただいています。
オープンソース製品をエンタープライズで利用しやすいようにラッピングすることは重要で、たとえばOpenStackというだけだけでは上手に使っていただけません。OpenStackだけでいきなりNovaでサーバを構成するというのもハードルが高いので、もう少し使いやすいオーケストレーションのレイヤを追加して、BPMによるワークフローを開発することで、企業内で使いやすいインターフェースを製品として提供したいと考えます。
(第4回に続く)