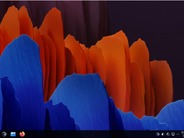本寄稿では、クラウドコンピューティングの動向について、ネットコンピューティングアライアンス(NCA)のモバイルクラウドフォーラムメンバーが、次の10年を展望し、現在の動向を解説する。モバイルクラウドが発展し、多様な形態となっていく過程をテクノロジを軸にさまざまな角度から解説していく。初回となる本記事をNCA代表の工学博士である津田邦和氏、その後、ジェナの代表取締役である手塚康夫氏、デーコムの取締役野口央氏、アプフロンティアの横山隆之氏、セキュアスマートの日高盛之氏、ソフトバンクロボティクスの首席エヴァンジェリストである中山五輪男氏が執筆する。
1995年3つの出来事があった。第一にWindowsにTCP/IPモジュールが標準装備され、第二にラリーエリソンが「ネットコンピュータ」を発表、第三にJAVAが発表された。それとともに通信インフラのブロードバンド化が進んでいた。

そこで1996年にわれわれは、ネットワークとコンピュータが新しい市場を形成することを議論していた。ASP(アプリケーションサービスプロバイダ)である。
その後固定通信網に続いて、無線のブロードバンド化、現在のLTEの計画が本格化し、2006年になると北米でiPhoneが発売され、すぐに東京で2007年にNCA(ネットコンピューティングアライアンス)メンバーが集まり、「モバイルSaaS研究会」が発足した。その後の「モバイルクラウドフォーラム」である。
このフォーラムでは、スマートフォンやタブレットと無線通信によって新しい業務システムやエンターテインメントの市場が出現することをいち早く予想し、いくつもの具体的なビジネスを創出してきた。
その後2010年以降になると、無線ネットワークとクラウドとが深いつながりをもちつつ新しいクラウドの潮流が表面化し始めた。IoT、AI、ロボット、VR/ARである。それに加えてモバイルクラウドがさらに構築しやすくなるジェネレータなどの進化が始まった。
IoTは、それまでの無線通信にWi-Fi・Bluetoothなどのバリエーションが出てきて、それらと密接な関係を持ちながら進展してきた。
AIは、1980年以前からの潮流ではあるが、クラウドの発展の中で大きく変化した。知の源泉をクラウドで集め、知的判断結果もクラウドで伝達できるようになったため、大きく発展する糸口をつかみ、新しい世代へ進展してきたといえる。その意味でモバイルクラウドと密接な関係を持つ。それらが、さらにロボットへの展開に強い影響を示している。
ジェネレータは、モバイルクラウドにおける悩ましい問題を解決しつつある。PCは圧倒的にWindowsのシェアが高いことから、あまりその他のOSを気に掛ける必要がなかった。しかし、モバイルクラウドでは、端末OSが3種類混在しており、ダウンロードアプリについてそれぞれの対応が迫られる状況にある。
これらは、Android、iOS、Windowsの3つであり、1つのアプリを展開するためにはどうしても3種類のソフトウエアを開発する必要性が出てくる。それによって開発コストが高くなってしまうのである。そこで便利になるのがジェネレータである。ジェネレータについては後述するが、ソフト開発のプログラミング工程、テスト工程、バージョンアップ工程が劇的に改善されるのである。
VR/ARについては、すでに周知のように、新しいゲーム、教育、医療、メンテナンスなどの新しいシーンで、市場が創出される徴候が見られ、クラウドとの深い関係を形成しつつある。
第2回は、ジェナの手塚氏が「IoTとAIが変えるモバイルクラウドの未来」をテーマに同日掲載している。
- 津田 邦和
- NCRI株式会社 会長
- データドック 特別顧問、ネットコンピューティングアライアンス(NCA)代表、寒冷地GEDC推進フォーラム 会長、DEECOP研究会会長、モバイルクラウドフォーラム会長、全国SaaSクラウド推進フォーラム 会長、東北SaaS・クラウドフォーラム会長。1980年代より、動的HTMLによるアプリケーションのサービス化研究、光センサータッチパネルの特許取得、インビジブルコンピューティング(のちのユビキタス)の研究等に従事し、1996年には友人たちとの共同による国内初のASPの提唱と推進団体設立を実施、関連する国際会議の事務局長等も歴任。その後20年間に20以上のクラウド関連団体役員・政府自治体委員・民間企業役員顧問等を務め、ガイドラインの作成・政府プロジェクトモデル実験・民間プロジェクト等を実施してきた。現在は、寒冷地型データセンター設計やクラウド教育カリキュラム作成、民間企業クラウド 事業コンサル、政府プロジェクト、大学講師、企業・ 団体役員顧問等に従事。札幌市出身、北海道札幌東高校卒、電気通信大学大学院博士課程修了。