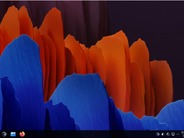未来の2つの顔
前述の無限ループに陥った問題は、人間同士であれば共有していると期待できる「常識」が共有されていなかったためでもある。もちろん設計者とユーザーといった人間同士でも同じ理由で問題を生じやすいので、UIやUXのデザインにあたっては気をつけねばならないが、ロボットや人工知能と人間との間であればなおさらである。
大規模な人工知能が社会インフラになりつつある世界で「当然の前提」と思っていたことが抜け落ちていたことにより大事故が起こりかけ、「社会がそれに依存して本当にだいじょうぶか?」「いざというときに『止める』ことができるか?」というのをスペースコロニーで実験するというのがジェームズ・P・ホーガンの「未来の2つの顔」である。
これはあまりにも大掛かりな「シミュレーション」であるが、(可能な範囲で)実験し、ユーザの行動に対するシステムの挙動を見るというのも、UXを考える上では大切なことである。
ロボット制御の身体性
アニメーションの世界を中心に「人間が(乗って)フルコントロールを行う」タイプの人型のロボットも広く描かれてきている。「どういうインターフェースがあれば人型のロボットをフルコントロールできるか」というのは非常に難しい問題なので、たいていは、操縦かんのようなものがあって(適当に)動かしている以上の描写はほとんどない。
ハインラインの「宇宙の戦士」に登場するパワードスーツのような、人間サイズで「着る」感覚に近いものであれば、人間の動作をそのまま(あるいは部分的に)トレースすることでコントロールが可能であろう。現実でも、(アクチュエータはついていないので「ロボット」の範疇に含めるかどうかは悩ましいが)人間の動作を拡大することで乗って動かす大型の外骨格、スケルトニクスのようなものが登場している。
ゲームなどでは、身体の動きを認識できるコントローラを使った部分的なトレースといえるようなタイプの遊び方をするものも見られる。
「動作のトレース」をより簡略化すると、ジェスチャインターフェースに近いものになる。不自然さや違和感の少ないジェスチャと、充分な速さの適切なレスポンス、フィードバックの組み合わせは充分に優れたUIとなり得るし、UXとしてもよいものを生み得る。それが本来の人間の身体の動作と違ったものであっても、ユーザーには「身体的」と認識することが可能となり、「身体性の拡張」と言える領域にまで到達することもある。
前出のアシモフのロボットシリーズでも、多数のロボットにわずかなジェスチャで指示を出し適切に動かせるのが、所有者としてのステータスというような描写が登場するものがある。複雑に考えを巡らしつつ操作するのではなく、ほぼ無意識レベルの何気ない動作で大きな規模の意図通りの動きが起こるというのは操作者に「素敵なUX」をもたらすことは間違いない。