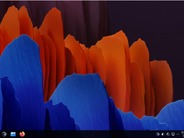デジタル時代の変革格差
以前、”デジタルバリューシフト”というテーマで記事を執筆した。「デジタルテクノロジは企業の価値そのものを変える」というテーマで、デジタル化により企業や社会をどう変えるかを紐解いていった。結局のところ、テクノロジそのものが価値を生み出したり脅威を引き起こしたりするわけではない。テクノロジを扱うわれわれが主人公であり、改めて自身の価値を見直すことが重要と説いた。
あれから2年が経とうとしているが、社会や企業のデジタルバリューシフトは進んだだろうか。自動運転技術の開発は思ったように進んでいないし、自動運転車が公道を走る気配すらない。依然として最大のマスマーケティングの手段はテレビであり、巨額の広告費の対価の指標は視聴率である。
一方で、無人店舗の「Amazon Go」のような未来を感じさせる試みも出始めており、コマツのスマートコンストラクションや、FANUCのField Systemなど、IoTやAIをコンセプトに変革に取り組む企業も多くなってきた。

進んでいる企業と進んでいない企業、その変革の格差は一体何か。その変革格差の根本は、”人”にあると確信している。筆者は、所属するウフルにて、主にIoTの概念をベースとしたビジネスコンサルティングを提供しているが、変革の可能性を一番強く感じる瞬間は新しいデジタルテクノロジと出会った時やアイデアをひらめいた時ではなく、変革をリードするであろう”人”に出会った瞬間である。
つまり、どんな素晴らしい技術も発想も、その価値を100%理解して行動につなげることができるリーダーの手に渡らなければ意味がないと感じている。
筆者はこのようなデジタル時代の価値変遷に抵抗がなく、デジタルテクノロジの恩恵を最大限に受けられるであろう人々を「デジタル人類」と名付け、本連載のメインテーマとした。
企業は今後この新しい人々をいかに味方に付けるかに腐心するべきであり、それに成功した企業が勝ち続けるだろう。連載第1回目の本稿では「デジタル人類」のアウトラインを述べようと思う。
なぜ人に着目すべきか
シンギュラリティという言葉がある。日本語では技術的特異点と訳され、人間の脳の限界を、人間と機械が統合された文明が超えていく瞬間のこととされるが、その結果多くの人間が職を失うであろうという推察とセットで語られることが多い。
では過去の(デジタルを含む)テクノロジは人間から職を奪わなかっただろうか。電話交換機は「交換手」という仕事をなくしたし、自動改札機は駅員から切符を切るという仕事を奪った。