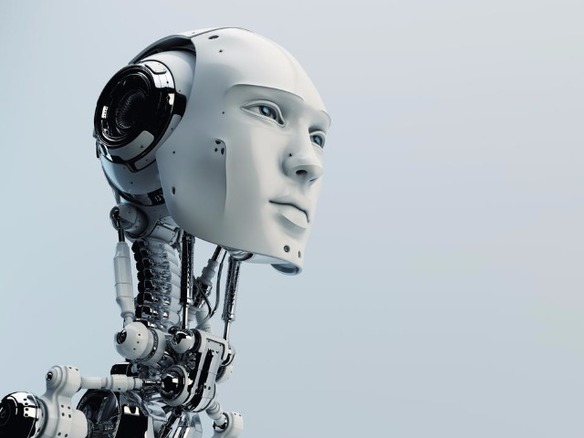インターネットが変えたもの
今や誰もが普通に利用するインターネットであるが、良く知られている通り元は軍用であった。しかし、その登場はあらゆるルールを変えていった。ショッピング、広告、コミュニケーション、コンテンツの消費……。
デジタル化できるものを全て飲み込み、人類にとってなくてはならない真の必需品となったのは、多くの人が納得するところである。10年後には昨今のIoTの概念を取り入れて現在よりももっと重要な社会インフラへと変貌していることだろう。
一方で、インターネットは「強制的なルール変更」をわれわれ人類に強いたとも言える。このルール変更について行けないと目を覆うような悲しい事例が発生するのである。
一つ例を挙げよう。世界に誇る日本の東海道新幹線は、ハイレベルな定時運行率、折り返し駅でのよどみない清掃作業と出発準備、高い安全性能など一見してスキがないように感じるが、実は世界の観光客から不評なことが1つある。
日本人としては意外な話だが、実は海外在住の観光客は「インターネットで」東海道新幹線のチケットを買えない。世界のどの高速鉄道サービスと比べても、この点は非常にマズい減点になっている。こういうものはインターネットで買える、という世界視点での常識から外れてしまっているのである。
インターネットが大きく変えたものの一つにコンテンツの消費スタイルが挙げられる。2016年「ピコ太郎」の動画が世界的に大ブレイクを果たしたわけであるが、既に1億2000万回以上の視聴回数(=高視聴率のドラマ1クール分で稼げるのべ視聴回数に相当する:図1)を稼いでいる。

図1
そして、われわれはこのコンテンツをスマートフォンで見たり、PCで見たり、そしてネットで話題の動画として取り上げられたテレビで見たりして消費し、「PPAP知らないの? これだよ、これ」といった感じでどんどん人に共有して楽しんだはずである。
さらに、この動画は世界的に共有され、関連動画の累計再生数は10億の大台も見えている。コンテンツがデジタル化されてインターネットで流通されるようになった、たったこれだけのことでわれわれのデジタルコンテンツ消費スタイルはあっという間に変化し、コンテンツを作った人への利益還元の構造も大幅に変化したのである。
変革に伴う仁義なき戦い
デジタルテクノロジとインターネット、そして今後は、IoTの概念や技術が世の中へ驚きを与え続けるであろうことに疑いの余地はないが、物事は単純に進まないのが世の常である。大きな痛みを伴う変革が起きる場合はなおさらである。
実は人類は過去に何度も「デジタイゼーション戦争」と呼べる争いを繰り返してきた。IoTの好事例として”引っ張りだこ”のイメージのあるKOMATSUの「Smart Construction」であるが、この動画で使われている建機にもデジタイゼーション戦争の痕跡が残っている。