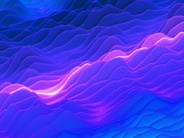人間とAIとの「共存」を超えた「共栄」はあり得るのか?
冒頭に紹介した人工知能の話に戻ろう。これまで筆者が述べてきた論旨にのっとれば、AIが人間には解読できない独自言語によってコミュニケーションを行っていたということは、使用されている言語が今回はたまたま英語であったとしても、根源的/原理的にはAIが人間とは異なる世界認識を持ちうる可能性があるということではないか?
2016年に亡くなった人工知能の父マーヴィン・ミンスキーもその主著『心の社会』(産業図書)の中で「日常的な思考のどのくらいの部分に、言葉が用いられているのだろうか?」と記している通り、言語は思考のすべてを網羅できない。Automatic(自動的)ではないAutonomous(自律的)な人工知能は、人間の使用する言語の特性とは異なる思考の道具=AIに特有の言語を自ら発明し、人間とは違う思考方法や認識様態を獲得するに至らないとも限らないだろう。今回のFacebookの人工知能研究所における「Bob」と「Alice」の件は、そうした未来を私たちに予感させてくれる。
ハンガリー出身の物理化学者・社会科学者・科学哲学者であるマイケル・ポランニーは『暗黙知の次元』(ちくま学芸文庫)の中で以下のように語っている。(マイケル・ポランニーによる『暗黙知の次元』。言語では絡め取ることのできない人間の知性=「暗黙知」の存在に論及した名著。兄は経済人類学者のカール・ポランニー)
私が人間の知を再考するにあたって、次なる事実から始めることにする。すなわち、私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができる。分かり切ったことを言っているようだが、その意味するところを厳密に言うのは容易ではない。例を挙げよう。ある人の顔を知っているとき、私たちはその顔を千人、いや百万人の中からでも見分けることができる。しかし、通常、私たちは、どのようにして自分が知っている顔を見分けるのか分からない。だからこうした認知の多くは言葉に置き換えられないのだ。
ポランニーが述べている通り「私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができる」。しかし、言葉がなければそれを記録したり伝達したりすることはできない。ドイツの哲学者であるルードヴィヒ・ウィトゲンシュタインは『論理哲学論考』(岩波文庫)において、「語り得ぬものについては沈黙せねばならない」という有名な言葉と共に「哲学は、語りうるものを明晰に描写することによって、語りえぬものを指し示そうとするだろう」と言った。人間が語りえぬものを人工知能が独自の言語で語ることができるようになったとしたら……。
そのとき、私たちとAIは「共存」というヴィジョンをはるかに超えて「共栄」という壮大な夢を実現できるのかもしれない。ただし、そのリスクをどう考えるかは人間とAIの関係にまつわる喫緊の課題と言えるだろう。