彼岸と此岸が交差するメディア空間としての紀伊半島
9月上旬、和歌山県は紀伊半島の高野山から熊野三社と呼ばれる本宮大社、速玉大社、那智大社を巡ってきた。途中、民俗学者・南方熊楠が那智勝浦の森に4年間籠って採集した粘菌等の研究のため定住した田辺にも立ち寄り熊楠翁の顕彰館を訪問したり、海上彼方に存在するといわれる補陀落浄土を目指して多くの行者が小さな船で出帆した補陀落山寺を見学したり、古来より生と死が大自然の中で奇妙に溶融/反転してきた紀伊半島という土地が持つ神秘性を堪能した旅であった。
今回の旅の行程はすべて高野山大学総合学術機構・密教文化研究所の野口博司先生が入念に組み立ててくださったものであり、興味・関心はあるものの知識の追い付かない筆者に、適宜、懇切かつ丁寧な解説をしていただいた。丸々3日間、突然思い立ったこの旅をこれ以上ない貴重な体験にしてくださった野口先生にはこの場を借りて多大なる感謝を申し上げたい。
こうした聖域や霊場などを巡る旅の話などをすると「昨今のスピリチュアルブームに踊らされてるんじゃないの?」とか、場合によっては「神や仏などと言い出して、いったいどうしちゃったんだ?」とか、妙な勘ぐりをされてしまうことも少なくないが、そもそも「メディア」というものは未知の世界の情報を既知の世界に持ち来す通路のようなものだし、彼岸と此岸の間を隔てる薄膜の浸透圧をチューニングする宗教的な祭祀や儀礼は、ことごとく非日常的な通信網の一時的な現出、つまりの現実の世界では閉ざされているメディアの扉を開放するためのプロセスにほかならない。従って「メディア」の語源に「霊媒」の意味が含まれているというのは、至って当然のことと言えるだろう。
熊野三社のひとつ速玉大社がある和歌山県新宮市出身の作家・中上健次は、自身の生まれ故郷である紀伊半島をつぶさに巡るルポルタージュ『紀州 木の国・根の国物語』(角川文庫)の中で以下のように書いている。
霊異というものを、いま一度ひらいて説明するなら、生と、性と聖と、そしてその裏にある死と死穢(しえ)と賎なるものの事であろう。生は絶えず死に転成するし、死は生に変転する。
中辺路を這うように湯の峯に来て、湯に入り蘇生する小栗判官とは、その霊異の典型であろう。聖なるものの裏に賎なるものがある。賎なるものの裏に聖なるものがある、とは小栗判官でもあり、日本の文化のパターンでもあろうが、紀州、紀伊半島をめぐる旅とは、その小栗判官の物語の構造へ踏み込む事である。
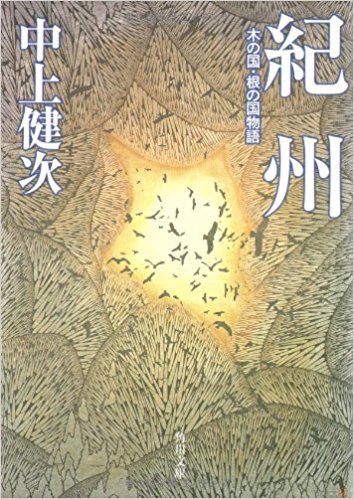
中上健次が自身の生まれ故郷である紀伊半島をつぶさに巡ったルポルタージュの傑作『紀州 木の国・根の国物語』(角川文庫)。中上文学を読み解くうえで重要な資料となる一冊
生と死、そして再生……。歌舞伎や浄瑠璃の題材として有名な「小栗判官」が業病を患い瀕死となったのち、再び生の世界に復帰するきっかけとなったのは、ほかならぬ、湯の峰温泉のあるこの熊野の地である。






