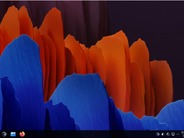IDEOのデザインプロセス
IDEOのKelleyは優れたプロダクトをデザインするための方法論をプロセス化しました。プロセスは、
1) Understand
市場やクライアントなど理解すべき現状について認識し理解する。
2) Observe
ターゲットの人達を観察し問題や課題を認識する。
3) Visualize
ターゲットに対する新しいコンセプトとアウトプットを目に見える状態にする
4) Evaluate & Refine
プロトタイプ作成し迅速に評価、対象のフィードバックをベースにブラッシュアップをし、再度評価というサイクルを迅速に繰り返す。
5) Implement
洗練されたコンセプトをいち早く市場に投入する。
と一連のプロセスを定義しています。
デザイン思考はアートか科学か
デザイン思考の元祖で書いた通り、デザイン思考はアート的な要素が強いように感じますが、実は適応範囲が広い。デザインはアートか、科学か、数学か?という問いに対し、デザイン科学のパイオニアであるジョン・ジョーンズは、こう答えたと言います。
数学者は時間からは独立した世界に存在するが、アーティストや科学者は時間の流れのなかでの現在という世界を意識して存在しているのであり、見たことのない未来を現実のものとして扱い、未来を現実化しなければならない。
未来とデザイン思考
ここで注目すべきキーワードは、未来。デザイン思考は未来を扱っています。デザイン思考では最初に1)Scan:発散によって可能な限り多くの解決を探します。ここでは、業界、業種や技術の思考的な制約を排除するための未来のインプットをしていきます。
既存の先入観を取り去る、2)Focus:その後収束によって最終案に絞り込んでいく。そして3)Act:最終的に最終案を実現するする為の実行計画に落とし込んで実現性を高めて行きます。ここでの発散とはあるテーマについて未来を現実に落とし込んだユニークなアイデアをもたらすプロセスであり、デザイン思考では未来思考が最も重要な要因となるのです。
未来をどのように制約なく創造できるか、それがデザイン思考で最も重要な要因となります。デザイン思考についての理解はデジタルの出発点になります。自分のデジタルの世界が未来を見据えているか、まずここから始めましょう。
Peace out,

- 松永 エリック・匡史
- 青山学院大学 地球社会共生学部 教授
アバナード株式会社 デジタル最高顧問
青山学院大学国際政治経済学研究科修士課程修了 - イノベーションをリードするデジタルコンサルティングの草分けであり、バークリー音楽大学出身のプロミュージシャンという異色の経歴を持つアーティストとしても活躍。コンサルタントとして、アクセンチュア、野村総合研究所、日本IBM、デロイト トーマツ コンサルティング メディアセクターアジア統括パートナー(執行役員)、PwCコンサルティング合同会社 デジタルサービス日本統括パートナーを経て現職。近書は「外資系トップコンサルタントが教える”英文履歴書完全マニュアル”」。