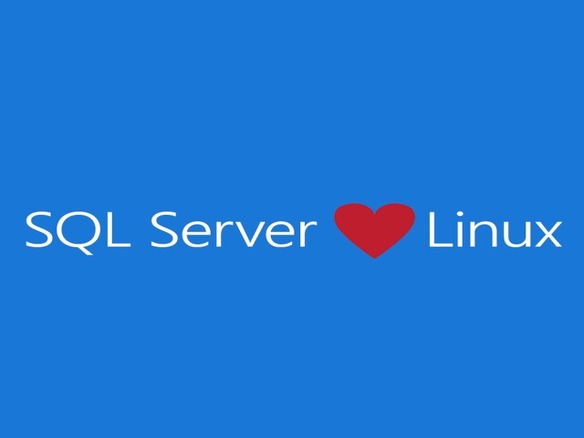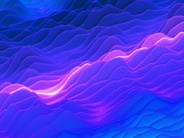日本マイクロソフトは10月26日、データプラットフォームに関するメディア向け勉強会を開催し、同月2日にリリースした「SQL Server 2017」の新機能を中心に解説した。

「Data Estateビジョン」について説明した日本マイクロソフト クラウド&エンタープライズ ビジネス本部 データ&AI プラットフォーム マーケティング部 エグゼクティブプロダクトマネージャーの岡本剛和氏
既報の通りSQL Server 2017では、従来の「Windows専用」という位置付けが大きく変更され、Linuxに対応した。さらに、昨今の機械学習/ディープラーニングの発展を踏まえて「Machine Learning Services」が提供され、GPUとPythonがサポートされる点も注目される。今回の説明会では人工知能(AI)への対応についてデモを交えた説明が行われたが、本稿ではその前提として語られたSQL Serverの内部構造の変化の過程について紹介する。
SQL Serverは、Microsoftが提供するWindows向けの各種サーバ・アプリケーションのための基幹コンポーネントだ。製品の性格から同社は当初からWindows以外のOSへの移植を想定した設計をしていたとは考えにくいものの、そうしたソフトウェアがなぜLinuxをサポートしたのか――。その理由は、そもそもSQL Server自体のパフォーマンスや安定性を向上させる工夫として実装している構造が功を奏した形だという。
というのも、SQL Server 6.5までの実装では、SQL Serverは内部で複数のスレッドを利用していたが、プロセス・スケジューリングはWindows任せだったため、SQL Server内部の動作状況を踏まえたスケジューリングはできず、パフォーマンス劣化の原因となっていたという。
そこでSQL Server 7.0には、SQL Server内に独自のスレッドスケジューラ(UMS:User Mode Scheduler)が実装され、自前でスケジューリングを行うようになった。これによって、ロック待ち中のスレッドにプロセッサの使用権を渡してしまうような無駄が無くなり、プロセッサの利用効率が大幅に向上した。この時期、SQL Serverが初期の不評を払しょくしてミションクリティカルなアプリケーションの基盤として採用される例が増えてきた背景には、こうしたアーキテクチャ変更があったわけだ。

SQL Serverの技術的変遷などを説明した日本マイクロソフト クラウド&エンタープライズ ビジネス本部 データ&AI プラットフォーム マーケティング部 シニアプロダクトマネージャーの横井羽衣子氏
次の大きな変化は、SQL Server 2005で実装された。大きな成果を挙げたUMSに代わり、新たに実装された「SQL OS」がUMSのスレッド・スケジューラ機能に加え、メモリなどのリソース管理の機能も入り、まさに「OS」としての機能を果たすようになった。
そしてSQL Server 2007 on Linuxでは、新たに「SQLPAL(SQL Platform Abstract Layer)」と呼ばれる抽象化レイヤが置かれ、SQL OSは下層のOSとの直接のやりとりをする層と、SQL ServerとOSをつなぐ役割を果たす層に分割された。その上でSQLPALの内部に含まれる形となった。
Windows NTで「HAL(Hardware Abstruction Layer)」が置かれて、OSとハードウェアの関係を抽象化することで移植性を高め、インテルアーキテクチャ(IA)以外のプロセッサをサポートしたのと同様のアプローチが、SQL Serverの内部でも行われていた。こうしたことが、SQL ServrにおけるLinux対応を実現できたポイントだったといえそうだ。
勉強会での主な説明資料は下記の通り。