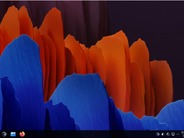「シェアリングエコノミーの衝撃」連載の第5回は、米Gartnerでデジタルビジネス全般のリサーチを担っているMark Raskino(マーク・ラスキーノ) リサーチバイスプレジデント&ガートナーフェローが来日したのを機に、シェアリングエコノミーについての見解を聞いた。
ビジネスとして成り立つシェアリングエコノミー
今回は、Raskino氏へのインタビュー形式でお届けする(敬称略)。
--まず、シェアリングエコノミーの捉え方をお聞かせいただきたい。

米Gartner リサーチバイスプレジデント&ガートナーフェローのMark Raskino氏
シェアリングエコノミーはさまざまな資産を有効に活用することを前提に、最新のITおよびデジタルによるテクノロジによって、これまで共有できなかったものが共有できるようになったことによって生み出されるエコノミーだと捉えている。
--ということは、取引形態としてCtoC(個人間)に限らず、BtoC(企業と個人)やBtoB(企業間)も対象になるということか。
シェアリングエコノミーが注目されるようになったライドシェア(車の相乗り)や民泊から見ると、CtoCが中心になるだろうが、私の捉え方としては限定していない。シェアリングエコノミーの定義はまだ定まっておらず、それぞれの立場で解釈が異なっているのが現状だ。捉え方によっては、例えば、銀行業も究極のシェアリングエコノミーといえる。従って、私は「テクノロジによってこれまで共有できなかったものが共有できるようになった」という比較論を捉え方の基本として考えている。
--そのシェアリングエコノミーの最近の動向については、どのように見ているか。
欧米に始まり、中国、そして最近では日本でもシェアリングエコノミーが広がってきているとの印象があるが、対象となる分野について存在感のある市場になってきているのは、車と自転車、民泊くらいだ。ただ、ここにきて共有可能で利用ニーズのある資産というのがさまざまな分野から出てきており、経済圏としてはこれからどんどん大きくなっていく可能性がある。
--そもそも、なぜシェアリングエコノミーが注目されるようになってきたとお考えか。
一言でいえば、稼げるからだ。ビジネスとして成り立つことが分かってきたから、活用できる資産を見つけてマッチングの仕組みを構築したシェアリングサービス会社が次々と登場している。ただ、シニカルな見方をすると、そうしたサービス会社に資金を提供しているベンチャーキャピタルの思惑も透けて見える。というのは、ライドシェアや民泊のように、潜在市場でうまくビジネスを進めることができれば、特定のサービス会社が成果を独占できる可能性があるからだ。
一方で、ビジネスだけでなく、環境対策としてシェアリングサービスに取り組んでいる会社も少なからず存在する。例えば、ライドシェアやカーシェアによって全体の車の数が減れば排気ガスが減り、環境改善につながるといった考え方だ。この環境対策としての可能性が、シェアリングエコノミーが注目されるようになってきた一面でもあるだろう。