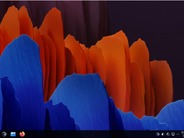セゾン情報システムズは、国内トップシェアのファイル連携ミドルウェア「HULFT」やデータ連携の「DataSpider」を中核とするデータ連携ソリューションを軸とした事業への構造改革を進める。流通・金融グループの情報子会社として50年の歴史を持つ同社だが、代表取締役社長の内田和弘氏は、経営を取り巻く環境の変化を踏まえて「“つなぎ”の強みを生かして特定、得意の分野でナンバーワンを目指す」と話す。同氏に改革の道のりと今後の戦略を聞いた。
--多くの日本企業が「デジタル変革」に乗り出そうとしています。セゾン情報にとっての変革とは、どのようなものでしょうか。
2020年に創業50周年を迎えます。流通の旧セゾングループの戦略情報子会社として設立され、1981年に信販業務システムを中心とする緑屋計算センターとの合併によって流通と金融のIT企業になりました。現在もクレディセゾンが大株主の1社であり、情報子会社として受託開発などの役割も担っていますが、2018年にクレディセゾンでの共同基幹システムのプロジェクトが完了したことで、今後は新たなビジネスを広げていく段階に入りました。

セゾン情報システムズ 代表取締役社長の内田和弘氏
共同基幹システムの構築では、延伸問題を引き起こしたことによって大きな損害を伴うことになりました。2015年には赤字にもなり、私が就任した2016年は経営基盤を立て直さなければならない状況でした。当時は何千人、何万人といる大手のシステム企業のようなリソースはありませんでしたし、頼みの流通や金融に特化したとしても対応可能な案件には限界がありますから、受託開発の体力勝負では勝てません。社内で厳しい賛否の声がありましたが、数百人規模でも生き残れる会社にならないといけないと考え、黒字でも将来の採算性が厳しい事業を売却し、赤字の事業から撤退して、実質的に単独のプロダクト事業だったHULFTを中心とするデータ連携基盤のビジネスに特化することにしました。
既に当時は、企業がクラウドにシフトすることが明確でした。それに、サプライチェーンが国や地域を跨がるようになり、システムも人やモノもグローバルに接続されたつながる時代が到来して、データやファイルの連携がビジネスになると予見していました。実際に現在の市場は、クラウドとオンプレミスとの間でデータ連携基盤を再構築するニーズが高まっています。
事業の再構築では、事業ごとにP/L(損益計算書)とB/S(貸借対照表)での評価を徹底するようにしました。以前はP/Lを重視していて、収益に対する視点を変える必要があったのです。また多数のサブシステムを運用しており、経営会議では各事業部が毎週40時間を費やしてシステムごとに形式が異なるデータをExcelに集計し、報告書や資料を作成する状況でした。
共同基幹システムでの問題から、プロジェクトごと、顧客ごとに詳しい状況を全社規模で把握、管理するように改める必要があり、自社にファイルやデータを連携するプロダクトもあるわけですから、まずはこれらを使って異機種のシステム間で異なるデータをリアルタイムに取り込み、可視化する基盤を整備しました。大きなトラブルを起こしたこともあり、二度とトラブルを起こさないためにも、あらゆる面で品質を把握し、可視化しなければなりませんでした。
よくビッグデータの中で実際に使えるデータはわずかしかないと言われますし、データサイエンティストもデータの収集と加工に多くのリソースを取られ、分析から知見を見いだす本来の作業には十数%しか割くことができないとも言われます。私たち社内での基盤整備は、それらを含めて自分たちで実験し、データの利用価値とデータの集め方や連携、加工のやり方などを実感する目的もあります。まずはどこに、どのようなデータがあるのか、集めたデータを全員が読め、加工できるのか、そうしたことを顧客に理解してもらう上でも、自ら仮説を立てて検証していく作業が欠かせなかったのです。