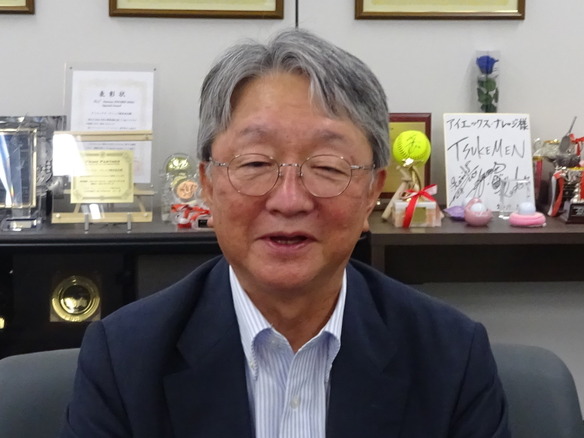中堅システムインテグレーター(SIer)のアイエックス・ナレッジ(IKI)がこのほど、2024年度(2025年3月期)に売上高230億円、営業利益14億5000万円などとする中期業績目標を公表した。2021年度の業績(売上高185億4100万円、営業利益11億4900万円)から推測すると、年平均7%の成長を遂げる必要がある。営業利益率は6.3%とほぼ同水準の計画になる。
代表取締役社長の安藤文男氏によると、目標達成のカギはクラウドとアジャイル開発にある。背景には、デジタル変革(DX)という大きな波がある。問題は、多くの企業がDX推進を叫ぶものの、実現したい内容や目的が異なっていること。そこで、約2年前の経営会議で議論した結果、「DXはクラウドベースで展開するケースが多くなる」と判断し、クラウドを「一丁目一番地」とする経営戦略を作成した。
加えて、一括請負から常駐型へとビジネスモデルが変わると予測し、アジャイル開発への対応を推し進める。DXを事業に役立つものにする上で、ユーザーとトライ&エラーを繰り返しながら進めていく常駐先でのアジャル開発が適するからだという。
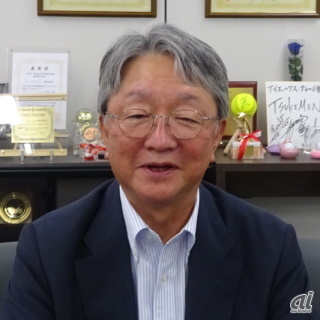
アイエックス・ナレッジ 代表取締役社長 安藤文男氏
同社の売り上げに占める請負契約の比率は、最盛期の4割程度から現在は2割を切っている。安藤氏は「システムインテグレーション(SI)ビジネスにとってありがたいこと」と、請負比率の減少を納得する。請負については「業務量は安定するものの、その中に火を噴くものがある」とし、プロジェクト管理を徹底し、不採算プロジェクトの撲滅に取り組んできた。
そこに四半期決算というSIビジネスにとっての追い風が吹き始める。例えば、2年間で5億円という発注や仕掛りの考え方がなくなる。分かりやすく言えば、SIerが1年間、一生懸命に作業しても、「まだ完成品ではないので、全額を支払えない」「予算オーバー分を負担してほしい」などと、ユーザー企業ともめなくなるということだ。
追い風がもう1つ。新型コロナウイルス感染症の流行がリモートワークを普及させたことで、クラウドを利用した働き方改革やDXの引き合いが増えた。しかも、単なる請負ではなく、常駐先のユーザーとDXを盛んに議論していく形だ。
こうしたクラウド案件の獲得が成長につながると確信したIKIは、「Amazon Web Services」(AWS)と「Microsoft Azure」の資格認定技術者の育成、獲得に力を入れる。クラウドを含めた教育費として年間1億円程度を用意し、2021年度に約100人がAWSの資格認定を取得した。2022年度も約100人の認定取得を見込んでいる。一方、Azureは対応を始めたばかりなので、資格認定者は少ないものの、2022年度中に50人を計画する。
しかし、これだけではクラウド案件の需要増に十分に応えられないので、クラウドに強いパートナー企業との協業を推進する。人手不足の解消に、M&A(企業の買収合併)も視野に入れる。これまでM&Aに力に入れてこなかったことで、IKIの協力会社が他社に買収されたこともあった。「私が知っている限りでも2社あった」と安藤氏は振り返る。M&Aの対象は、IKIと同じビジネスモデルを展開する企業や技術的な補完関係のある企業になる。地方のSIerについては時間をかけてじっくりと考えている。リモートワークの環境が整備されたことで、地方の技術者も活躍できるからだ。
IKIの顧客先から読み取れることもある。NTTデータとKDDI、日立製作所、NEC、日本IBM、東芝など取引先上位10社の合計売り上げが、2021年度に全体の71.2%と前期から4.4ポイントも増えている。この10社の中には、三菱UFJフィナンシャル・グループとみずほフィナンシャルグループ、東京きらぼしフィナンシャルグループ、富国生命保険なども入っており、主力事業のシステム開発、保守、運用に加えて、コンサルティング事業の拡大などによって、2021年度は前年度比で7%超の増収となる。営業利益は技術者育成などによる単価向上などで、同32%と大きく伸ばす。
安藤氏は、2024年度にクラウド関連売り上げを半分以上にすると期待する。現在、正確な売り上げをつかんでいないものの、大阪でのクラウド関連の売り上げは半分を占めるという。「モノ作りとグローバル展開する企業が多いからだろう」と同氏は推測する。一方、東京はオンプレミスへの需要がかなりあるものの、ユーザーは経済性を考慮しながらクラウド化を進めていくと読む。
だからこそ、DXの波に乗るためにはこれまで以上に信頼関係を重要視して、ユーザーとともに学んでいく姿勢が必要になる。そして、クラウドやアジャイル開発の技術・知識を蓄積し、活用を推進していく。提案型営業などの体制強化も進める一方で、問題は次の策になる。例えば、アジャイルで開発したソリューションを、どのように横展開していくかだ。67歳の安藤氏は、どんな手を打つのだろうか。

- 田中 克己
- IT産業ジャーナリスト
- 日経BP社で日経コンピュータ副編集長、日経ウォッチャーIBM版編集長、日経システムプロバイダ編集長などを歴任、2010年1月からフリーのITジャーナリスト。2004年度から2009年度まで専修大学兼任講師(情報産業)。12年10月からITビジネス研究会代表幹事も務める。35年にわたりIT産業の動向をウォッチし、主な著書は「IT産業崩壊の危機」「IT産業再生の針路」(日経BP社)、「ニッポンのIT企業」(ITmedia、電子書籍)、「2020年 ITがひろげる未来の可能性」(日経BPコンサルティング、監修)。