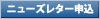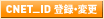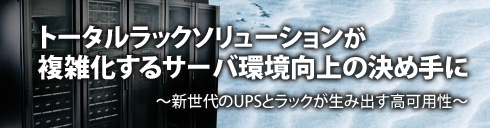
情報システム/基幹システムを問わず、分散化が進んだシステムの再編成が盛んに行われている。だが、低廉なサーバを用いたシステムの再編成は、メリットも数多くあるが、システム管理の煩雑化や専有面積の増大などのデメリットを伴っていることを忘れてはならない。それらのデメリットを打ち消してシステムを最適化するにはサーバ本体の管理だけでなく、それらを設置するためのラックも含めたサーバルームの環境を再考する必要があるのだ。
加速するシステム統合における
問題点とは?
サーバルームの問題(1)−増え続けるサーバ
ハードウェアやソフトウェアの技術進歩に伴い、企業システム全体の投資コストは年々低下し、以前より容易に導入できるようになった。中でも大きいのは、サーバの低価格化だ。かつては信頼性の高いメインフレームで構成されていたシステムが、情報系から基幹系に至るまでWindowsやLinux、Unixといった汎用OSと複数のPCサーバで代替えできるまでになったのだ。
これは、一見便利な環境に見えるが、システム部門からすると思わぬ弊害を呼んでいることがある。例えば、オープン化とサーバの低価格化に乗って分散管理が進んだ結果、セキュリティレベルの非均一化に加えて、全体の管理コストの増加や人員増加が生じ、効率が低下するというケースも考えられる。また、サーバの台数が増えたことで、サーバによって占有されるスペースが増えてくる。
サーバルームの問題(2)−機器の排熱
現在、設置コストの削減や、管理の効率化を実現するための手段として、1〜5U程度の筐体に、6枚〜10枚程度のサーバを実装できるブレードサーバが注目を集めている。だが、ブレードサーバのような薄型サーバは、高密度化による消費電力の増加だけでなく、排熱量の増加を引き起こす。このため、熱に対する対応も、従来とは違うレベルで意識する必要になってくる。
マシンの排熱に対しては、データセンターであれば空調設備が整っているから大丈夫と思われているケースは少なくない。しかし、ラック内部のエアフローを考慮した環境を構築しないと、ラックは冷やしたものの、ラック内の機器の温度は下がらずに、サーバがダメージを受けてしまうというような事態にもなりかねない。
システム統合というと、ソフトウェアやハードウェアの統合に目が行きがちであるが、ITの信頼性を上げるという意味では、ラックなどのファシリティを含めてトータルな観点で考える必要があるのだ。
サーバルームの問題(3)― 変化に対応できない電源環境
一方、システムの信頼性という意味では根本を支える電源環境、つまりUPSはどうか。一般的なサーバルームや電算室では、1ラックあたり3kw程度の消費電力を想定してデザインされている。だが、米国の調査会社が調べたところによると、2002年の時点で平均1.5kW程度だったラックあたりの電力消費量は、消費電力量の大きいブレードサーバや高密度化したサーバ、ストレージ機器の台頭により、9.5kW程度まで増加するという見通しが出されている。
このような環境では、UPSも従来のように大型なものに戻るのかというとそうでもない。やはりUPSもIT機器の省スペース化というトレンドに適応しなければならない。つまり、ラック全体をサポートできる容量を維持しながら、ラックにマウントできるサイズで、他のIT機器の為のスペースを最大に確保できる出力密度の高いUPSが必要となってくるのである。 従来のような1サーバに対し1UPSという電源保護環境では、管理が煩雑になり、省スペース化の流れにも逆らうことになる。
また、重要なアプリケーションやデータの保護という点では、内部冗長構成が可能である事も重要な選択のポイントとなる。ブレードサーバのように拡張性に優れた機器には 、やはり同じようなコンセプトで段階的に増設や冗長化が設定できるUPSも有効な選択肢になり得る、という訳だ。さらにいえば、ラックあたりの実装密度が高くなる事を考えると、ラック内の電力使用量をリアルタイムで監視するPDU(Power Distribution Unit)を組み合わせ、電源とマシン環境そのものをトータルに管理できることが望ましい。