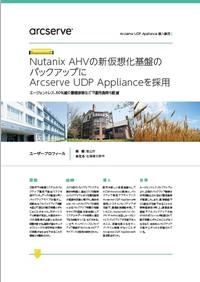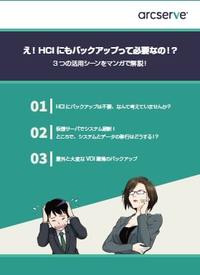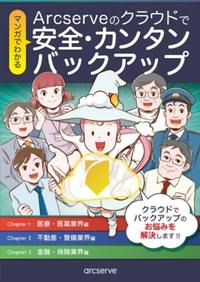中堅中小企業にも注目されるNutanix
大手ディストリビューターも手応えを実感
日本最大級のITディストリビューターであるダイワボウ情報システム(以下、DIS)は2019年4月、ハイパーコンバージド・インフラ(HCI)市場をリードするNutanixとディストリビューター契約を締結した。

ダイワボウ情報システム
経営戦略本部
情報戦略部
部長
谷水茂樹氏
「通常、新たな商材の取り扱いを開始した直後は、販売が立ち上がるまでにある程度の期間が必要です。ところが、HCIの代名詞ともいえるNutanix製品は違いました。契約をして間もない段階から問い合わせが入るようになり、早い段階から手応えを感じられました。HCIの採用があまり進んでいなかった中小規模のユーザーでも、構築期間の短縮や運用の効率化なども含めたトータルでのコスト削減を意識して、複数サーバをNutanixに統合することを検討するケースが出てきました」と、DIS 経営戦略本部 情報戦略部 部長の谷水茂樹氏は説明する。
DISは全国に約90カ所の営業拠点を展開し、販売パートナー約19,000社という地域に密着した営業体制を強みとしており、同社は全国各地のパートナーを経由して、エンドユーザーに製品やソリューションの販売を行っている。最近では中小規模のユーザー企業でもHCIを検討する例が増えてきているというわけだ。

ニュータニックス・ジャパン
プロダクト・マーケティング・マネージャー
マーケティング統括本部
三好哲生氏
そしてNutanixは、HCI市場の中でも中小規模ユーザーに選ばれやすいという。ニュータニックス・ジャパン マーケティング統括本部 プロダクト・マーケティング・マネージャーの三好哲生氏は、以下のように語る。
「現在のNutanixのユーザー規模は両極端といったところで、大規模なユーザーにも中小規模のユーザーにも使っていただいています。当初は主にVDI用の基盤として採用するケースが多かったのですが、最近ではサーバを稼働させる基盤、プライベートクラウドとしての導入が増えてきました。我々のソリューションは、ユーザーの選択肢を狭めることがないように、という方針で設計しています。例えば、ハードウェアのベンダーをロックインしませんし、ハイパーバイザについてもNutanix AHVを用意しつつもマルチハイパーバイザ対応です。また最近では、データセンター内だけでなくパブリッククラウドも含め、マルチクラウド環境をシンプルに運用できるよう様々な機能を取り入れてきました。そういった、柔軟に選択できるという点も評価されているのだと思います」
少なくとも当面はHCIと既存インフラが混在
バックアップ統合も含めた検討が重要に
NutanixをはじめとするHCIは、そのシステム基盤を容易に拡張していくことが可能だ。HCIを導入したユーザーの多くは、その規模を必要に応じて拡張しながら、物理サーバや3Tierの仮想化基盤などの既存環境徐々にHCI上へ移行していくシナリオを描く。つまり、将来的には完全にHCIへ集約する計画だとしても、導入当初はHCIと既存環境混在で運用することになるのだが、それによってむしろ運用が煩雑になる部分もある。その一つがバックアップの運用だ。バックアップ方法が環境ごとに異なっていると、その分だけ手間が増え、バックアップ先も分かれてしまうなどコストの最適化が難しい。
この問題に対し、長年に渡ってバックアップソリューションを手掛けるArcserve Japanは、混在環境に強いデータ保護対策を提案している。

Arcserve Japan営業統括部
ディレクター
小久保洋平氏
「当社のArcserve Unified Data Protection(UDP)は、バックアップ元が物理環境でも仮想環境でも、混在していても対応できる統合バックアップ/リカバリソリューションです。主要なハイパーバイザにはネイティブ対応しており、仮想マシンをエージェントレスでバックアップすることができます。Nutanix AHVにも、2019年にリリースしたバージョン7でネイティブ対応となりました。もちろんNutanixのファイルストレージ機能『Nutanix Files』上のデータも、CIFS/NFS経由でバックアップが可能です。Arcserve JapanとNutanixは、グローバルでも日本でもアライアンス関係にあり、安心してお使い頂けます」と、Arcserve Japan営業統括部 ディレクターの小久保洋平氏は説明する。
Arcserve Japanのバックアップソリューションは、日本市場で広く使われており、新たにNutanix製品を導入したユーザーにも、使い慣れたコンソールであることが多い。HCI導入時に、既存環境も含めたバックアップ統合・効率化計画を立案するのであれば、このように今まで通りの操作感ですぐに使えるツールが好ましいといえるだろう。
「しかも、コスト面でも有利です。Arcserve UDPはバックアップの際、永久増分バックアップ機能によってストレージ容量を大幅に節約でき、さらに重複排除で数分の1ほどにバックアップデータを縮小します。災害対策においても、『仮想スタンバイ』『インスタントVM』により、DRサイト側のArcserve UDP上で仮想マシンを稼働させることができ、コスト抑制が可能です。遠隔バックアップ先やDRサイトとしては、当社のクラウドサービス『Arcserve UDP Cloud Hybrid』も効果的と言えるでしょう。ちなみに、Arcserve UDPのNutanix AHV対応版は専用のエディションが用意されていますが、日本ではNutanixを選定するコスト意識の高いお客様に合わせ、標準エディションと同じ価格設定で安価に提供しています」(小久保氏)
HCIと組合せてシンプルに運用
アプライアンス版がより効果的
Arcserve UDPは、ソフトウェアとして販売されているだけでなく、アプライアンス製品も用意されている。こちらはWindowsをバックアップサーバ専用に最適化したモデルで、ストレージ容量4TBから80TBまでのモデルまで用意されているので、ユーザーは必要な容量のモデルを選ぶだけだ。その容量に格納できる範囲であれば、バックアップ対象の台数などは問わないライセンス体系となっている。データ肥大化などの理由で2台目のアプライアンスを導入した場合でも、1つのコンソール画面で統合管理が可能だ。こういった特徴から、HCIとの親和性でいうとArcserve UDPアプライアンスの方が効果的といえるだろう。
DISの谷水氏も、HCI環境でも外部へのバックアップを合わせて提案することで、ユーザー様にわかりやすいストーリーとして提案できるという。
「これまでも、物理サーバを販売するときに、バックアップやUPSなどの周辺環境まで合わせて提案してきました。その点はHCIのようなモダンなインフラでも同様で、一貫性のあるストーリーとして提案する方がユーザーにもわかりやすく親切です。バックアップに関して言えば、かつての物理サーバではテープバックアップが主流でしたが、今であればArcserve UDPアプライアンスによるバックアップやDRが有効な選択肢となるでしょう。HCI導入と合わせて、バックアップ環境を刷新しDRサイト構築も検討しませんか、といった提案になるわけです。このようなNutanixとArcserve UDPの組み合わせの有効性は、パートナー様を通してユーザー様にきちんと情報を伝えたいと考えています」
今後は、Arcserve Japanとニュータニックス・ジャパン、DISの3社がコラボレーションしたプロモーションなども計画中ということだ。