デジタル変革のために成すべき
経営者のマインド変革
―― 日本企業はこの厳しい時代において、デジタル技術を活用した変革を求められています。いわゆるDXを推進するにあたって、企業にはどのような課題があると考えていますか
エリック氏私は外資系コンサルティング会社でDXの立ち上げ及びリーダーとしてDXコンサルティング事業に従事したのち現在は主に大学の教員として活動していますが、並行してコンサルタントとして企業の経営者向けにDX推進を支援しています。
正直、数多くの企業の状況を拝見してきた経験から、日本企業は“崖っぷち”にあると考えています。日本のDXは、いまだに効率化やコスト削減といった「IT活用」にとどまっており、ビジネス変革には至っていません。海外企業の経営者は「デジタルは変革のチャンス」と考えています。彼らは、変革のビジョンがなければ変化の激しい市場で生き残ることができないと理解しているのです。
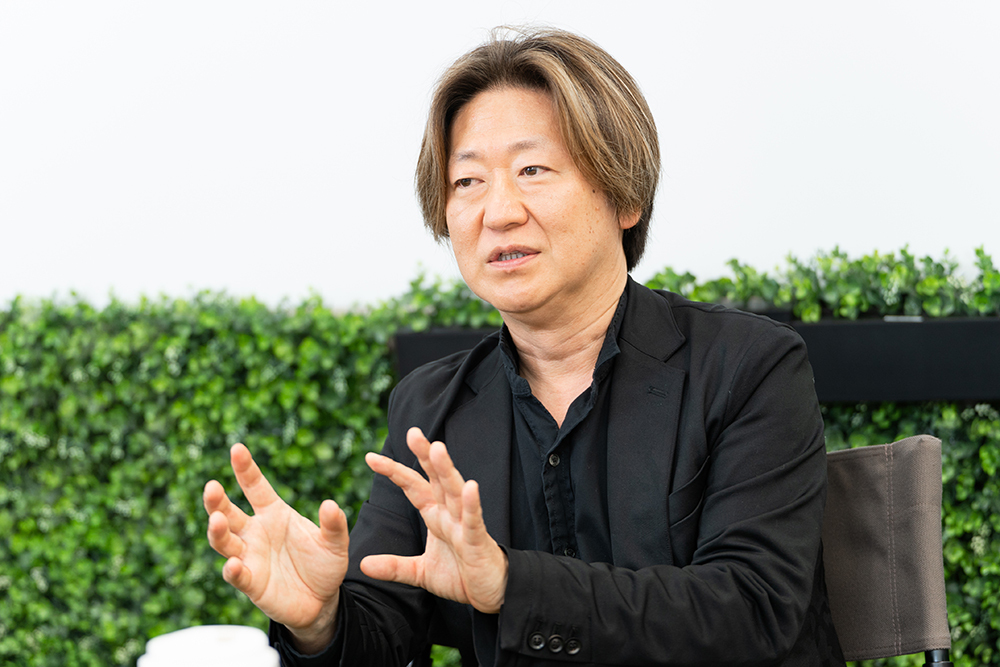
青山学院大学 地球社会共生学部 学部長 教授
松永エリック・匡史氏
田口氏私は製造業のDXを推進するコアコンセプト・テクノロジーでCTOを務め、現在は製造業向けDX支援メディア「 Koto Online」の編集長を務めています。Koto Onlineの企画で様々な企業を取材したり、経営者の方々と対談したりしています。
エリックさんのおっしゃるとおり、DXに成功している日本企業は多くありません。その中でも成功している方に話を聞いてみると、デジタルやITを論ずる前にマインドを変えている、ビジネスを変えようというマインドで先へ進んでいるという印象です。
すでに多くの日本企業は、デジタルを活用した生産性向上・効率化に努めています。成功者が取り組んでいるのはその先、どうやって売上を伸ばすべきかという点でデジタルを積極的に活用しています。

Koto Online編集長
田口紀成氏
山賀氏私はIBMやマイクロソフトなどのIT企業を経て、現在はElasticの日本法人代表を務めています。仕事柄、さまざまな企業の経営層と話す機会が多く、マインドの変革が重要だと感じるシーンもよくあります。
例えば、このコロナ禍では多くの企業がリモートワークを推進しました。しかしパンデミックが落ち着いた今、元の働き方に戻っている企業も多いようです。日本企業にとってのリモートワークは、出社できないから広がった代替手段に過ぎないというわけです。一方で欧米企業のリモートワークは、業務環境を整えて優秀な人材を確保するための経営戦略なのです。
もともと多様化を推し進め、経営資源を確保する働き方改革の一環としてはじまったはずなのに、コロナ禍を経て戻っているというのは非常にもったいないことだと思います。今を乗り切れば良いと考えるか、チャンスを生かそうと考えるか、その発想の違いがDXの成否の根底にあるのではないかと感じています。

Elasticsearch株式会社 日本法人代表
山賀裕二氏
田口氏自分の会社を大切にしている創業者・経営者は、自分が何とかしないと生き残れないと考えて、変わっていくことを選択していますね。
山賀氏経営者に必要なスキルやマインドについて、とある調査では米国の経営者が顧客志向・業績志向・変化志向・テクノロジーリテラシーと答える一方で、日本の経営者はリーダーシップ・コミュニケーション・チームマネジメントと、組織の推進力にポイントを置いた返答が並びました。
どちらがよい・悪いという話ではないのですが、この違いは鮮烈な印象でした。現代ビジネスに求められるアジャイルな対応や新しい価値の創出という点では、米国経営者の考え方のほうがフィットしているように思います。
感覚でDXに取り組む日本企業
データ活用が変革のカギ
―― 日本企業は、ポジティブなマインドでDXを推進すべきところを、ネガティブな方向に動き出しているように見えますね
エリック氏そもそもデータを活用し数字で判断する事が苦手な日本企業は、ポジティブな判断の基準がないんですね。過去の経験や感覚で経営していて、データを元に判断していない点が大きな問題だと思います。例えば米国の場合、考え方の違う多種多様な国籍のプレイヤーが集まっているので、共通のデータを元に判断や行動する習慣がついているんです。感覚だけでは世界では戦えません。
田口氏「適切なリスク」などという言い方がありますが、数字が見えなければ「適切」の意味がつかめません。そして「こんな感じのリスクなので負うことはできないね」と、感覚で判断してしまいがちです。
ちゃんと数値として可視化できれば、「この量のリターンがあるなら、この量のリスクを負ってもよい」と明確に判断できます。本来はそうした会話や検討が成り立たなければならないのですが、それを実現するプラットフォームを持っていないのです。そもそも正しく検討する必要があることにすら気づけていません。
エリック氏日本企業のCIOの位置づけが危ういと感じています。CxOはあくまで経営層なのですから、CIOはITを戦略的に経営視点で見なければなりません。リスクやコスト面だけではなく、中長期的に売上が上がることも考えなければならないのです。リスクにばかり重点を置き、中長期の成長に向かう新しい挑戦に対して消極的なCIOが多いように見受けられます。
山賀氏大きな失敗をしない、会社に損害を与えないというところから出発してしまって、変化をチャンスとして捉えず、ビジネスの変革に結びつかないケースもあるのではないでしょうか。しっかり基盤を固めるということばの耳障りはよいのですが、何のための基盤かという視点が必要です。
まず経営者がマインドを変えなければならない。そしてマインドを変えるにはデータが欠かせないのです。
創業者・経営者の志と文化が
DXを推進する
―― ITやデータの活用を推進するにあたっての課題にはどのようなものがありますか
エリック氏 ITの位置づけは大きく変わりましたね。旧来のホストコンピュータから始まったITは、人間の作業を効率化するビジネスのバックエンドの仕組みが中心でした。しかしクライアントサーバーやインターネットが登場し、ITは急速に発展しました。ネットを使った販売や、サービスそのもののIT活用がビジネスの本流となっています。経営者がデータを活用し意志決定をするようになり、経営にもデータが命綱となってきている。
そこに気づいていない経営者がまだまだ多い。ITは所詮ツールであり、経営には直結せず、裏で動いているものという意識がある。そうなると、データの重要性に気づかず、そのデータを守るセキュリティをコストと捉え、最もお金をかけなければならないところ、いちばん優秀な人材を置かなければならないところなのに、投資を積極的にしません。また、ある意味、経営を支えるIT人材は、縁の下の力持ちではなく、経営に重要な存在なのです。セキュリティに関してIT人材に投資をしないことの危険性はお分かりかと思います。
ITの柔軟性は経営の柔軟性と同意義になります。つまりIT企業は一ベンダーではなく経営パートナーとして捉えなければならないのです。経営改革を果たしたいのであれば、IT企業をパートナーにしなければダメなのです。
―― 経営層・中間管理層・現場と、データ活用やDXが自分の役割の範疇にとどまってしまっているように見えます
田口氏今や、人と人とがビジネスを引き継いでいくという時代ではありません。データをもって過去がどうだったかを示して、将来をどうしていこうかと話し合う社会になってきています。
このとき、その重要なデータをどこに預ければよいかという点が重要です。どこに置くべきか、どこが安全か、経営者は決めなければならないのです。
お金を銀行に預けるように、データも経営資産として同じように考えてほしいのです。Elasticの検索エンジンは非常に強力で、1ユーザーとしてお勧めしたい選択肢の1つです。
大量に貯められたデータ
価値ある“宝”へ昇華するには
―― システムログやセキュリティログも重要なデータ資産の1つです。ログデータを活用するにあたって、どのような課題が考えられますか。どのようなデータ管理が必要でしょうか
山賀氏急速にデジタル化が進み、ログなどのデータが急激に増大してインターネット上を飛び交っています。ほとんどの会社では、こうしたログを貯め込んでいるはずですが、何も活用していないのが現状です。なにかインシデントが発生して初めて、貯めたログから情報を引き出そうとするわけです。もはやどこに何が保管されているのかもわからない状態です。
サイバー攻撃の手口が高度化されている現在、最新のセキュリティ対策は、脅威がある程度入ってくることを前提として、攻撃活動にすばやく気づくこと、すばやく対処することを目標としています。そのため、ログをリアルタイムに監視してアラートを上げる仕組みを構築し運用するのがこの数年のトレンドとなっています。
一方で、それを難しくしているのが、IT環境の複雑化ですね。複雑のクラウドやオンプレミスが混在する環境は当たり前となり柔軟なシステム構築、運用がますます可能となる中で、ログやメトリクスの監視や分析は個別の環境ごとにやり方が違うケースがほとんどです。
Elasticが強みとしているのは、システムから独立し環境に依存せずに横串でリアルタイムに監視できるという点です。
エリック氏現代の企業システムは、ものすごくカオスになっていますよね。自分たちのIT環境がどのようになっているのかをきちんと可視化するということが、今やるべきことです。ちゃんと見えなければ、どこから侵入されているかわからない。危険極まりない状態です。

田口氏私たちは、体温を測って何度だったら薬を飲むとか、病院に行くとか、アクションを決めていますよね。それと同じように、アクションが決まっているものだけデータを見えるようにすればよいのです。すべてをきれいに見ようとすると、とたんに実現できなくなってしまいます。すべてのデータを貯めておいて、自分がアクションを決められるものだけを目にする仕組みにすればよいのです。
エリック氏データはもちろん宝なのですが、使い方を間違えるとゴミにもなりえます。データの活用は、判断とアクションにつながらなければ意味がありません。対象のデータが例えば100個あったら、それを即時に判断しアクションに移すことは不可能です。対象のデータを絞り込み、判断基準となるKPIとそれに対応するアクションを決めることで、データ活用をしたと言えます。ある企業の取り組みで、KPIを6つに絞りアクションを明確にしました。そうしたら経営層の判断とアクションが飛躍的に機能したのです。
山賀氏生成AIの発展によって、そうした大量のデータをビジネスに生かせる時代がやってきました。
生成AIをビジネスに活用しようとする企業は、今後ますます登場する複数の大規模言語モデル(LLM)を使い分けていくことになります。それには大量の社内・社外のビジネスデータを各LLMに学習させる必要がありますが、時間もコストも増大するため現実的ではありません。そこで、データを統合的に管理する環境を整えて、各LLMと連携して関連する情報を引き出す仕組みが主流になっています。そのソリューションとして、Elastic を活用するケースが非常に増えています。
エリック氏今やさまざまなシステムがAIの機能を取り込んでいます。例えば生成系AIによって作られたデータをどのシステムが管理するのか、どのデータが適切なデータなのかを判断することも必要です。複数のシステムにまたがる場合、システム全体としてのデータ管理が複雑化していきます。これを企業のIT部門だけが管理するのは不可能ですよね。この場合、システムと業務を包括的に管理するためには、IT部門、業務部門、さらには経営層の範囲にまたがるベンダーフリーな仕組みは欠かせません。データの分散は、情報漏洩だけではなく、参照すべき適切なデータの所在を企業が把握することが重要であり、これまでのITにはない違った視点でのシステム再構築がキーになるのではないでしょうか。
DXの力となるデータ活用
Elasticの真の価値とは
―― 日本企業にElasticをオススメするポイントを教えてください
山賀氏Elasticは、OSSから歴史がスタートし、エンジニアの方々には非常になじみのある検索エンジンです。企業のお客さまへの永続的な製品・サービスの提供を目的に、2012年のオランダで会社が設立されました。
その後、大量のデータから高速に必要なデータを抽出するという検索の力が認められ、国内外のさまざまな先進的サービスで活用されています。
昨今、生成AIでビジネスデータを活用するという流れが来ています。ビジネスデータを利用するには、AIへ必要なデータを渡す機能とデータセキュリティが不可欠です。生成AIに投げる質問に関連するデータを以下に抽出し質問とともに渡せるかが生成AIのアウトプット品質を決定すると認識され、Elasticが脚光を浴びるようになりました。
もう1つ注目されているのが、高速な検索エンジンの特徴を生かした、システムログやセキュリティログの可視化です。Elasticの最大の特長は、適応領域の広さにあります。セキュリティに特化した競合製品はたくさんありますし、システム運用管理にしても同様です。しかしElasticは、1つのデータ検索というコア技術で複数の領域に適用することが可能です。総合的にはスキルの集約化やコストの低減といったメリットを得られます。
エリック氏Elasticの戦略で面白いのは、劇的な変化をしているIT業界の中で、競合分析から入らず、あるべき企業ITの姿からサービスを設計している点だと思います。変革を核とするDXでは必須な視点です。将来ITがどんな姿に変化しようとも、Elasticは企業ニーズを長期的に見据え、企業が必要なサービスを提供し続けてくれると期待しています。

田口氏Elasticは、完全・完璧な製品として固まっているものではなく、それが利点だと思っています。非常に柔軟なので、Elasticの上に作るものは完全にユーザーにフィットできるというわけです。エンジニアとしては、お客さまが新しいことをやりたいというときに無理なく応えられるソリューションだと感じています。
山賀氏Elasticは、検索テクノロジーをビジネスのコアとして位置付けているお客さまが多いですね。彼らは、検索エンジニアをしっかり内部に確保しています。一般の企業には、検索テクノロジーに詳しいエンジニアはあまりいません。
ビジネスにおける検索テクノロジーの活用は地道な作業です。チューニングをしながら精度を高め、ユーザーエクスペリエンスを向上させていく、継続的な業務です。この専門性の高い仕事・スキルについて、Elasticが多くの企業をご支援できると思っています。
―― Elasticはコミュニティにも注力していますね

山賀氏Elasticのコミュニティは非常に活発です。世界中のエンジニアが積極的に情報交換しており、Elasticの製品開発メンバーも参加しています。コミュニティでの議論が製品開発につながり、市場・コミュニティを尊重したアップデートが施されています。 コミュニティの存在は、新たにElasticを利用するユーザーにとっても大きなメリットです。
エリック氏Elasticには強力なコミュニティがあり、常に上を目指す優秀なエンジニアの知へのニーズを満たしているわけですね。今後、Elasticが強力なコミュニティを通じて、企業や技術の壁を超えた変革をリードするような存在になる可能性を秘めている。これは非常に大きな価値だと思います。
―― 今後のElasticについて教えてください
山賀氏何かまったく新しいものを作るというのは、Elasticらしくないですね。私たちは、コアコンピタンスである検索テクノロジーをいかに強力なものとしていくかというところに投資を継続しています。
直近では、生成AIとのデータ連携の強化、システムやネットワークのロゴをはじめとした大量のデータの更なる可視化と対象領域の拡大、環境に依存しない導入のしやすさや使いやすさの追求といった機能強化を通じて、お客様綺語の高いROIの実現に貢献し続けていくことが私たちの使命だと考えています。
―― ありがとうございました



