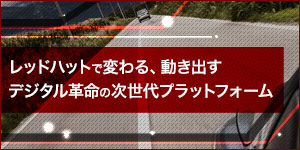仕掛けの工夫が革新をもたらす
一方、ホワイトハースト氏に続き演壇に立った大和総研 副社長の鈴木孝一は、「OSSのようなオープン・テクノロジー/プラットフォームを使うのは、もはや当然の選択」としたうえで、「重要なのは、(オープンなプラットフォーム上で)どんな"仕掛け"を作るか」だと説く。
そうした仕掛け作りの好例として、鈴木氏は今回、欧州における事例をいくつか披露した。一つは、AI(人工知能)を利用したドイツの貨物コンテナの例だ。このコンテナが優れているのは、広範な用途への適応が可能な点にあるという。「ITの仕掛けには、このコンテナのように、他への転用が効く汎用性・モジュール設計が大切です。その意味でも、仕掛けのプラットフォームには高いオープン性が当然求められるのです」と、鈴木は付け加える。
また、オランダのある農企業では、従業員10数名程度の小規模事業者でありながら、センサー付きのAIコンテナによって、ハウス栽培における収穫・出荷作業の効率化を図ると同時に、データ分析によって、いつ、どの時点で、何の野菜をいくつ生産・出荷するのが最も効率的かの判断を下しているという。さらに欧州では、CO2排出量の削減目標を達成すべく、自家発電で生まれた熱とCO2をハウス栽培に循環させる試みや、スマートシティ構想が各所(今回披露されたスマートシティはフランス リオン市の例)が進められているもようだ。
このように、ITで優れた"仕掛け"を作り、適切に制御することで、ビジネスや社会に変革・革新のうねりが巻き起こせる。だからこそ、新たな着想や工夫、視点が大切であり、変わるべきは、ITではなく、「ITを使う皆さん自身です」と鈴木氏は語り、講演を締めくくった。
この鈴木氏の後を受けて登壇したパナソニック インフォメーションシステムズの前川一博社長は、オープンイノベーションの重要性について次のように唱える。
「日本の製造大手の中には、いまだに自前主義にとらわれている向きもあります。ですが、それでは今日の変化に追随していくのは不可能です。やはり、オープンイノベーションの発想で、社外の優れた知と技術を積極的に取り入れてくことが不可欠です」
前川氏によれば、パナソニック インフォメーションシステムズの発展・革新も、自らの技量・知見に磨きをかける一方で、OSSに代表される社外の知や新技術の積極的な取り込みによって支えられてきたという。また、知と技術の共創・共用という観点から、同社は、大和総研が主導する「アライアンスクラウド推進ソサエティ」に参加し、異企業間での「クラウド(プライベートクラウド・プラットフォーム)」の共用化も推進している。
さらに前川氏は今回、ITサービス企業の経営者としての立場から、「顧客視点」の重要性も説く。
「IT業界に時として見られるのが、ディマンド・サイド・ロジック(需要側論理)の欠如です。ただし、このロジックで物事を考えないかぎり、お客様の本当の満足は得られません。技術はこれからも猛スピードで変化し、進化し続けるでしょうが、それを利用するお客様のことを第一に考えなければ、サービス産業であるIT業界は衰退の一路を突き進むはずです。顧客視点を忘れては絶対にならないのです」
なお、先に触れたとおり、OSSは「ユーザー=開発者」という構図の中で発展を遂げてきた。つまり、OSSには前川氏の言う"デマンド・サイド・ロジック"がすでに組み込まれていることになる。それが、OSSの今日の隆盛につながっているのかもしれない。