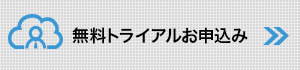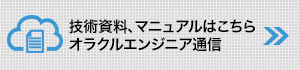「Oracle Cloud」は本当に使える? ノーチラス神林氏率いる技術者集団がホントのところを一刀両断
クラウドサービスは多彩なアプリケーションで利用されているが、それでもまだクラウド基盤で扱うには不向きな用途もあった。例えば、企業の根幹となる基幹システムで使われるRDBMSや、それと連携するバッチ処理だ。これらは、クラウド上では実効性能を高めることが難しいと言われてきたが、最近では事情が変わりつつある。並列分散処理による高速バッチ処理技術を得意とするエンジニア集団である株式会社ノーチラス・テクノロジーズが「Oracle Cloud」の性能を検証した。
株式会社ノーチラス・テクノロジーズ(以下、ノーチラス)は、「永続的にエンジニアリングができること」を目標の一つに掲げるエンタープライズ系IT企業だ。少数精鋭で高い技術力を誇っており、「ウチにはボンクラはいない」と代表取締役会長の神林飛志氏は豪語する。

株式会社ノーチラス・テクノロジーズ
代表取締役会長 神林 飛志氏
同社が得意とする分野は、高速なデータ処理が要求されるバッチ処理などのミドルウェア。現在では、並列分散処理技術を取り入れたオープンソースソフトウェア(OSS)のAsakusa Frameworkを主に扱う。さらにその実行環境として、単一ノードのマルチコア/マルチプロセッサ環境に最適化された、オンメモリ上で高速に動作するDAG実行エンジン M3 for Batch Processing(以下、M3BP) を株式会社フィックスターズと共同で開発、Asakusa Frameworkと組み合わせたソリューションAsakusa on M3BPとしてOSSで公開している。M³BPは単一ノードのメニーコア上で並列処理を行うための実行環境で、小〜中規模データサイズのバッチ処理に非常に適しており、中間結果が全てメモリ上に収まる規模のバッチにおいてはHadoop MapReduceやSparkよりも高速、かつ高いコストパフォーマンスが特長だ。Sparkとの比較では処理速度は2倍・ノード数は1/5、費用対効果で10倍の性能を発揮(5ノードでSparkを稼働させた場合との比較)する。
ベアメタルサービス登場を受けて
自社エンジニアがOracle Cloudを徹底検証
こうした分散処理技術は難易度が高く、本格的に手掛ける能力を持つ企業は決して多くない。ましてや、エンタープライズITの"本丸"に近い部分のコア技術を扱う企業となるとなおさらだ。この領域でノーチラスが存在感を発揮していることが、同社の高度な技術力の証と言えるだろう。
ノーチラスとOracleとの関わりについて神林氏は、「オラクルとは、顧客ベースが重なる部分がかなりあり、我々の関わったプロジェクトでもOracle Databaseから引き出したデータをバッチ処理するといったケースがよくあります。といっても、今までは人的な交流が中心でした」と話す。

株式会社ノーチラス・テクノロジーズ 川口 章氏
その関係に変化が生じたのは、オラクルがパブリッククラウドサービス「Oracle Cloud」において新たにベアメタルサービスを含む新しいインフラストラクチャ・サービス「Oracle Cloud Infrastructure」(以下、OCI)の一般提供を開始した昨年10月のことだ。一般的なIaaSサービスと比較して格段に高いパフォーマンスを発揮できるというOCIは、M3BPとも相性が良いと期待されるため、具体的にどれほどの性能を実現できるのかを検証することになったからだ。
神林氏は、ベアメタルの純粋な性能を把握したいという考えから、コア技術に関わる精鋭の2人をアサイン。フレームワーク開発を行っている普段のノウハウを生かして、3つの検証ストーリーのもとでOCIを検証することにした。3つのストーリーとは、「ベアメタルインスタンスと仮想インスタンスとの比較」「オラクルのベアメタルと他社クラウドサービスとの比較」「Oracle Databaseとのデータ入出力連携」だ。
結論から先に言うと、神林氏は、「パフォーマンスに関して、ここまで良いとは予想外だった。Oracle Databaseユーザーなら、まず最初に検討すべき価値がある」と、OCIの性能を高く評価する。
[PR]企画・制作 朝日インタラクティブ株式会社 営業部 掲載内容有効期限:2017年12月31日