講演より--「クライアントの疑わしい挙動を記録・分析、そして警告を発するクライアント・レピュテーションとは?」

フォーティネットジャパン コーポレートマーケティング部 部長 余頃孔一氏は壇上で、クライアントの疑わしい挙動を記録、分析し、警告を発する「クライアント・レピュテーション」を解説するとともに、同社のUTM(Unified Threat Management:統合脅威管理)「FortiGate」を紹介した。
余頃氏は冒頭、現在のサイバー攻撃が組織化され、分業化さえしていると指摘する。
「まずマルウェアを専門的に作成する人間がいて、犯罪シンジケートに売っている。その犯罪目的で作成されたソフト(crimeware)を用い、犯罪を『サービス』として代行し利用料を取るという動きがある。いうなれば「CaaS(crimeware as a service)」というものだ。このCaaSを使用して、企業や団体を攻撃する動きが増えている」(余頃氏)という。

フォーティネットジャパン
コーポレートマーケティング部
部長 余頃孔一氏
では標的型攻撃は、どのようにして企業に忍び寄ってくるのか。「まず、ITリテラシーの低い社員、支店、取引先、スマートフォンなどのような、企業などで、最も情報セキュリティが弱いと考えられる部署が狙われる」と余頃氏。
次の段階では、ID/パスワード、メールなど、2次攻撃に利用できる情報が盗まれ、最初に侵入したマルウェアが、他のマルウェアをインストールし、ある時機が来るまで、パソコン内に潜伏する。さらに、そこから、IT管理者、研究部門などのような、真の目標への攻撃と侵入が始まり、重要情報が外部に送信されてしまうのだ。
標的型攻撃に抗する対策としては「まず、入口が重要になる。マルウェアを侵入させないこと。可能な限り、ここで止めたいのだが、マルウェアが組み込まれたUSBメモリなどメディアを使われると止めようがない。そこで、パソコンなどのような内部のクライアント対策により、内部での拡散を封じ、外部へ出させない出口対策も必要」と、余頃氏は語る。標的型には段階があるため「マルウェアに侵入されたとしても、潜伏期間があるので、この間に発見することが重要だ」(余頃氏)という。
余頃氏は「サイバー攻撃が巧妙化する一方となったいま、入口、クライアント、潜伏期間、出口といった段階に応じた”多層的な防御”が望ましい」と指摘したうえで、「UTM(Unified Threat Management:統合脅威管理)は、さまざまな、防御のための要素を備えている」と話す。
フォーティネットジャパンが展開しているUTM製品「FortiGate」は「ハード、ソフト、サービスを、すべて自社で開発、提供しており、セキュリティ、ネットワーク、管理など、多彩な機能があり、ユーザ数無制限ライセンス」(余頃氏)などの特徴があるという。従来、企業、団体のIT環境を外部の攻撃から防衛するための要は、ファイアーウオールが主力だったが、余頃氏は「多層的な防御を実現するには、UTMに優位性がある」とする。
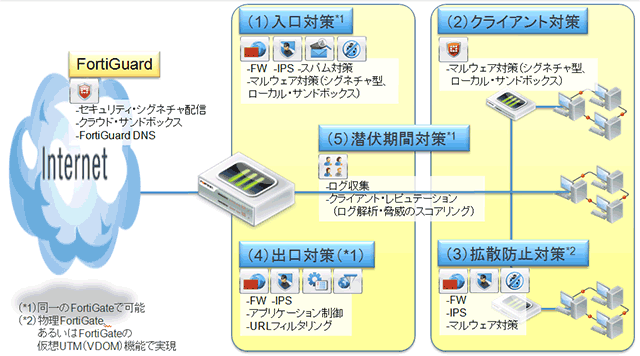 FortiGateで実現する標的型攻撃対策
FortiGateで実現する標的型攻撃対策※クリックすると拡大画像が見られます
「FortiGate」の目玉として挙げられるのは、この製品のOSであるFortiOS 5.0に搭載されている「クライアント・レピュテーション」だ。
この機能は、マルウェアに侵入されてしまった場合、潜伏期間に入っているマルウェアを検知する。パソコンなどクライアントを識別し、複数の振る舞いを基に、クライアントのレピュテーション(評価)を実行、脅威の状況をレポートし、クライアントの、疑いのある挙動の蓄積により、脅威のレベルを判断する。
例えば、クライアントが、存在しない「URL」へのアクセス、存在しない「IPアドレス」へのアクセス、業務上関係のない地域へのアクセスといった振る舞いを繰り返したとしたら、そのクライアントはマルウェアに侵入されている可能性が大きくなる。余頃氏は「このような対策を講じておかないと、脆弱な部署が狙われ、仮に大きな被害が出なかったとしても、他の攻撃のための踏み台にされる危険性がある」と語る。
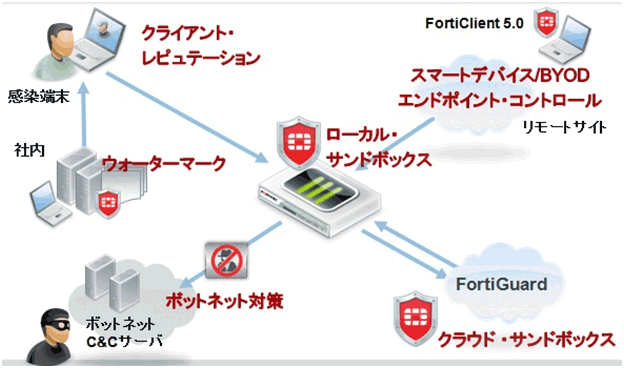 クライアント・レピュテーションをはじめとする、FortiOS 5.0のセキュリティ強化点
クライアント・レピュテーションをはじめとする、FortiOS 5.0のセキュリティ強化点※クリックすると拡大画像が見られます
「『FortiGate』とクライアント対策製品などを組み合わせ、多層的な脅威対策を確立し、可能な限り、脅威を低減化すべき」であると、余頃氏は強く訴えた。





