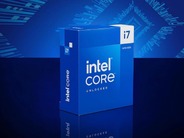サンフランシスコ発--IBMは他のどの競合企業よりもたくさんの知的財産を所有しているが、そんな同社がいま、その共有方法を学ぶべきだと考えている。
IBMのテクノロジー&ストラテジー部門バイスプレジデントIrving Wladawsky-Bergerは、当地で開催中のOpen Source Business Conferenceで講演を行い、企業が単独でやっていける時代はとうに終わっており、いまは一致協力することが時代の趨勢だと述べた。
「むかし--たとえば10年前なら、企業は自社で開発したものはすべてプロプライエタリでなくてはいけないと考え、さらに知的財産(Intellectual Property:IP)はどんな場合にも保護しなくてはならないと考えていた。だが現在では、外部コミュニティのエネルギーを活用したいと思う場合、知的財産に対するプロプライエタリなアプローチと、よりオープンで協力的なアプローチとのバランスをうまく取らなければならなくなっている」とWladawsky-Bergerは述べた。
IBMはオープンソースに関して、まさにこの両方を組み合わせたアプローチを採ってきた。
同社はこれまで何年も、積極的にLinuxの普及に努め、数百名ものプログラマをその改良に当たらせてきた。また「Eclipse」プログラミングツールプロジェクトも立ち上げた。だが同時に、「WebSphere」ビジネスソフトウェアや「DB2」データベースなど、プロプライエタリなソフトウェアの販売も続けている。
IBMはまた、同社の持つ500件の特許をオープンソースプロジェクトが利用できるようにしたが、一方でより多くの特許を確保し競合他社に水をあけようともしている。
Wladawsky-Bergerは講演のなかで、「新しいタイプの技術革新サイクル」について説明した。このサイクルのなかでは、企業は拡大しつつあるオープンソースソフトウェアの波の一歩先を行くことができるという。
「自社の人材をコミュニティに参加させ、知的財産の一部を提供することで、コミュニティは向上する。そうしたうえで、オープンソースプラットフォームに基づくプロプライエタリ製品を開発すればよい。これらのプロプライエタリ製品は、時期が来ればプロプライエタリとしての価値を失うだろう。だが、オープンソースコミュニティにこれを譲り渡すことには価値がある。こうしたサイクルを繰り返していけばよい」(Wladawsky-Berger)
同様の考えを持つ企業幹部はほかにもいる。Sun MicrosystemsのプレジデントJonathan Schwartzは米国時間5日、オープンソースソフトウェアをベースにした「Participation Age」と同氏が呼ぶ考えを説明するとともに、それが新たなログラマや新たな国家経済をコンピュータの領域に惹きつける力について述べた。
さらに、XimianやSuSE Linuxの買収によりオープンソース分野に参入したNovellもまた、プロプライエタリとオープンソースを組み合わせたアプローチを採用している。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ