次に、生活者視点での利用シーンを見てみましょう。
流通経済研究所の情報連携ワーキンググループでは、生活者視点で未来の情報連携を研究しています。
販売時点情報管理(POS)システムを活用することで地域別や時間帯別、性別、年齢層別の商品売れ筋動向は、すでに把握できています。これに個人の買い物情報を電子化、クラウドで活用する電子レシート機能を合わせると、生活者、消費財メーカーともに、メリットがあります。
POS情報と電子レシートの組み合わせで享受できるメリット
- 生活者は自動で家計簿を作ることができ、購入履歴も管理できる
- 購入品の付帯情報(取扱説明書、保証書、保険、ポイントなど)を管理でき、必要な時に自在に取りだすことができる
- メーカーは、自社商品をたくさん購入してくれる顧客に対して、集中的に多くのポイントを還元でき、感謝の気持ちを伝えることができる
未来を支えるデータ連携基盤
今までお話したとおり、企業も個人も面でつながる社会の実現には、EDIを含むデータ連携を支える基盤システムが重要になります。
必要な要件としては、以下が考えられます。
- 企業やクラウド上にある業務アプリケーションのデータをリアルタイムでつなぐ通信機能やワークフロー機能
- データ連携の際、つなぐ先にあわせて自在にデータを変換し、管理する機能
- 個人情報の管理なども含めたセキュリティ機能(データの分割保管、項目単位のセキュリティ確保技術も求められ、特に重要)
このような環境がそろったとき、インターネットベースの新しいEDIが活躍し普及するのです。すべての企業やサービスが、同時にかつシームレスに、そして、セキュアにつながっている状態!まさに未来の世界が待っているような気がしてワクワクしてきます。
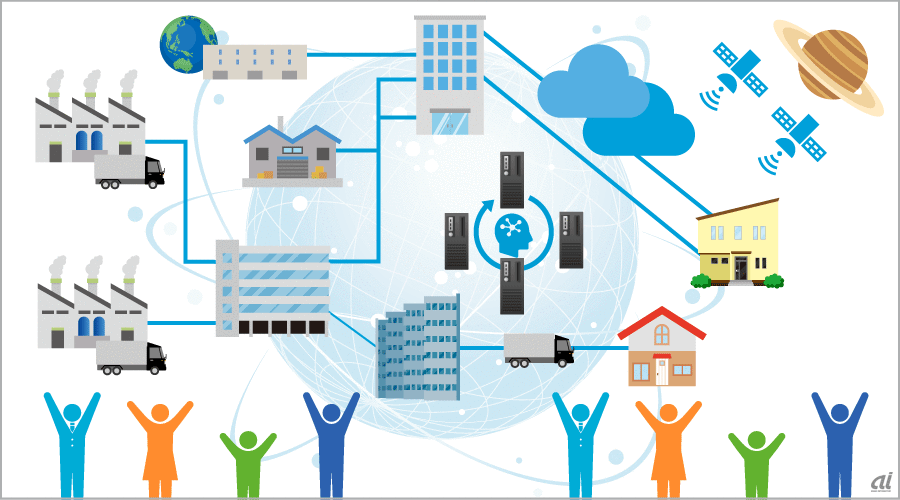
データと一緒にワクワクする未来へ(出典:データ・アプリケーション)
4回にわたって「固定電話のIP網移行から未来のEDIまで」をご紹介しました。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからも従来型EDIを超えた未来のEDIに向けての研究を続けていきたいと思います。 ご意見等ございましたら、ぜひお聞かせいただければ幸いです。

- 藤野 裕司
- データ・アプリケーション
- エグゼクティブコンサルタント
- 1980年代初頭より企業間データ交換を手掛け、1991年より日本の標準EDI開発・普及に携わっている。公的、業界、研究、講演執筆などの活動や、企業、業界EDIコンサルティングを通じ、日本のEDI発展に多く関わりを持つ。現在は、「固定電話のIP網への移行」を中心にEDIコンサルタントとして活動している。製造、流通、物流、金融業界など幅広い領域をカバーし、業界標準EDIやSCMの普及等がメインテーマ。製造業界ではグローバルEDIの推進、流通業界では流通BMSの展開、最近ではアプリケーションクラウドとの連携やIoTとの融合なども視野に入れた取り組みを進めている。その他、コンピュータセンター運営、EDIの技術サポート経験をベースに、ユーザーの立場から考えるEDI/SCMを提言。 産業界のみならず総務省、経済産業省、中小企業庁、国土交通省、大学関係にも多くの人脈を持ち、産官学にわたる幅広い情報網を持つ。





