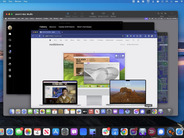重層下請構造の2次、3次となると、私たちとは直接の契約関係にはないので、どこまでセキュリティを担保していくのかという話になっていきます。そうすると、業務手順の中にいろいろなことを入れ込んでいかないといけなくて、昔はPCを使う人だけフォローしていけばよかったのですが、今はそれこそスマホや、いろいろなデバイスがありますし、今後のIoTまで含めて考えると監視する範囲は無限に広がります。
ZDNet:防御ではなくて早期検知とか、対応というところを重要視していらっしゃる企業がだんだん増えてきているというお話しだと思います。具体的にCSIRTとしてなるべく早期検知をして、被害を最小限にするためにどんなことをしていらっしゃるのでしょうか。

デロイト トーマツ リスクサービス(DTRS) サイバーリスクサービス シニアマネージャー 岩井博樹氏
岩井氏:皆さんそうだと思うのですが、結局は費用対効果を考えてしまいますよね。入口出口、できれば内部も監視、対策もした上で、データ保護。侵入されてしまうことが前提であれば、データがいつ漏れてもおかしくないと考えると、ファイルの暗号化は必須になってきます。
攻撃が増えただけでイタチごっこになるので、入口出口はそれなりの対策で、ただ内部はちゃんと守らないと何かあったときに言い訳ができないところです。内部はこの十数年、攻撃者が侵入した後の手口が変わりません。ネットワークへの侵入後の不正操作は一番手を入れないといけないところなのですが、とにかくお金がかかるというのと、運用が大変という課題があります。

ディー・エヌ・エー(DeNA) システム本部 セキュリティ部 部長 DeNA CERT 茂岩祐樹氏
社内のネットワーク通信は、MSS(マネージドセキュリティサービス)に投げればなんとかなるというものではありません。業務システムが出しているトラフィックだったり、特にデロイト トーマツですと監査データを含む機微情報が流れるので、MSSはもってのほかということになったりします。
流れているトラフィック、データも見られてしまうわけですから、それは難しい。やはり内部の対策は効果が期待できるのですが、そこに対するコスト面や運用という点が結構悩みどころですね。
茂岩氏:DeNAでは、防御、検知、対応の3つをバランス良くやるのが大事だと思っているのですが、やはりアンチウイルスで引っかからないものは必ずあるという前提でやっています。そうしたら次にそこをすり抜けてきてPCがマルウェアに感染したら、一番最後のストレージで個人情報を取られるということだと思います。その層で個人情報までいけないように多層にするということはまず基本としてあります。