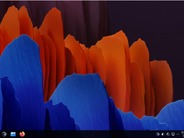エンタープライズアーキテクチャ(EA)により、組織の業務と情報システムの理想的な全体像を表す「設計図」が作成される。エンタープライズアーキテクチャが企業の設計図を整備する活動だとすると、なぜ設計を意味する一般的な用語である「デザイン」ではなく、「アーキテクチャ」という言葉で表現されているのであろうか?
一つの理由は、「設計(デザイン)」という言葉を使うと、部品の設計図として着目されてしまいがちなことにあると思われる。エンタープライズアーキテクチャが目指すのは組織の「全体最適」である。そのためには、企業内セクションの役割を詳細に示す「設計図」ではなく、企業の「全体設計図」が必要がある。アーキテクチャがもともと建築様式を意味する言葉であるように、アーキテクチャという言葉を用いることで、細かく分断された詳細ではなく、全体像を把握する必要性を表現しているといえる。
そして、アーキテクチャという言葉が使われる理由がもう一つ。それには、電気電子学会(IEEE)による定義が参考になるだろう。IEEEによると、アーキテクチャとは「システムを構成する各コンポーネント、各コンポーネント間の関係、コンポーネントと環境との関係、およびその設計と進化を支配する原理に体現された、システムの基本的な構造」のことである。この定義はわかりにくいが、注目したいポイントは「コンポーネント(構成要素)間の関係によって示された全体像」がアーキテクチャであるということである。アーキテクチャという言葉は、単に全体像を把握する必要性を表しているだけでなく、その方法も示している。すなわちEAには、「構成要素間の関係を明らかにすることによって全体像を把握する」ことが求められているからだ。
EAには、このアーキテクチャの考え方をビジネス分野にまで拡張し、ITとビジネスを共に「構成要素間の関係」の視点から整理しようという意図がある。ビジネス分野ではアーキテクチャという言葉はEA以前にはあまり使われてこなかった。しかしながら、「要素関の関係により全体像を明らかにする」ことがアーキテクチャという視点に立てば、例えばポーター教授が1985年に提唱したバリューチェーンの考え方もアーキテクチャに他ならない。バリューチェーンに基づく戦略策定は、購買から製造、販売、サービスにいたる企業活動の全体像と、それらの間の関係に基づくものだからである。このように、アーキテクチャという言葉は使っていなくても、その「要素関の関係」という考え方自体はビジネス分野でも非常に重要なものであった。その結果、ITとビジネスの連携を目指して両者を融合したエンタープライズアーキテクチャという考えが生み出され、多くの経営者が注目するようになったのだと思われる。
(みずほ情報総研 EAソリューションセンター 近藤 佳大)
※本稿は、みずほ情報総研が2004年9月28日に発表したものです。