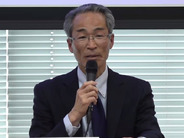藤井氏は、どうしても外国にデータを置きたくないというポリシーがある場合は仕方がないとしながら、「たとえ愛国者法でGoogleにデータの開示要求があったとしても、 Googleの法務部門を通して正規の手続きをとらなければ開示することはない」と説明する。
セキュリティリスクについては、「○のときに△が起きたとき」といったように、発生条件を掛け算で求めると、値が限りなくゼロに近い場合もある。理論上の可能性と実際に起きる可能性を認識する必要がありそうだ。
セキュリティに加え、もう1つクラウド環境への移行で気になるのが稼働率の問題だ。Google Appsは有料ユーザーに対して99.9%の稼動率を提示している。一方、これまでGoogle Appsの障害を伝える報道がしばしばあり、潜在ユーザーの多くがGoogle Appsを評価する際に気にしている点と考えられる。Googleは「Apps ステータスダッシュボード 」で、一般ユーザー向けとGoogle Appsユーザー向けサービスの稼働状況を公開している。これによると、4月18日現在履歴データのある2月19日から4月18日の間で、軽微なものを含めGmailに障害が起きたのは、2月25日、3月7日、4月3、4、5、6日、4月18日であることが分かる。

Google Appsの稼働状況を公開
最も近い4月18日は、午前1時42分に「Gmailの問題は調査中です。間もなく詳細情報をお知らせします」とのアナウンスあった。その後、2時24分に「Gmailサービスは、一部のユーザーに対しては既に復旧していますが、まもなくすべてのユーザーに対して解決する見込みです」と追加。2時46分には復旧が告知された。障害が頻発した4月初旬は、4月4日の午後11時25分に「0.05%以下のGmailユーザーが影響を受ける問題が発生しております」と通知された。
こうした稼働率への評価は、導入企業によって異なる。例えば、Gmailについての障害発生頻度を考える際に、自社にかかわる障害の発生確率と、もし自前でシステムを用意した場合に想定される確率を、コストやビジネスの観点から考慮しなければならない。
小さなものを含め、Gmailやカレンダー、ドキュメント、スプレッドシートなど、製品ごとに障害の発生状況を常に公開する体制になっていることは、悪い情報も常に把握できるという面でユーザーに安心感をもたらすであろうということである。
これまで、システム障害時に正確な情報が出てきにくい傾向があることを考えると、ここでも情報共有の発想転換が起きているといえそうだ。
Keep up with ZDNet Japan
ZDNet JapanはFacebookページ、Twitter、RSS、Newsletter(メールマガジン)でも情報を配信しています。