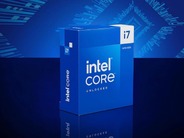未来の情報管理社会を風刺したGeorge Orwellの『1984年』(1949年発行)が売れている。この1月には米Amazonで売り上げ1位となったが、それとならび称される技術官僚主義のディストピア小説『すばらしい新世界』(1932年発行)も10位以内にランクインしたそうだ。
その著者であるAldous Huxleyは1954年に『知覚の扉』を発表。サボテンに含まれる「メスカリン」を自ら服用し、知覚が変化して「偏在精神」に触れた体験を記述した。
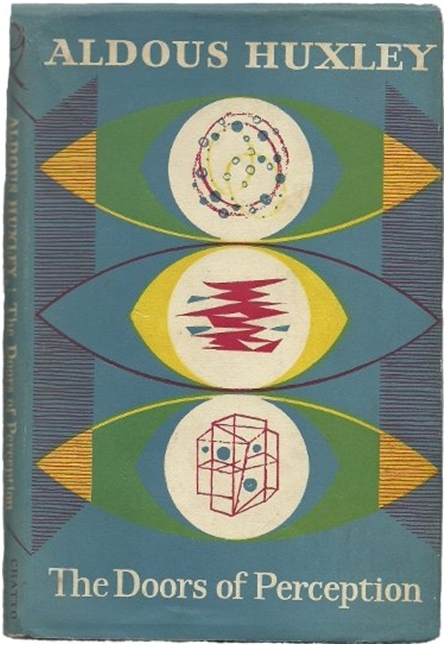
(写真)「知覚の扉」の初版本の表紙。1960年代に活躍した米ロックバンド「The Doors」の名前の由来となるなど文化、芸術、学術問わず多方面に影響を与えた。
Cover of the first edition of ''The Doors of Perception'', released by Chatto and Windus in 1954
もちろん現在このような化学薬品は厳密に法規制されている。しかし今はケミカルな形ではなくメカニカル、コマーシャル、インダストリアルな形で日常生活にテクノロジが浸透し、人間と情報と心の関係は変化している。
そしてそれを加速させるのが人工知能(AI)で、人間の脳と感覚、そして心自体を拡張しているのではないか。
Huxleyの言う「偏在精神」は、フランスの哲学者Henri-Bergsonの考えに概念だ。
要約すると「人間は自分の身に生じたことをすべて記憶し宇宙のすべてを知覚できる(=偏在精神)が、無関係の“巨大な量な知識”に押しつぶされないように“脳や神経系、感覚器官”が“除去作用的に機能”する」というものである。
今日の人間の“脳や神経系、感覚器官”を機械化したともいえる認知テクノロジ「AI」ーー。果たしてAIは、IoTやCPS(サイバーフィジカルシステム)などでもたらされる地球規模、宇宙規模での“巨大な量な知識”である「ビッグデータ」を、どのように“除去作用的に機能”すなわち、「構造化」していくのだろうか。
コミュニケーションの変化で広告とICTが急接近
現在、筆者は広告会社の企画部門でテクノロジを活用した新しいコミュニケーションの調査および製品やサービスの開発業務を行っている。「ZDNetはIT業界向けの情報メディアだから広告業界はあまり関係ないのでは」と思われるかも知れないが、実はそのようなことはまったくない。
むしろその接近ぶりは戸惑うほどで、実際、筆者がおつきあいする社外のパートナーは理工系の色濃いテクノロジ系企業ばかりとなった。まずは、筆者が本業とする「コミュニケーション」軸でその接近に至る変化を見てみよう。