最近は、自分が書いた記事について、部分的にでも人工知能(AI)で生成したものだと思われたりしないように、冒頭に断り書きを書いておくべきかもしれないと感じている。なお、この記事の作成には人間の脳(正確にはライター1名と編集者2名の脳みそ)しか関わっておらず、その中にチップが埋め込まれた脳はない。
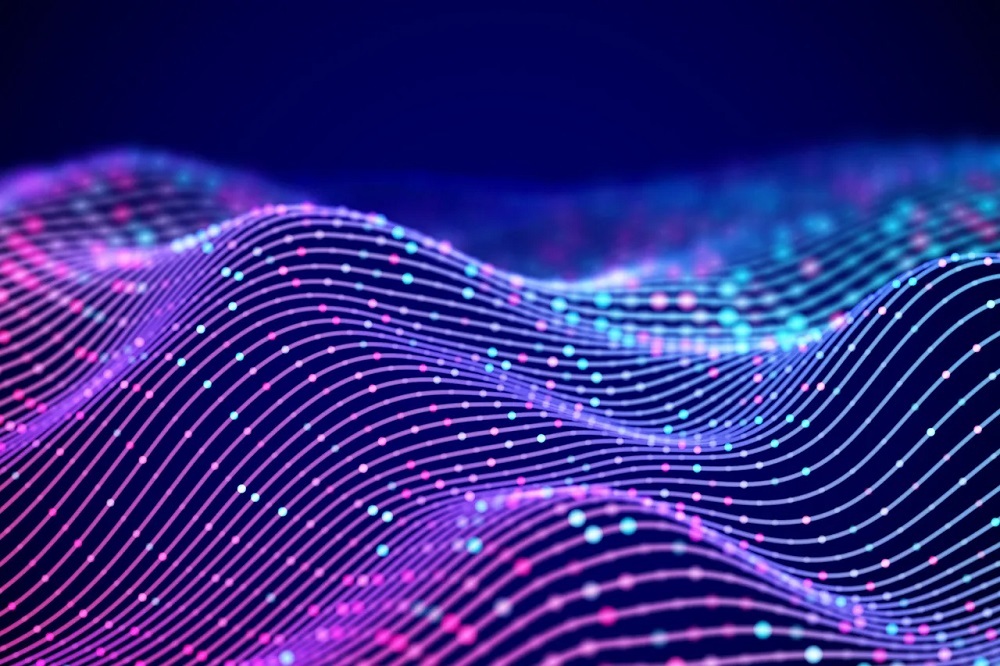
提供:Getty Images/maxkabakov
残念ながら私たちは、もはや簡単には人間とロボットを見分けられなくなっている。今はまだ、ターミネーターに出てくるようなスカイネットがすべてを管理する社会にはなっていないが、長年の間、着実に(主にバックエンドで)進歩してきたAI技術が、一般の人々にも利用でき、理解できるものになったことで、今日のAIの能力は1つの転換点を迎えている。
このような状況になったのは、生成AIプラットフォームである「ChatGPT」が、人間を模倣し、さまざまな作業を手助けする能力で多くの人を魅了したためだ。ChatGPTが手助けしてくれる作業は、ソフトウェアのコーディングや、旅程の計画、電子メールの文面やエッセイの作成など多岐にわたる。ChatGPT以外にもさまざまなAIアプリケーションがあり、その中には、有名なアーティストや作家に「インスピレーションを得た」画像や曲を作れるものもある。
そしてそこには、一部の業界におけるAI利用についてどのように線引きすべきかという議論の核心がある。
筆者のようなジャーナリストの仕事に関して言えば、その線引きは明確で、事実誤認や盗用は絶対に受け入れられない。そのため、ChatGPTのようなツールは、筆者の仕事には(たとえ調査の補助であっても)まったく役に立たない。
おそらく、弁護士たちも同じようなことを考えているだろう。最近、あるニューヨーク州の弁護士が、訴訟の準備書面に、実際には存在しない架空の判例を引用するという問題が起きた。お察しの通り、この弁護士がChatGPTに調査を任せたところ、虚偽の情報源に基づいて文章を生成したのだ。
しかし、線引きが必ずしも明確でない場合もある。
人気アーティストの曲調をベースとする音楽の生成だけでなく、特定のポップスターに酷似した声色で「歌われる」楽曲の作成にもAIが使われることが増えている。例えば、シンガポール出身の歌手Stefanie SunがAvril Lavigneの「Complicated」をカバーしたように聞こえる楽曲が登場したが、その楽曲の歌声は、Sunが実際に歌ったものではなかった。
素人の耳には、AIが生成した声は、2000年のデビュー以来、3000万枚以上のレコードを売り上げたSunにそっくりに聞こえる。しかし、Sunのファンによると、AIの歌声にはSunの感情的なニュアンスが欠けているため、容易に識別できるという。
しかし、そうした認識が今後変わる可能性があることは、Sun自身も認めている。Sunは5月にブログで、自分の全盛期が終わった今、このAIペルソナは自分よりも大きな名声を獲得している、と冗談めかして書いた。また、わずか数分で新しいアルバムをリリースできる相手と競争するのは不可能だとした。
Sunによると、AIは情報を処理し、つなぎ合わせて、意見や考えを形成しているという。これは、人間にしかできないと信じられてきたことだ。AIがさらに進化して、人間の感情を模倣できるようになるのは、時間の問題かもしれないとSunは示唆した。
「この新しいテクノロジーは、あらゆるもの、あらゆる人間を量産できるようになるだろう」とSun。「人間は特別ではない。人間はすでに予測可能であり、残念なことに、合成することもできる」
報道によると、現時点では、生成系AIに関する法規制が整備されていないため、Sunのレーベルは法的措置を検討していないという。
Sunは自分のAIペルソナを潜在的なライバルとみなしているが、カナダのシンガーソングライターであるGrimesは、AIが合成した自分の声を使って作られた音楽という概念に対して、よりオープンな姿勢を取っている。つまり、そのような音楽を作成した人とロイヤルティーを折半すればいい、という考えだ。Grimesはそうした楽曲作成者に対し、自身の公式ウェブサイト経由で音楽を登録するよう呼びかけている。また、AIプロセスを支援するため、自身のボーカルサンプルをウェブサイトで公開する予定だ。Grimesは、「自分が機械と融合するのはクールだと思う。私は、あらゆるアートをオープンソースにして、著作権を廃止するという概念を気に入っている」とツイートした。
同じ業界でも、新しい収益モデルを受け入れない人もいる。
米国のラッパーであるIce Cubeは、ポッドキャストのインタビューで、自分の声を使ってAIで曲を作成した場合、曲を作った人物はもちろん、それを再生するプラットフォームも提訴すると述べている。
同氏のコメントは、カナダのラッパーであるDrake氏と、同じくシンガーソングライターのThe Weekend氏が作ったものに聞こえる、AIが作成した「Heart On My Sleeve」という曲が発表されたことを受けてのものだ。この2人のカナダ人アーティストは、過去に何度もコラボレーションをしていることで知られている。
Heart On My Sleeveは、「TikTok」や「Spotify」などのさまざまなプラットフォームで拡散されたが、両アーティストの所属するレーベルの申し立てにより削除された。この楽曲は今でも「YouTube」で視聴できる。
この楽曲の制作者は、2人の作品やスタイル、声を学習させたAIモデルを使ってこの曲を作ったと言われている。
Heart On My SleeveのようなAIが生成した楽曲が潜在的に抱えている法的な問題については、すでに詳しい法律家がおり、法律家にインタビューした記事でも議論されているため、ここで詳しく取り上げることはしない。この曲は、フェアユースや不実表示に関する多くの疑問を投げかけていると同時に、問題はものまねやトリビュートアクトとも関わりがあると述べるにとどめておく。
AIの広がりがもたらす問題の本質
しかし筆者は、AIの仕組みと、人間のアーティストやミュージシャンがインスピレーションを得ている方法には類似点があると考えている。偉大なアーティストが、先達の影響を受けているというのはよく聞く話だ。米国のシンガーソングライターであるBruno MarsはElvis PresleyやThe Beach Boysに影響を受けたと語っているし、Billie Eilish氏もThe BeatlesやGreen Dayの影響を受けているという。
これらのアーティストは、ほかのアーティストの楽曲を聴いて、そこから学びながら育ち、自分のスタイルと響き合う部分を取り込んで自分のアートを生み出している。
ある意味では、これはChatGPTのような大規模言語モデルや生成AIツールがやっていることそのものだ。AIツールは、過去の作品から学んだことをベースにして、新たな作品を生み出している。違うのは、人間の精神が自分が成長し、学んできた中で、素晴らしいと思った作品から影響を受けて形作られるのに対して、AIモデルには本質的に偏りがなく、計算能力が十分にあるため、成長のために学ぶものを選択する必要がないということだけだ。
つまり、著作権を侵害しておらず、不実表示もしていないのであれば、過去の有名な作品からインスピレーションを得てAIが生成したコンテンツは、有名作品からインスピレーションを得て人間が生み出したコンテンツと本質的に違いがない。そもそも、世の中に出回っている製品のほとんどは、基本的な構造を基盤として、ベストプラクティスに基づいて作られているのだ。
これは、英国のシンガーソングライターであるEd Sheeranが、Marvin Gayeの楽曲をめぐり、訴えられた裁判で、同氏の行為が著作権侵害にはあたらないという判決を勝ち取った際に使ったロジックとほとんど同じだ。Sheeran氏の弁護士を務めたIlene Farkas氏は、陪審員に対して、似ているとして問題となったGaye氏の曲とSheeran氏のコード進行やリズムは「音楽のアルファベットの文字」だと主張した。Farkas氏は、「作曲家は、今も、そしてこれからも永遠に、これらの基本的な音楽の構成要素を自由に使えなくてはならない。さもなければ、音楽を愛する私たち全員が貧しくなってしまう」と述べた。
ミュージシャンでYouTuberのRick Beatoは、この主張を「コード進行に著作権はない」と簡潔に言い換えている。
では、AIが成長を続け、あらゆるところで使われるようになったら、人間にはどのような役割が残るのだろうか。人間は、高度な処理能力と学習能力を持つAIと競争の中で、どうすれば差別化できるのだろうか。
筆者は、私たち人間は、イノベーションを続け、知識を創造的に活かし続ける必要があると考えている。そうした基礎の上に自分の工夫を加えて、ほかの人にはあまり使われていない要素を取り込んでいく必要がある。
インターネットが出現して普及していったときのように、AIという新しい技術を得たことで、怠惰になるようなことがあってはならない。Beatoも、「同じことを繰り返してはならない」と語っている。
筆者は最近、あるラウンドテーブルの司会を務めたのだが、その際、自分の参加者への質問は自分の頭で考えたものであり、AIの力を借りたものではないと発言した。そのとき、数人の参加者が「それのどこがいけないのか」と尋ねてきた。
それに対する筆者の答えは、考えるまでもないものだった。ChatGPTのような生成AIツールを使えば、交わされた議論に基づいて、絶妙な質問のリストを導き出せたとしても不思議はない(皮肉にも、その時の話題はAIに関するものだった)。しかし、会話の進行に合わせてその場で質問を変えていくことはできなかっただろう。
筆者が司会をするときには、あらかじめ質問のリストを作っておくのだが、ラウンドテーブルが始まってからも、参加者が出すさまざまな意見に合わせて常に新しい質問を用意し続けている。議論の中では、国内の業界の状況や、これまで語られたことがなかった個人的なエピソードについての話が出てくることが多く、議論の展開に合わせる形で質問を変えていくわけだ。
筆者のありふれたユーモアのセンスを含めて、こうした工夫をAIモデルで再現するのは(少なくとも今はまだ)簡単ではない。そして筆者は、AIの時代になっても、こうした形であれば自分の知識やスキルである程度の競争力を保てるのではないかと思っている。
この記事は海外Red Ventures発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。






