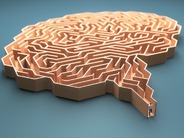コミュニケーション能力が劣っていると判定される、あるいは自ら「苦手」と思い込んでいる人がいる――こういう人は、自分や周囲から何かのきっかけでその「レッテル」を貼って/貼られてしまったがために、「コミュニケーションの舞台」にあがる意欲が減衰し、舞台から退却している人、いわゆる「非コミュ」だといえるだろう。
しかし、協働とかフレキシビリティとか情動、差異が重視されるいわゆるポストフォーディズム化の社会において、非コミュは、まったく不利になる。そこで本稿では、非コミュに悩み、そこから脱出したいと望む人のために、まず肝心の「コミュニケーションの舞台」にあがるためのアドバイスを紹介する。
#1 初めて会う相手だと緊張して、何を話したらいいかわからない
コミュニケーションは「観察」からはじまる。そして観察は「好奇心」に強く影響される。つまり、相手に興味を抱くことによって、結果としてコミュニケーションが発生するといえる。そして、興味を抱くためには、相手が何を考え、感じているのか、あるいはどんな背景を持っているのかを知る必要がある。したがって、自分をアピールするために「うまく話をしよう」とするのではなく、相手がどのような人物であるのかを探求することに徹すれば、話は尽きないはずだ。
#2 友人とは楽しく話せるのに、ビジネスだとうまく会話できない
ビジネスの世界では、言動や結果の多くが「評価」される。さらに、それに対する有形無形の「報酬」や「罰則」が適用され、少なからず人々は、その判決を体験する。しかも、それらは人によって成されるため、往々にして不平等であったりするわけだ。
コミュニケーション能力は、不平等という観点から見ると、きわめてやっかいな性質を持っている。自分がいじめられた、不当に恵まれなかったと感じると、この能力は損なわれやすい。つまり、逆に考えれば、評価に対する恐怖心や不信感を克服することさえできれば、友人と会話するときのように自然で魅力的なコミュニケーションを発揮できるということでもある。そして、そのきっかけとなるためには、ほんの少しの成功体験があればいい。