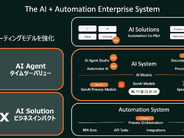Microsoftの「Windows 10」向けの新しいウェブブラウザを開発しているチームは、米国時間5月11日付けの詳細なブログ記事で、同社が「Microsoft Edge」のリリースで導入するセキュリティ上の改善点について、いくつか説明している。
Microsoftは、独占禁止法をめぐる議論で、「Internet Explorer」はWindowsの中核的機能として「統合」されており、切り離すことができないと主張していた。同社はその議論に決定的に敗北し、それが間接的に、欧州圏での「ブラウザ選択画面」につながった。独占禁止法をめぐる別の議論の結果として、WindowsのKやKNバージョンのような奇妙な製品も生まれることになった。こうしたSKUでは、「Windows Media Player」が取り除かれており、Microsoftに多大な負担を発生させている。そして筆者の知る限りでは、実際の顧客はこうしたSKUを全く購入していない。
しかし、そのブログ記事の中ほどに埋もれていた小さな見出しが、筆者の目に留まった。その小見出しは、1990年代後半に始まり、議論を呼んだ米国政府対Microsoftの独占禁止法訴訟を思い出させた。
「Microsoft Edgeはアプリである」

Microsoftが20年近く前に主張していた中心的な論点から考えると、その変化は計り知れない。
その公判の事実認定の文書を今読むと、ワームホールを通って、別の世界に来てしまったような気がする。
例えば、「現実的なWindowsの代替品」という項目では、「Intel互換PC」の市場と、「OS/2」「Linux」「BeOS」といった、当時流通していたOSについての非常に長い議論がある。Thomas Penfield Jackson判事は、Appleが数年後に、Steve Jobs氏の「NeXTSTEP」をベースとするOSを搭載した、Intel互換PCへの移行に成功することなど知る由もなかった。このNeXTSTEPは、その10年前から既にあったものだ。
一方で、Linuxは最終的に成功を収めることになるが、それはひとえに、「Android」へと形を変えたことと、非x86、非PCのモバイルプラットフォームを支配したことによるものだ。
「Netscape」のビジネスモデルについて書かれた長いセクションを読むと、やはり奇妙な感じがする。このビジネスモデルは、ユーザーにウェブブラウジングソフトウェアの料金を請求するということが大きな位置を占めていた。裁判所は、Microsoftが相当な金額を請求しないままにしており、自社ブラウザを無償提供することで、明らかにその独占力を乱用していると主張していた。