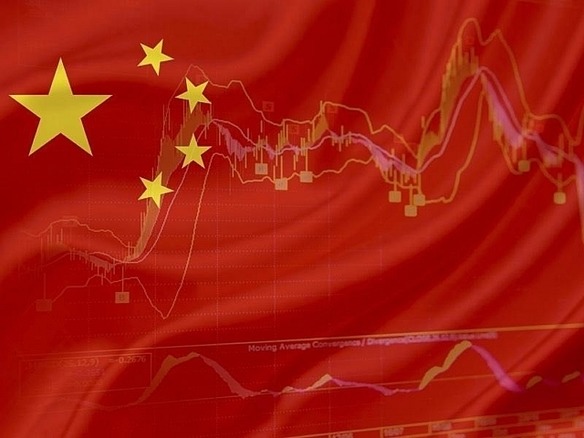貧富の格差が激しい中国で、阿里巴巴(Alibaba)や騰訊(Tencent)をはじめ、さまざまなネット企業が公益事業に取り組んでいる。
インターネット上での寄付系の交易運動は、最初は1995年に中国の掲示板上で、ある山東省の女性患者を助けようという草の根的な動きから始まった。やがてミニブログの「微博(Weibo)」が普及するとアルファブロガー(「大V」と呼ばれる)が、時々貧しい人々に向けて義援を行うよう声掛けをするようになった。また騰訊は2014年に「微信(WeChat)」の一機能として、知り合いと一緒に寄付をする機能「一起捐」を追加した。これらによりそれなりの金額が集まったが、見ず知らずの人や地域を助けようと駆り立てられる人は多くなかった。
中国の多くのネットユーザーが自ら義援金を支払おうと動いたのは、2008年の四川大地震の募金であった。当時の阿里巴巴、現在の〓蟻金服(Ant Flinancial。〓は虫へんに馬)の第三者決済サービス「支付宝(Alipay)」が四川大地震の後に公益プラットフォームをリリースした。当時は国民総参加といった雰囲気で募金が行われたが、支付宝には2017年8月末までに計2億回、9億6700万元の義援金が送られたという。
一方で2011年には「郭美美事件」と呼ばれる義援が眉唾となる事件が発生する。さまざまなところで書かれているので詳しくは調べていただければ分かるが、簡単に言えば郭美美という成金女性が「赤十字社と関係を持っている」とネットでうわさされ、義援金が彼女の懐に入っているとデマ情報がインターネット上を駆け巡った事件である。当時は今よりもネットユーザーに金銭的な余裕がなく、金持ちへのひがみが強かったため、義援金をやめようとする人も出てきた。
中国でインターネットの義援の形が変わったのは、PCからスマートフォンに利用がシフトした2015年以降だ。各ネット企業のリリースする公益プラットフォームは、個人の財布が痛まないものへと変わっていく。
騰訊は2015年、微信で計測した歩数に応じてさまざまな義援ができる「益行家」をリリースした。2018年10月までに計7億3000万回、8億3900万元の義援金が送られた。金額的には四川大地震と変わらないが、その何倍もの回数の義援がされたことは、ハードルが下がった証といえる。Uberのような配車サービスの「滴滴(Didi)」にもドライバーが走った分だけ義援ができるという機能がある。
〓蟻金服が2016年に追加した義援サービス「〓蟻森林」は、ニュースでしばしば報じられたり地下鉄駅の広告で表示されたりすることから、今のネットユーザーが最も思い浮かぶ義援サービスかもしれない。支付宝で光熱費や地下鉄での支払を行うと、抑えた二酸化炭素発生分を「〓蟻森林」に振り分け、一定数に達すると内蒙古自治区の植樹地域に1本植樹するというものだ。ネットユーザー一人ひとりがキャッシュレス化を進めた結果、環境にも優しいのが分かりやすく理解でき、貢献できる機能なのだ。
ECサイト大手の「京東(JD)」の取り組みもまた面白い。EC市場は巨大化しているとはいえ、農村部はまだ物流網が満足でなく、つまりは配送人員や配送インフラが不十分であることから、中国全土の農村部に倉庫と物流ステーションを構築し、非政府組織(NGO)などとともに職業学校を建設し、農村部での人材育成と雇用を進めている。
さらに京東は微信の歩数計上機能と提携し、農村部の貧困対策に貢献できる「※歩鶏(※は足へんに包)」という義援サービスをリリースした。※歩鶏は10万歩ごとに1匹のひよこが貧困農家に送られて、京東の指導の下で鶏を育て、その名の通り生鮮食材を扱う「京東生鮮」上で販売できる(100万歩分送れば市場価格の3倍で販売できる)というもの。さらに京東のフィンテックを担当する「京東金融」の貧困向け少額融資商品を活用し、貧困農家や貧困農村の義援を加速させる。
脱貧困の公益事業ができるとともに、自社サービスが利用されたり、商品が売れたりするビジネスであるが、その利用にはスマートフォンやキャッシュレス決済の普及が不可欠となる。
- 山谷剛史(やまや・たけし)
- フリーランスライター
- 2002年から中国雲南省昆明市を拠点に活動。中国、インド、ASEANのITや消費トレンドをIT系メディア、経済系メディア、トレンド誌などに執筆。メディア出演、講演も行う。著書に『日本人が知らない中国ネットトレンド2014』『新しい中国人 ネットで団結する若者たち』など。