近年は、企業の間で人間が手掛ける定型作業をソフトウェアのロボットプログラム「RPA(ロボティックプロセスオートメーション)」の処理に置き換え、省人化を図る取り組みが進んだ。ただ、RPAの適用効果は決められた作業(タスク)の範囲であり、本質的な業務改革には不十分との指摘もなされている。NTTデータ イントラマートが10月23日に開催した「intra-mart LIVE!」では、同社代表取締役社長の中山義人氏がユーザー企業とともに、RPA導入の次なるステップとして業務プロセス全体を最適化していく方策を紹介した。

NTTデータ イントラマート 代表取締役社長の中山義人氏
なぜ、RPAの次が業務プロセス全体の最適化なのか――同イベントの基調講演の最後に中山氏は、「かつてBPR(Business Process Re-engineering)が注目されたが失敗した。その後、グローバル会計の視点でERP(統合基幹業務システム)が導入されたが、これはパッケージソフトに人が合わせれば良かった。現在のRPAブームは、現場発の業務改革の機運を生んだ。これを業務全体の最適化につなげることが、デジタルトランスフォーメーション(DX)での目的になる」と述べた。
属人化した業務のプロセスを最適なものにするというBPRは、かつてその理想形を実現するにも人的な要因などに左右され、結果を手にできない企業が相次ぎ、日本では浸透しなかった。次にERPなどの登場で業務や手順の“標準化”という概念が出てきた。ただ、人に要求されたのは“形が決められた業務”への順応であり、システムによる処理を効率的に補完する役割が重視された。そこにRPAが登場し、人が果たしてきたこの役割すらも置き換え、システム化が始まっている。
歴史が長い、あるいは事業規模の大きな企業ほど、その内部には人が作り上げた膨大な業務プロセスが存在する。現代の担当者の多くは、その属人的なプロセスに潜む無駄や非効率性と格闘しながらも、プロセスを改善してより良い業務を実現するという本質的な取り組みを志向している。
講演の中では、日本ビジネスプロセス・マネジメント協会 理事の横川省三氏が、DXの目的を「優れた顧客体験の実現」と紹介した。RPAの出現により、業務プロセスを構成する作業のうち単純な繰り返しの作業は、RPAで人が手掛けなくて済むようになったが、単純で繰り返すだけではない作業は人が手掛けなくてはならず、さらに業務全体という広い視座で最適化を進めるのは、人にしかできないと話す。つまりRPAのようなテクノロジーは、業務から人を排除するのではなく、本質的な仕事に臨むための手段になる。人はテクノロジーを使って業務を変え、「優れた顧客体験」を実現させていくことで、新しい価値を生み出す。中山氏は、それがこの領域におけるDXの意義だと強調した。
業務変革をどう進めるか
講演の冒頭に登壇したリコーITソリューションズ 代表取締役 執行役員社長の石野普之氏は、リコーグループにおける働き方改革でのDXの目的を「生産性の向上ではなく働きがいの実現」と紹介した。リコーのビジネスは長らくオフィスの中の業務にフォーカスしてきたが、現在は在宅勤務やモバイルワークなど、働く環境はオフィスの建物内にとどまらない。そこで、働く環境がどんな環境でも手段であろうとも、「お客さまがより良く働けるようにデジタルでサポートすることを目指している」とした。

リコーITソリューションズ 代表取締役 執行役員社長の石野普之氏
同社が展開する施策は、例えば、複写機とクラウドサービスを基盤にエコシステムパートナーの多様なサービスを掛け合わせる「RICOH Smart Integration」や、モバイル活用などがある。基本的には、まずリコーグループ内で実践し、その成果を外部の顧客に提供するというスタンスだという。
その中で現在進めるのが、1994年から利用してきたNotesのリプレースになる。30年近く利用したこのシステムには、膨大な情報資産と約13万種類の業務アプリケーションがあるといい、さまざまな方策で現在と将来のビジネス環境に変えているところだという。主に、グループウェア/コラボレーション関連はMicrosoftのOffice 365に、情報資産管理(EIM)は自社開発してモバイルでも利用できるようにした。
13万種類の業務アプリケーションは、現状の棚卸しをして、その7~8割を捨てる決断をした一方、参照系など今なお利用の多いものは残し、トランザクション系の約5%のアプリケーションを「Intra-mart」でローコード開発を行っている。
石野氏によれば、Notesは“エンドユーザーコンピューティング”の概念から多様なアプリケーションを現場発で生み出し、業務の改善に貢献した。ただ、複雑でサイロ化したアプリケーション環境という弊害も伴った。そこでNotesのリプレースは(1)標準に基づく統制の確保、(2)教育、(3)開発者支援、(4)グローバル展開――の4つの基本原則を定め、バランスのとれた業務改革を進める。2020年春頃に実現を目指しているという。
RPAの後はどのように業務プロセスを最適化していくのか。数千台規模のソフトウェアロボットを開発、運用する住友林業情報システムでは、業務での各作業における共通的要素を中心としてソフトウェアロボットの“パーツ”を用意し、必要に応じて組み合わせることで短時間にRPAを開発できるようにした。同社では1日当たり10台のソフトウェアロボットが新たに稼働しているという。
だがICTビジネスサービス部 シニアマネージャーの成田祐一氏は、「ロボットでも足りないところが出てくる。さまざまな作業がつながる“業務”には人が介在する。ロボットと人が共創する仕組みが必要だと感じている」と話した。そこで現在は、BPM(Business Process Management)による取り組みを検討している。
オリックスグループ13社の36業務を担当しているオリックス・ビジネスセンター沖縄では、BPMを通じて各種業務の内容をプロセスレベルに応じて可視化している。そこで活用しているのが、BPMN(ビジネスプロセスモデリング表記)になる。
オペレーション事業本部 副本部長の平良一恵氏によれば、同社では23チーム総勢約800人が担当する755の業務プロセスをBPMNで可視化し、定義している。可視化することによって業務内容を一目で把握し、理解が深まる。そこからRPAなどテクノロジーを活用できる部分も明確になり、業務改革を担える人材の育成にもつながると紹介した。
日立製作所グループで情報通信システム関連のBPOを担当する日立ICTビジネスサービスでもBPMによる業務プロセスの現状を可視化するとともに、業務改革を担う人材の育成に注力する。エンジニアリングバリューチェーン本部の藤田繁郎氏は、RPAとBPMが必要だと述べ、同社ではBPMで可視化して1300のプロセスのうち200のプロセスでローコード開発によるスピーディーなアプリケーションの開発と実装に取り組む。
同社では、アプリケーション開発などのスキルを習得して業務改革を担う人材を育成する2カ月の研修を展開する。これを受講したという調達部の相良翔子氏は、「難しいテーマも多かったが、身近な課題などにも取り組みながら、最後は経営層に改革内容を提案するところまでを学べた」と語り、現場視点だけではなく業務全体を捉える観点からの方法を身に付けることができたという。
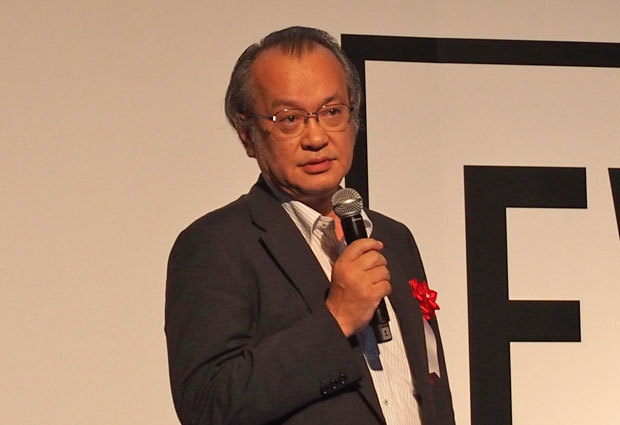
日本ビジネスプロセス・マネジメント協会 理事の横川省三氏
先述した日本ビジネスプロセス・マネジメント協会の横川氏は、DXの目的を「優れた顧客体験の実現」としたが、テクノロジーの適用領域が拡大しても、人間の感情といったアナログ的な要素とシステムをどうつなげるかという部分は必ず残り、そこは人でなければ担えないと語った。
最近では、アプリケーションやシステムのさまざまなログなどのデータを分析して業務プロセス全体を可視化し、改善方法などをシミュレーションできるプロセスマイニングといった手法も出てきている。横川氏は、RPAやローコード開発、プロセスマイニングといったこうしたテクノロジーを利用しながらデジタルによる新しい業務プロセスを構築し、「優れた顧客体験」という人にしかなし得ない取り組みを進めていくべきだと提起した。
業務プロセスの全体最適に向けた実践例としては、トッパン・フォームズ BPO統括本部の田村雅司氏、大同火災海上保険 取締役 情報システム部長の阿波連宗哲氏らが、それぞれの取り組みを紹介してくれた。





