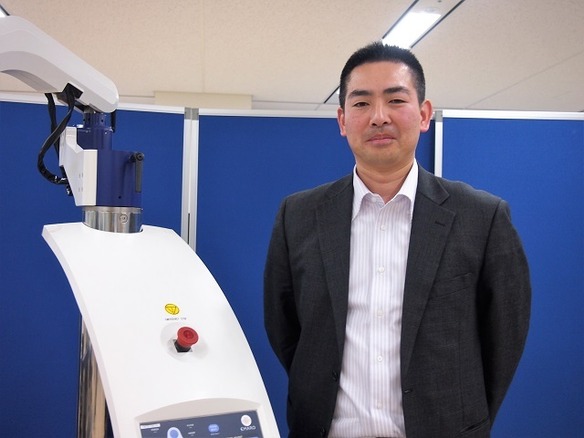--最初は大学内での研究だったということですね。
研究開始から10年以上、大学内での研究開発活動として技術の改良を続けており、研究室としては完成度の高い試作機もありました。その間、川嶋と、同じく創業者で研究をしていた只野(現 東京工業大学 准教授)は、研究した技術を世に出す方法を模索していました。大企業さんとのお話もあったのですが、そのオファーを断っても、自分たちの手でやっていきたいというモチベーションを持ち続けていたのです。
そんななか、東京工業大学でテックカフェという産学連携の推進イベントがあり、そこで知り合ったベンチャーキャピタルのジャフコの方に声をかけていただき、文部科学省のSTARTプロジェクトに応募することになりました。
--文部科学省のSTARTプロジェクトからは、具体的にどのような支援を受けましたか。
2012年に採択を受けてからの3年間、事業化準備に必要な資金の支援を受けました。そして、2014年に会社を設立しています。ジャフコには、事業プロモーターとしてパートナーになってもらいました。
--研究室と企業での、研究開発の違いはどういう部分にありますか。
企業の場合には、売り上げを上げるための模索を正当な事業活動として行えるのが特徴です。大学での研究開発活動は論文が成果なため、製品として良いものを作っても、研究としての新規要素がないと論文が書けないというジレンマがあります。例えば、装置の小型軽量化は製品としては重要ですが、同じ理論を使っている限りは、新しい論文にはなりません。
大学研究室での試作機の洗練化が可能な開発活動は限界に達していた時期に会社を設立できたことで、製品化に必要な開発が行えるようになりました。一方で、プロジェクトが大型で数十人規模のベンチャーで賄える規模ではなく、専門的な人材の確保や、システム上で必要な要素の開発規模が非常に大きいところは、難しい部分でもあります。
--大学発ということで、通常のベンチャーとの違いは何がありますか。
有望なシーズがあり、そこに資金がつき、大企業がパートナーとなって実現化するのがよくあるケースだと思いますが、当社の場合は、創業者が自分たちの技術を確実に世に出そうと、限られた研究資金の中でも自分たちで可能な限りの努力をして試作機の完成度を高めてきました。
そのため起業後も大学との結びつきが強く、製品化においても大学のノウハウを取り入れながらやっているのが大きな特徴でしょう。「手術支援ロボット」というワードには華やかなイメージがありますが、実際は泥臭い製品開発です。ものづくり技術で産業界に影響力のある東京工業大学が絡んでいることに安定感や安心感があるという点は、外部から堅実に評価されているのではないかと考えています。
また、製品開発は社内でやっていますが、次世代製品につながるようなシーズ研究は両大学と共同研究として進めています。医療機関の性格が強い東京医科歯科大学にて、製品のプロトタイプの評価を実施することもあります。