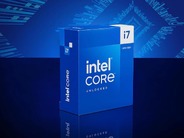新たなコラボレーション基盤の構築を目指す企業は、まず何を考慮すべきか。そして、長らく使い続けてきたNotes/Dominoからの移行を決断するのであれば、そのプロジェクトはいかに進めていくべきか。
今回は、「Notesマイグレーション」をサービスとして提供している日本ユニシスに、移行ユーザーが実際に直面する課題や、Notes移行プロジェクト成功の秘けつについて、これまでの事例をもとに話しを聞いた。彼らは、SIベンダーとして、どのように移行を検討するユーザーをサポートしようとしているのだろうか。
Notesマイグレーションブームの2つの波
Notesマイグレーション(本稿では、Notes/Domino自体のバージョンアップと他社製品への乗り換えの両方の意味を含む)には、過去いくつかの節目があった。まず、マイクロソフトが「SharePoint Portal Server」をリリースした直後の2004年ごろ。Notes/DominoのR4.5やR4.6を利用しているユーザーに、最初のマイグレーションブームが起こった。R4.xのサポート切れに、OSであるWindows NT 4.0のサポート停止も重なり、Notesに代わる新たな技術基盤にも関心が向いた。それが“Notesマイグレーション第1の波”といわれる。しかし、当時は移行の難易度やコストが障害となって、計画が頓挫する案件も少なくなかったという。また、多くのユーザーにとって、Notes/Dominoを完全にリプレースできる要件を満たす製品が、市場に見あたらなかったという事情もある。
その際、多くのR4.xのユーザーはあえて大きなリスクを負うことを避け、R6やR6.5へのバージョンアップに踏み切り、移行ブームは一旦沈静化した。しかし、その後、マイクロソフトは、SharePointの機能強化を続け、市場においてもそのメリットが次第に認知されるようになる。
その後、2007年4月にNotes/Domino R6のサポートが終了したのを契機に、再びマイグレーションブームが起こる。R7やR8で、先進性を高めるために行われたアーキテクチャの変更は、結果的に旧バージョンのNotes/Domino上で作り込まれたアプリケーションの移行をさらに難しいものにしてしまった。皮肉にも、そうしたユーザーにとっては、Notes/Dominoでのバージョンアップをするのも、他の基盤へ移行するのも、手間とコスト的にはそれほど代わらない選択肢になってしまったのである。それが現在も続く“Notesマイグレーション第2の波”の端緒である。
第1の波では、企業活動に必須となったITによるコラボレーション基盤を、いかに低コストで維持するかが議論の中心となったが、現在巻き起こっている“第2の波”では、ワークスタイルの変革や情報系の見直しといった、より大きなテーマの中で、Notes/Dominoを使い続けるか否かが問われている。こうした課題に対して、経営層が企業活動全体のビジョンに直結するものとして検討するケースが増えているという。