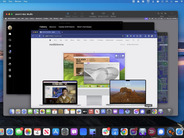日本経済新聞の「やさしい経済学」の連載で、新しい事業価値を創造するための枠組みとして“SEDA”モデルというのが紹介されていた(3月13日朝刊、延岡健太郎氏=一橋大学教授)。SEDAとは、サイエンス、エンジニアリング、デザイン、アートの頭文字で、サイエンスとエンジニアリングは機能的価値を実現し、デザインとアートは意味的価値を実現するものとされている。
なかでもデザインとアートの違いとは、デザインが「顧客の要望に合わせる」ものであるのに対し、アートは「顧客に新しい意味を提案する」ものであるという。
では「新しい」とは何だろう? 例えば車であれば、一般的には新しく発売されたモデルであって、さまざまな自動制御が付いていたり、ハイブリッドであったりと、今までにない機能が付いているということだ。これはデザイン的には顧客のニーズに応えていて新しいと言えるのだが、アート的には決して新しくはないようだ。美術評論家のBoris Groys氏によると、「Kierkegaardによれば新しい車などというものは存在しない」(『アート・パワー』P50)のだという。
Kierkegaardが車について述べた訳ではないだろうが、Kierkegaardは、差異が差異として認識できるならば、その差異はもう新しくないとした。つまり、ハイブリッドが新しい機能だとしても、それをそう認識できる時点でもはや新しくないのである。
アートの世界での新しさとは、「過去の慣習によって規定され美術館のコレクションには受け入れられない」ものでなくてはならず、受け入れられたらすでに新しくないということだ。
アートの世界は何でもありである。しかし、その価値が認められるためには、それはその差異が認識できないほどに新しくなくてはならない。
ビジネスにおいて、新しい価値が価値として認められないが故に、気が付かないうちに新興企業が大手企業のマーケットを破壊してしまうことがある。いわゆる「イノベーションのジレンマ」における「破壊的イノベーション」である。
この破壊的イノベーションは、顧客の要望に合っていないが故に、その差異は評価されることはない。そして、その差異に価値があると認められたときには、大手企業は大きく出遅れこととなる。
アートの世界で新しすぎて既存の芸術との差異として認識できないものは、例えばMarcel Duchampの「泉」などが当たるだろう。これは小便器を横倒しにして「泉」とタイトルを付けただけのものである。無審査の美術展にすら出品を拒否されるほどにその存在は無視され、それゆえにその新しさは際立った。
そして、同じような発想が企業のイノベーションに求められるならば、大企業がイノベーションのジレンマを乗り越えるのは容易ではない。皆が普通にキャンバスに絵を描いているなかで、便器にタイトルを付けて作品と言い張る社員を評価しなくてはならないのである。
日本経済新聞のコラムを執筆した延岡氏も既存の価値の深化と、新たな価値の探索を両立するのは難しいと言っている。イノベーションにアートが求められのであれば、これは一企業に閉じて考えるよりも、多様な人材を受け入れ、挑戦と失敗を許容する社会の仕組みとして実現することの方が現実的であるかもしれない。
そういう意味で、これまでのアメリカはとても強かったと言える。
飯田哲夫(Tetsuo Iida)
アマゾンウェブサービス ジャパンにて金融領域の事業開発を担当。大手SIerにて金融ソリューションの企画、ベンチャー投資、海外事業開発を担当した後、現職。金融革新同友会Finovators副代表理事。マンチェスタービジネススクール卒業。知る人ぞ知る現代美術教育の老舗「美学校」で学び、現在もアーティスト活動を続けている。報われることのない釣り師