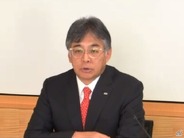岡田:量子コンピュータを実社会で使うためには、大規模な問題への適用と高速化・高精度化にまだまだ現時点では課題があると考えており、共同研究を実施しているところです。
特に高速化については、断熱定理と呼ばれる量子アニーリングの核について、再検討を加えました。非常にゆっくりと量子アニーリングを実行すると、確実に最適解を得られるという保証を与える数学的な定理です。

失敗する原因をつかむにはここを追求するべきだと考えました。これまでに考えられているメカニズムとは異なるメカニズムが、量子アニーリングの性能に影響を与えていることを突き止めました。
6月のAQC2017で発表しましたが、やはり皆さん大きな課題意識を持っているようで、関心の高さがうかがえました。
9月の日本物理学会でその進展について報告したいと思います。さらに2018年のAQC2018がNASA Ames研究所で開かれるということですから、そこで多くの研究成果を披露したいと思います。
――ありがとうございました。
*****
インタビューから日本を代表する企業と大学が手を組み、新しい技術を利用したシステムやサービスづくりの基礎を構築している様子がうかがえる。
量子アニーリング研究を実施する一員として日々感じていることは、単なる基礎研究では感じることのないものだ。
研究を実施して、その成果を出すたびに世の中が変わっていくような不思議な感覚と、周囲のスピード感と迫力、ダイナミズムを感じるのだ。
それだけ世界中が注目しており、新しいアイデアと技術が次から次へと生み出されているのが、この分野である。そのため多くの人が関わり、さまざまな出会いをする。
このデンソーの研究者たちと出会えたことも非常に幸運な巡り合わせだ。
今後も日本の産学連携の一つの代表例として、世の中に新しい成果をもたらしていきたい。
- 大関 真之(おおぜき まさゆき) 東北大学大学院情報科学研究科応用情報科学専攻准教授
- 博士(理学)。京都大学大学院情報学研究科システム科学専攻助教を経て現職。専門分野は物理学、特に統計力学と量子力学、そして機械学習。2016年より現職。独自の視点で機械学習のユニークな利用法や量子アニーリング形式を始めとする新規計算技術の研究に従事。分かりやすい講演と語り口に定評があり、科学技術を独特の表現で世に伝える。