一般社団法人日本CPO協会(CPOA)が設立され、1月20日にオンラインで設立記者会見を行った。⽇本のソフトウェアプロダクトをグローバルで通用する水準に引き上げることを目的にしている。クラウドサービスやeコマースなどのソフトウェア領域においてCPO(Chief Product Officer)やVPoP(VP of Product)、PdM(Product Manager)を対象に、プロダクト開発に関する国内外の事例や企業の知⾒を共有する。プロダクトマネージャーを育成し、日本のソフトウェア業界におけるモノづくりを強化することを⽬指すという。
日本CPO協会で対象とするプロダクトは、工業製品のように手に取れるものではなく、クラウドサービスやeコマースをバッケージングしたものとしている。

日本CPO協会 代表理事でメトロリー CEO兼CPOのKen Wakamatsu氏
代表理事に就任するメトロリー CEO(最高経営責任者) CPOのKen Wakamatsu氏は、「4年間で国内200社以上を訪問して企業とプロダクトの関係を探った結果、日本のプロダクトづくりの課題は、優秀なエンジニアやデザイナーが多いものの、その能力をプロダクトづくりに生かすことができる設計者が少ないことが分かった」と述べた。
米国では、7~8人のエンジニアに対して必ず1人のプロダクトマネージャーが存在し、CTO(最高技術責任者)やCFO(最高財務責任者)と同様に、CPOが設置されることが一般的だとする。CPOやプロダクトマネージャーが事業部の戦略や目標、ユーザーニーズといった複数の要素をプロダクトに落とし込み、ユーザーに届ける価値を明確にしているとし、「それが世界に通用するサービスが次々と登場する理由の一つだと考えている」(Wakamatsu氏)と話した。
続けてWakamatsu氏は、「日本では、一人の顧客のために、システムインテグレーターがシステムを受託開発することが多いが、プロダクトはその逆。あらゆるユーザーが同じものを使うことが前提になっている。日本でもプロダクトが広がっているが、提供企業側の課題は、プロダクトをリードする人材の重要性が理解されていないこと」とした。
同氏によれば、世界中のユーザーが使いやすいと感じるものを生み出すには、エンジニアやデザイナーの能力を生かし、ベストプラクティスを理解し、プロダクト全体を設計し、リードする人材が必要になる。だが、その人材が少なく、同時にそれを学ぶための仕組みがないという。「日本のプロダクトをグローバルで通用させるには、プロダクト開発における生きた情報が必要。日本に海外の知見や事例を届け、アイデアを交換できる場を設けることで、世界で戦える水準に高めたい」とした。
Wakamatsu氏は、両親は日本人だが、米国で生まれ育った経験を持ち、マクロメディアやアドビ、シスコなどを経てセールスフォース・ドットコムに入社。2016年に同社日本法人に出向し、同社初のプロダクトマネージャーとして、プロダクトマネジメントチームを⽴ち上げた。現在はメトロリーを設立し、交通費精算を人工知能(AI)で自動化するサービスを提供している。
「幼少期に、ソニーや任天堂といった⽇本のハードウェアプロダクトが⾝近にあり、誇らしく感じたことを覚えている。米国のエンジニアには、こうした日本のハードウェアプロダクトに触れて育った人が多く、日本のソフトウエェアプロダクトに期待している人も多い。日本から世界に通用するプロダクトを生み出すことに貢献していきたい」と語った。
日本CPO協会 理事の大津裕史氏(Sansan執行役員 CPO)は、世界のクラウドサービス市場規模が2014年から5年間で約3倍に成長し、2021年には約3500億ドルになること、またMM総研の調べで2019年の国内クラウドサービス市場が前年比21.4%増と成長し、2024年まで年平均18.4%増で成長するといったデータをまず示した。
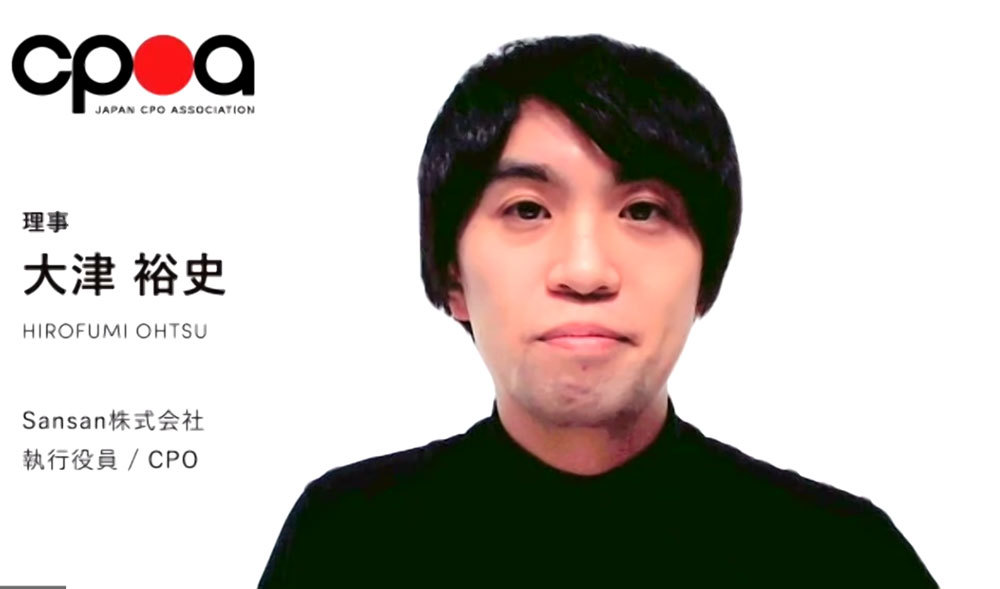
日本CPO協会 理事でSansan 執行役員 CPO大津裕史氏
その一方で、「クラウドサービスなどを提供する企業のうち、CPOがいる企業は66%、VP of Productがいる企業は72%にとどまる。自社でプロダクトを開発してもリードする立場の人材がいない企業が3分の1もあるのが日本の実態。米国ではこうした人材がいない企業の方が珍しい」と指摘する。
また、人材投資を増やしている企業は日本で22%にとどまり。市場やニーズが拡大しているにも関わらず、サービスを提供する側の人材に投資する企業が少ないとする。米国ではプロダクトマネージャー向けの勉強会や交流会が活発なのに対し、日本では機会がなく海外の最新情報や新たな刺激を得ることができず、サービス提供側の組織体制や投資が追いついていないと指摘した。
「このまま世界に通用するサービスが生み出せず、日本のクラウドサービス市場が成長すれば、それは海外で作られたサービスが日本に展開される、日本経済にとって残念なこと。日本企業が世界に通用するサービスを生み出すことは、日本経済の発展にも重要な挑戦」(大津氏)
同協会は、具体的な活動として、メディア運営、イベントの開催、調査レポート発行の3点を挙げる。
メディア運営では、⽶国のクラウドサービスを中心に、現役で活躍しているCPOやVPoP、PdMに独⾃にインタビューを行い、同協会のウェブサイトに掲載。「これまで⽇本国内ではほとんど知る機会のなかった、海外のプロダクトづくりの取り組みや事例について発信する」(Wakamatsu代表理事)とした。2月中旬に第1弾として、ServiceNow プロダクト責任者のMarcus Torres氏のインタビューを公開するという。
イベントの開催では、国内でプロダクト提供する企業向けに、定期的なオンラインイベントを開催。プロダクト開発にまつわる事例の発信や、プロダクト企業同士の情報交換の場を提供する。6月には、1000人規模の集客を⽬指す日本初のプロダクトマネージャー向け大型オンラインイベントを予定している。
調査レポートの発行では、国内外のプロダクトづくりに関する意識、実態に関する調査レポートを定期的に発行する。特に、国内プロダクト提供企業における⼈材への投資や組織体制に関する調査を定期的に実施し、プロダクト開発に対する意識変化や実態を明らかにするという。
協会発足に合わせてソフトウェアサービス企業のCPOやプロダクトマネージャーが理事メンバーとして参加。会見では各理事もコメントした。
「多様なプロダクト開発メンバーが優れたアウトプットを出すには、プロダクトマネージャーのスキルセットが重要になる。あいまいなコミュニケーションを排除するなどの基本動作はもちろん、さまざまな手法論を用い、スケジュール管理、コミュニケーションの取り方などが重要になる。グローバル視点での情報が共有できるようになることに期待している」(メルペイ 執行役員 CPOの伊豫健夫氏)
「米国では3~4割が女性のプロダクトマネージャーだが、日本ではまだ少ない。プロダクト開発において、多様な視点が十分にないことは日本企業の課題。新たな道を開いていくことが必要。プロジェクトマネージャーを目指す女性の勇気になりたい」(XTalent 執行役員の松栄友希氏)
「当社は、さまざまなバックグランドを持った社員の集合体。また、スモールビジネスを対象にしたSaaSビジネスを展開している。ユニークな体制で培ったノウハウを、社内にとどめるのではなく、国内外に発信していきたい」(Freee VP of Product Managementの宮田善孝氏)
「日本を含むアジアのエンジニアの力を束ねて、アジャイルの開発を導入しながら、日本のDX(デジタル変革)を推進する中で、幅広い企業において、モダンな環境で開発が推進できるようにノウハウを共有したい」(ラクスル 執行役員 CPOの水島壮太氏)
「かつてはプロダクトマネジメントに関する情報が少なく、私自身、初歩的な間違いも経験してきた。この多くは知識があれば防げたものだと考えている。プロダクトマネージャーの間違いが、会社の存続につながることがある。活動を通じてプロダクトマネージャーが必要とする情報を提供したい」(SmartHR 執行役員 VP of Productの安達隆氏)
「HRテックの領域では、働いている一人ひとりにフォーカスを当てたワークテックの概念が持ち込まれつつある。それに対応したプロダクトの開発、設計の難易度が高まっている。これからの社会の求められるプロダクトは何かといったことを議論し、当社のサービスで培ってきた知見を還元したい」(ビズリーチ 執行役員の古野了大氏)

日本CPO協会の理事メンバー
なお、協会の活動を支援する協力会社として、クアルトリクスとグッドパッチが参画することも発表された。





