同氏が言う「オープンハイブリッドクラウド」とは、オンプレミスを含むプライベートクラウドとパブリッククラウドを行き来でき、両方のメリットを享受できるオープン環境を指しているようだ。オープン環境なのは、LinuxだけでなくIaaS環境構築管理ソフトウェアのOpenStackもオープンソースソフトウェアであることから明らかだ。
考えてみると、Totton氏がRHELの変遷として語るOSからクラウド基盤への移行は、まさしくコンピューティングそのものの進化といえそうだ。
「医療ビッグデータなどを核にした新たな情報活用基盤の構築を目指していきたい」 (富士通 合田博文 執行役員)
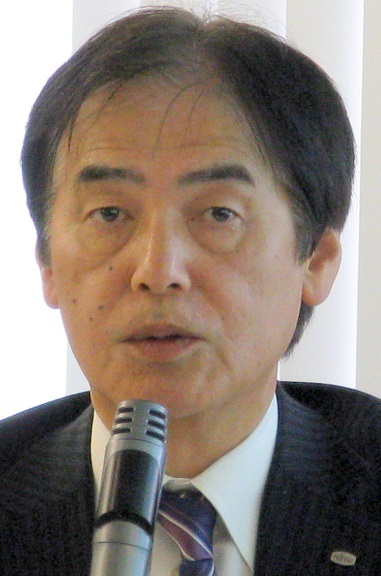
富士通 執行役員 合田博文氏
富士通が先ごろ、ヘルスケア事業に関する取り組みについて記者説明会を開いた。冒頭の発言は、同事業の陣頭指揮を執る合田氏が今後の活動へ向けて意気込みを語ったものである。
富士通はヘルスケア分野において、1975年から医事会計システムを手掛け、1986年からオーダリングシステムで病院内の業務効率化を支援、1996年から電子カルテシステムで院内全体の情報共有を図り、2006年から地衣医療を連携することで地域全体の情報情報共有に取り組んできた経緯がある。
会見の全容については関連記事を参照いただくとして、ここでは合田氏が説明した同事業の中核組織となる「未来医療開発センター」について少々紹介しておこう。
2013年12月に設立された未来医療開発センターは、超高齢社会における健康増進や重症化予防、疾患の早期発見、新薬創出、個別化医療などの実現にICTを活用しながら、研究機関、製薬企業、医療機器ベンダーなどとの協業も図ってヘルスケア事業を推進する社長直轄の社内横断組織だという。
同センターのミッションとしては、「国家プロジェクトから創出される次世代医療情報システムビジネスの開拓」「ゲノムなどのバイオバンクや電子カルテ診療情報を統合した医療ビッグデータビジネスの創出」「スパコンを活用したシミュレーションビジネスの企画、推進」「IT創薬を目的とした化合物設計サービスの事業化推進」などが掲げられている。
合田氏はヘルスケア事業の取り組みについて、「これまでの実績をもとに、今後は医療ビッグデータや次世代電子カルテ、治験、創薬などを核にした新たな情報活用基盤の構築を目指していきたい」と語った。冒頭の発言は、このコメントのエッセンスである。
同社ではこれらの事業展開によって、2013年度で1000億円余りだったヘルスケア事業の売り上げ規模を5年後の2018年度には2000億円に倍増させる構えだ。
ただ、同事業分野は今後の有望市場と見られているだけに、最近においても医療のICT化とともに医療機器なども幅広く手掛ける東芝や日立製作所が同事業へ一層注力していくことを明言している。今後はさらに激しいサバイバル競争が繰り広げられることになりそうだ。
Keep up with ZDNet Japan
ZDNet JapanはFacebook、Twitter、RSS、メールマガジンでも情報を配信しています。






