富士通は2015年5月に発表した「FUJITSU Knowledge Integration」を具現化し、共創サービスを体系化する取り組みを5月12日から提供を開始した。さまざまな取り組みを通じてサービスを実装する。5月23日から富士通ソリューションスクウェア内に「FUJITSU Knowledge Integration Base PLY」を開設する。
デジタルテクノロジの進化で人々の生活スタイルが変わり、これを活用したより快適なサービスへのニーズが高まっている。
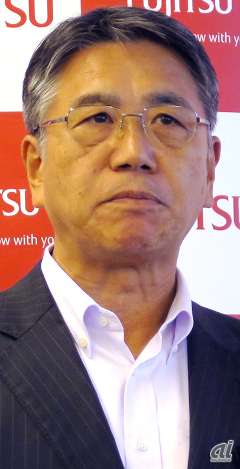
富士通 取締役 執行役員専務 グローバルサービスインテグレーション部門長 谷口典彦氏
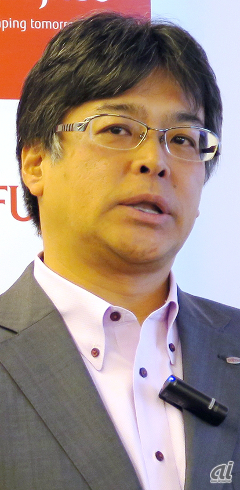
富士通 執行役員 グローバルSI部門 金融システム事業本部長 時田隆仁氏
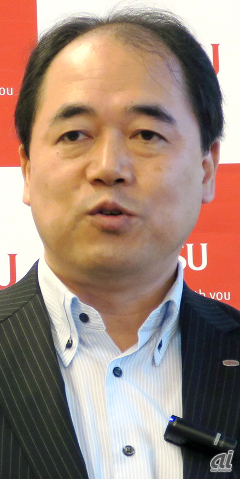
富士通 グローバルSI部門 グローバルSI技術本部長 中村記章氏
谷口典彦氏(取締役 執行役員専務 グローバルサービスインテグレーション部門長)はデジタルイノベーションに伴い、「社会・産業」「顧客との関係」「組織運営・働き方」と3つの流れが生まれていると語り、「今」に適したサービスを提供するためには、ユーザー企業や消費者の潜在的欲求にITベンダーの持つICT利活用のノウハウを連携させ、企画、開発する共創が効果的だと自社のポリシーを説明した。
谷口氏は、基幹系システムや業務システムの“Systems of Record(SoR)”では継続的業務改善サイクルであるPDCAが有効ながらも、イノベーションを創造する“Systems of Engagement(SoE)”では「OODA」ループが重要だという。
OODAループは米空軍軍人が提唱した監視(Observe)、情勢判断(Orient)、意思決定(Decide)、行動(Act)という意思決定理論だが、富士通では知識機動力経営の実践とSoEの実現にOODAループが欠かせないと説明した。
だが、SoRとSoEを異なる存在として認識しながらも区別することなく両立し、富士通の蓄積してきた知見やノウハウを実装、そしてユーザー企業との提携で統合するのがKnowledge Integrationの主目的だと説明。「人と人、人とモノ、モノとモノとのつながりが大事。知識を横につなげることで新たな価値を創造する」(谷口氏)と意気込みを語った。
富士通はKnowledge Integrationを具現化するため、4月1日付けで組織を変更している。
グローバルデリバリ部門とインテグレーションサービス部門を統合したグローバルサービスインテグレーション(GSI)部門を設立。専任30人規模の社員がプロデューサーとしてフロントに立って、ユーザー企業と技術部門となるデジタルサービス部門とサービスプラットフォーム部門と連携し、新たな取り組みや新技術の活用をワンストップで実践する。
SoRとSoEの両者に対する富士通のビジネスアプローチについて時田隆仁氏(執行役員 グローバルSI部門 金融システム事業本部長)は「データやロジックが安定すればSoEからSoRに移管する場面も出てくる。両者を連携させるシステムが大事」と説明した。
具体的には現行の基盤システムのAPIをクラウドから活用し、機能単位でSoRをスリム化するアプローチ、機能単位でSoRをスリム化してクラウドに移行させるなど経営リソースの最適化を提言している。すでに概念実証(Proof of Concept:PoC)や事業実証(Proof of Business:PoB)を多くのケーススタディを重ねてきた。
共創サービスについて中村記章氏(グローバルSI部門 グローバルSI技術本部長)は「共創はデジタルビジネス時代には欠かせない取り組み」と語り、これまで同社の取り組みを体系化し、共創サービスとして展開する。一方的に価値を提供するのではなく、ユーザー企業とともに新たな価値を生み出すため、あえて“プログラム”という呼称を用いたという。
共創サービスは「情報収集・問題発見」「アイデア創出」「サービスの実装」の3レイヤに分かれる。






